


『THE ハプスブルク』展
京都国立博物館
2月12日、2月21日の二回、『THE ハプスブルク』展を楽しんだ。
まずはじめは一人で。歌舞伎教室と抱き合わせで3時間余鑑賞。
二度目は関西に帰ってきていた子どもと一緒に。『古代カルタゴとローマ展』と抱き合わせてみた。
『THE ハプスブルク』展は素晴らしい作品がこれでもか、これでもかと展示されている。
流石、栄華輝くハプスブルク家のコレクションだ。
美術におけるパトロンとしてのハプスブルク家の業績は計り知れないものがあるだろう。
素晴らしい作品が多いので、はじめの部屋(明治天皇からの贈り物)から丹念にみすぎると時間がいくらあっても足りない。
わたしは『THE ハプスブルク』展は二度みたが、まだ見たい。もう一度見に行きたいという絵が多い。
時間や条件が許される方は、是非足をお運びになっていただき、自分の目で確かめていただきたい。
好むと好まざるに関係なく、素晴らしすぎる作品、話の面白い作品が多いことに気づかれることだろう。
ところで申し訳ないのですが、今月初旬のわたしは目が回るほど忙しい。
好きだった『THE ハプスブルク』展はメモをとり丹念にみたし、印象に残るものも多かったが、今回は要点だけ書き留めることにした。
先ほども記録したようにこの展覧会は素晴らしい展示物が多すぎる。
時間に余裕の無い人で展覧会を見に行かれる方は、まず会場を駆け足でざっと見て回っていただきたい。
自分の目で確かめたあと、好きな作品をじっくりみていただくと満足いただけると思う。
次に各国の特徴を捉えてもう一度みて行くと面白い。
肖像画は何も言わずとも、足が止まるであろう。
まだ時間に余裕があるようなら最後の部屋の美術工芸品を頭に末(或は絵画をしっかりおさえておき、工芸品を探す)、もう一度絵画の中で探すなども楽しいものだ。
今回の展覧会の目玉はなんといっても 肖像画。
ハプスブルク家でもいちばん高い地位を与えていたと説系が記されていた。
この部屋は素晴らしいものが多すぎる。
女性はあくまでも美しく、男性は威厳高く描かれている。
いちばん大きな肖像画(フランツ・クサファー・ヴィンターハルター オーストリア皇妃エリザベート)はローアングルで8頭身以上のスタイルだが、顔は真正面で若々しく描かれていた。
また男性を描いた肖像画の衣服の色彩にも注目していただきたい。
衣服を色彩で強調し広げ バックの色彩と調和させることにより、結果目の錯覚を用いて男性を大きく見せるといった趣向を凝らした絵が多く見られるーーーはずだと、わたしが勝手に思っている。
肖像画の中には写実にに徹したもの、病弱な子どもの長生きを祈願して呪術的飾りを身につけさせたもの(ベラスケス)、ハプスブルク家でもいちばんの画家に対するパトロンなど興味深いものが多い。
ベラスケスは二点ある。こちらは見逃せない。
肖像画以外にも わたしが好きだった絵は数多くあった。
時間がないので、今回は二つだけ紹介したい。
ひとつは オランダ絵画のルーベンス2点 及びルーベンスと工房1点。
ルーベンスの『キリスト哀悼』は部屋を入ってすぐ左に10号内外の小さな作品だが、力強い。
また右に二点。こちらは200号はあるだろうか。いずれも素晴らしい。
そのうちの一点は上(写真)に載せたペーテル・パウル・ルーベンスの『悔悛するマグダラのマリアと姉マルタ』である。
この絵は娼婦であるマグダラのマリアとそれを見守る姉マルタの対比が非常にも面白い。
絵を見ていただくとわかるように
動と静
赤と黒
光と影
陽と陰
といった形でマグダラのマリアとそれを見守る姉マルタが描かれている。
流石、ルーベンス 。天才である。
。天才である。
この絵を見るのに、ベンチが無いのが残念。わたしは柱にもたれこれらをかなり長い間(といってもほんの10分間くらいだからたいしたことは無い)楽しんでいた。
あとひとつはルーカス・クラナッハ(父)の『洗礼者聖ヨハネの首を持つサロメ』
上の写真の中で生首を持ったものだ。
これは絵が好きな訳ではない。話が興味深い。
母親にベールをかぶり衣裳を着て踊るように言いつけられたサロメは母に次のような要求をしたという。
「ヘロデ王の首を・・・。」
彼女の要求はかなえられ、満足感に満ちた顔が何とも怖い。
この絵は美しいサロメと痛々しい生首の対比を楽しむとわかりやすい。
今回は駆け足で記録した。
好きな作品画多くあったにもかかわらずッ少ししか紹介できなかったことが残念。
京都ではもう少し展覧会が開催されている。
先ほども書いたが、機会があれば是非みていただきたい内容深い展覧会であった。
『THE ハプスブルク』展HPより ▼
ブダペスト国立西洋美術館(ハンガリー)
日本とオーストリア・ハンガリー二重帝国(当時)との間の修好通商航海条約締結140周年を記念して様々な文化行事が催されていますが、ウィーン美術史美術館がブダペスト国立西洋美術館と共にご紹介する本展覧会は、その中でも際立って大規模なものであり、また当館が過去数十年の間に日本で行ってきた展覧会の中でも、最も重要で大きなもののひとつです。
ウィーン美術史美術館とブダペスト国立西洋美術館が誇るオールドマスターの傑作を、2009年9月より東京の国立新美術館、2010年1月より京都国立博物館にてご覧いただけます。ティツィアーノ、ティントレット、ベラスケス、ジョルジョーネ、ルーベンスそしてヴァン・ダイクらが、日本とオーストリア、ハンガリー両国との友好140周年を華やかに盛り上げてくれることでしょう。本展には宝石細工やエキゾティカと呼ばれる外来の珍品、ブロンズ像など、クンストカンマー(工芸館)から選りすぐられた作品も出品されます。そして特筆すべきは、日本・オーストリア交流年2009を機に、明治天皇からハプスブルク宮廷に贈られた画帖が、記念すべき初の里帰りを成し遂げることです。
なるべく多くの方々にこの素晴らしい展覧会へ足を運んでいただけるよう願っています。
ウィーン美術史美術館総館長
サビーネ・ハーグ
歴代皇帝や王妃などの威風堂々とした姿を現代に伝える宮廷肖像画。権力者たちの豪華な装身具やドレスが細かく描きこまれ、600年以上続いた栄光のハプスブルク家の歴史に思いを馳せる扉へと誘います。シシィの愛称で知られるエリザベート皇妃の肖像画も特別出品致します。
アンドレアス・メラー
11歳の女帝マリア・テレジア
フランツ・クサファー・ヴィンターハルター
オーストリア皇妃エリザベート
フランツ・シュロッツベルク
オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世
ジョルジョーネ
矢を持った少年
ティツィアーノ
聖母子と聖パウロ
歴代コレクターたちが常に関心を寄せていたイタリア。絵画だけでなく、彫刻や建築、音楽まで芸術全般にわたり、イタリアはハプスブルク宮廷の模範であり続けました。ジョルジョーネやティツィアーノらヴェネツィア派の傑作をはじめ、コレクションの重要作品を中心としたイタリア絵画を紹介します。
アルブレヒト・デューラー
若いヴェネツィア女性の肖像
ルーカス・クラナッハ(父)
洗礼者聖ヨハネの首を持つサロメ 16世期初頭、ドイツではデューラーやクラナッハらの巨匠が活躍し、皇帝マクシミリアン世らの宮廷や、裕福な商業都市から数多くの注文が寄せられました。この二人のほか、17世紀に活躍したヨーハン・リスの作品なども展示し、黄金期のドイツ絵画を紹介します
ヤン・ブリューゲル(父)
森の風景
ペーテル・パウル・ルーベンス
悔悛するマグダラのマリアと姉マルタ
皇帝ルドルフ2世や大公レオポルト・ヴィルヘルムらは、オランダ・フランドル地方出身の画家たちを大勢雇い入れており、テニールスなどのようにコレクションの管理官を務めた画家もいました。この地方を代表する画家、ルーベンス、ヴァン・ダイク、レンブラントらの傑作を紹介します。
ディエゴ・ベラスケス
白衣の王女マルガリータ・テレサ
ディエゴ・ベラスケス
皇太子フェリペ・プロスペロ
バルトロメ・エステバン・ムリーリョ
悪魔を奈落に突き落とす大天使ミカエル 16世紀、カール5世によって初めてハプスブルク家に統治されたスペインでは、同国の画家が大勢宮廷に雇い入れられました。中でも巨匠ベラスケスは、国王やその家族など、芸術性の高い肖像画を数多く残しています。18世紀にかけて活躍したムリーリョやエル・グレコらスペインの代表的作家の名作をご堪能ください。
作者不詳
ラピスラズリの鉢
ジョヴァンニ・バッティスタ・フォッジーニ
貴石の象眼の小箱
ハプスブルク家の審美眼は絵画にとどまらず、工芸品にも注がれました。コレクションが全盛を迎えた16-17世紀の作品を中心に、王族の優雅な生活を感じさせる豪奢な彫刻や工芸品の数々をお楽しみください。



























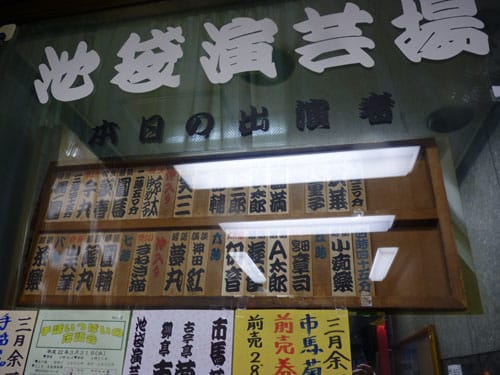


























































 。天才である。
。天才である。






