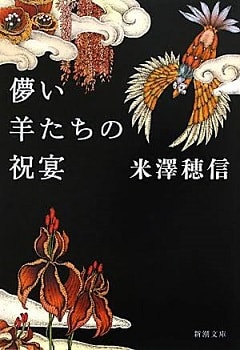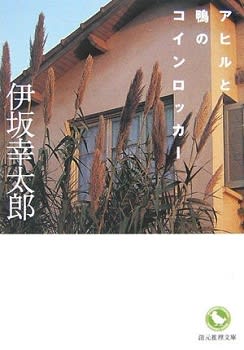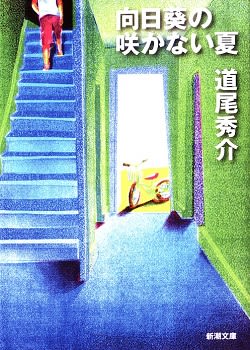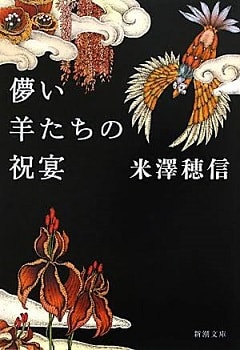
儚い羊たちの祝宴 米澤穂信
2008年作品
米澤穂信ラッシュでごめん!
5つの屋敷・5人の令嬢・5人の使用人と、それを取り巻く人々のノワール小説。
時代設定こそ名言されていないものの
前時代的封建的な上流階級の群像劇。
登場する令嬢がいずれも「バベルの会」なる読書会に参加しており
具体的にどんな会なのかはほとんど見えないものの、
最後の一篇で明かされる仕組み。
以下、各作品のあらすじと感想。
『身内に不幸がありまして』
物語は丹山家に仕える村里夕日の手記で進んでいく。
当主の孫にあたる吹子とは立場を超えた絆で結ばれていて
共に読書を嗜むのを至上の喜びとしていた。
しかしある時、丹山家より勘当された長男の宗太が屋敷を襲い
使用人たちを惨殺してしまう。
作中に出てくるあるアイテムが事件の重要なキーとなっているものの
おそらくそれを元にして真相を見抜ける読者はいないはず。
にも関わらず、知っていればいるほど
ネタを明かされたときの悔しさが増幅する見事なトリック。
寒気を覚えるほど凄惨なストーリーも横溝テイストでナイス。
『北の館の罪人』
六綱家の妾の子である内名あまりは母の死に際の言葉に従い
使用人として六綱家に住み込むことになる。
しかし、世話を任されたのは鉄格子で封じられた「北の館」。
そこには六綱家の長男である早太郎が監禁されているが
それを苦にすることなく、部屋にこもって何かの作業をしている。
こちらも1作目と同じく、早太郎から買い出しに頼まれる様々な品物が重要。
また、ミステリ部分とは別に、兄妹たちの確執が退廃文学を想わせて
5篇の中でも美しさと儚さがもっとも際立っている作品。
何重にも閉ざされたシニカルという名のカーテンを一枚ずつ開けていく
ラストの余韻がたまらない。
『山荘秘聞』
辰野家の別荘の管理を一人で任されることになった使用人の屋島。
美しい地に建てられた美しい館が心から気に入ったため
その手腕で日々完璧な維持管理を務めていたが
一年経っても客がまったく訪れないことにもどかしさを感じていた。
そんなとき、屋敷の庭に雪山登山で滑落した青年を発見する。
いわゆる倒叙型のサスペンス。
青年を捜しにきた捜索隊をもてなしたいがために秘密を隠し続けるという
歪んだ仕事愛に震えつつも、その高い能力を評価して欲しい気持ちへの共感も
密かに抱かせる屋島というキャラ。好き嫌いは読者によって分かれそう。
個人的にはこういった自分の意思を貫くために能力を発揮するキャラが好き。
『玉野五十鈴の誉れ』
小栗家の唯一の跡取りである純香と屋敷の全員は、
絶対的な権力を持つ祖母に逆らうことは許されなかった。
そんな純香の15の誕生日に使用人として玉野五十鈴が与えられ、
生きる目的のなかった純香にとって最高の友人となる。
大学へ進学し、五十鈴と二人きりで送る生活は幸福の絶頂だったが
小栗家の婿である父の家系で殺人が起き、
純香は汚れた血の娘として座敷牢へ入れられてしまう。
純香と五十鈴の関係がたまらなく耽美で
読んでいる側も思わずニヤニヤしてしまう。
座敷牢に入れられている最中に起こる事件に関しても、
真相が推測可能な程度にヒントが散りばめられているので
率直に言ってミステリ的には大したことなかったかな…と思ったけれど
ラスト一行を読んだ瞬間、喉から「お゛お゛お゛ぉ…」という呻き声が漏れた。
ここまで美しく悪趣味な文章は滅多にお目にかかれない!!
『儚い羊たちの晩餐』
これまでの作品に出てきた「バベルの会」の会場であるとおぼしきサンルーム。
物語はとある女学生がそこで古びた日記を発見するところから始まる。
日記の最初には「バベルの会はこうして消滅した」の一文が添えられている…。
莫大な遺産によって成金となった大寺家は
それを誇示するかのように放埒の限りを尽くしていた。
食に関しても、それまでの料理人を追放し
厨娘(ちゅうじょう)と呼ばれる最高の料理人を雇う。
しかし、夏という名のその料理人が作る料理の費用は常識を遥かに超えていた。
うわあああ!! これ感想書きたくねぇーー!!
厨娘の夏さんが途轍もなく格好よく美しく知的な女性であるがゆえに
わざと途中でオチがわかってしまう文章の書き方は胃が痛くなる!!
なんという作者の悪意!!
5篇の作品がどれも面白かった!!!
キャラクターのつくり方も素晴らしいし
上流階級の人々の一人称で話が進むため、
そのノーブルさを表現するためのボキャブラリーも申し分ない。
米澤穂信はこんなインモラルな作品も書いてたんだなぁ…。
読めば読むほど底知れない発想力!!
文章 ★★★★★
プロット ★★★★✩
トリック ★★★★
(★5個で満点)