今でもカラオケで根強い人気のある「新潟ブルース」「信濃川慕情」。私も若いころは、よくスナックで歌ったものでした。
この歌は、1967年(昭和42年)美川憲一、黒沢明とロスプリモスの競作で発売されました。
美川憲一の方は、A面が「新潟ブルース」、B面が「信濃川慕情」。
一方のロスプリモスの方は、A面が「信濃川慕情」、B面が「新潟ブルース」でした。どちらも作詞「山岸一二三」、作曲「山岸英雄」のご兄弟でした。
新潟ブルース歌詞
1 想い出の夜は 霧が深かった
今日も霧がふる 万代(ばんだい)橋よ
別れの前に 抱きしめた
小さな肩よ ああ…
新潟は 新潟は 面影の街
2 しあわせの夜を 二人過ごしたね
いつかより添った 古町通り
ほのかに白い 指先で
涙をふいた ああ…
想い出の 想い出の 新潟の女(ひと)
3 忘られなくて ひとりさまよえば
青い灯がゆれる 新潟駅よ
愛した訳じゃ ないんだと
強がりいえば ああ…
新潟は 新潟は 霧に更けてゆく
信濃川慕情歌詞
1、 町に流れる 長い川 今もあの日と 変らない
愛を誓った 君なのに
川面に浮ぶ 木の葉のように 流れていずこへ
教えておくれ 教えておくれ信濃川
2、思い出させる 長い川 君とみつめた あの夜を
肩を抱いたら うつむいて
何も云わずに 泣いてた君が 心に残るよ
返しておくれ 返しておくれ信濃川
3、遠く流れる 長い川 恋の嘆きの 信濃川
君を求めて 今日もまた
ひとり来てみた 万代橋(ばんだいばし)は 小雨にけむるよ
教えておくれ 教えておくれ 信濃川
この2つの歌碑が、信濃川沿いに建っていると聞きましたので、それを訪ねてみたいと思います。
先ず、新潟ブルースに出てくる「新潟駅」。
ここは、万代口と南口があります。南口は、新幹線側でかなり整備されていますが、万代口は、ただ今工事中です。やはり万代口の方が風情がありますね。


新潟駅から万代シティの方に歩いて行きます。バス停では、今月5日から運行を始めた「BRT」が停まっていました。このBRT,福岡市でも導入が検討されています。


萬代橋に着きました。
萬代橋は、現在の橋は、3代目でRC造六連アーチを持つ全長306,9mの橋です。1929年(昭和4年)完成。
平成16年には、国の重要文化財に指定されました。いつまでも新潟の街が発展に尽くすことを願って「萬代橋」と名づけられました。
今では、新潟市のシンボルとなっています。




渡って河川敷は、「やすらぎ堤」の遊歩道になっていて、ここでは、市民の皆さんのジョギングやウオーキングコースとなっています。


「新潟ブルース」の歌碑は、萬代橋を渡って「ホテルオークラ」の向かい側のビルの1階に建てられています。新潟市制100周年を記念して造られました。

萬代橋を渡ると、古町方面です。歩道の横には、ガス灯があります。


その近くには、「道路元標」があります。東京まで442km、京都まで592km、青森まで578kmです。


古町は、江戸時代初期まで本町と呼ばれていました。現在の本町は、あら町、新町と呼ばれていました。
古町6,7は、旅籠、古町7は、塗り物、紙の専門店街でした。明治17年(1884)、古町に3階建ての勧商場(デパートの全身)などが出来、明治22年(1889)市制施行後、古町は、商店街として発展しました。
明治末期に古町5,6に夜店が開かれ、大正3年(1914)に電気館(活動映画館)が出来ると、更に人気が高まって、北陸有数の商店街と成長していきました。
盆の花市、歳末のお歳市には、近在はもちろん、遠くの町から来た人たちで賑わいました。


新潟市のマンホールです。左のマンホールは、萬代橋を図案化したものです。右は、新潟市の花、チューリップ、真ん中にひまわりがデザインされています。


観光循環バスで市内を廻ろうかと思いましたが、このバス1時間に1本しか発車してなく、仕方なく歩いて次の目的地に行きました。

白山神社
新潟市の中心部に位置し新潟の総鎮守として千有余年の歴史のある神社。白山さまは、別名を菊理媛「くくりひめ」という女の神様で、夫婦の神様がケンカをした際に仲をとりもったと
日本書紀にあり縁結びの御利益のある神社です。(新潟ナビより)



白山神社より、信濃川河道(やすらぎ堤)に行きます。
「信濃川慕情の歌碑」は、確か、このあたりにあるのですが・・・・・・・・


昭和大橋があります。
昭和大橋は、昭和39年新潟国体前に完成しましたが、国体終了後の6月、新潟地震で崩壊しました。


歌碑を探しましたが、見つけられませんのでウオーキング中の方に聞きましたが、わからないとのこと。
新潟ブルースに比べ、この信濃川慕情は、少し知名度が落ちるからでしょうか?
信濃川沿いに探すと体育館の近くにありました。近くには、面白い形をしたものがありました。これで木を支えているのですね。


そのあと、新潟の北前船記念館、豪商小澤家などに行こうと思いましたが、今日月曜日は、どこも休館日です。
仕方がないので、帰りの飛行機の時間は、まだありますが、昼食を兼ね、新潟駅に向かいました。
初めての新潟でしたが、こんどは、ゆっくり月曜日でない日に行きたいと思います。

































































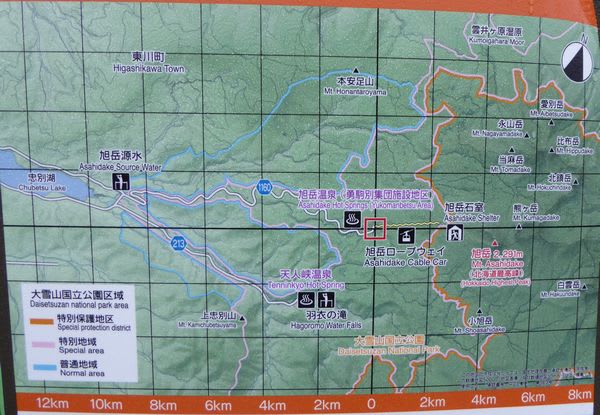











































































 (つづく)
(つづく)



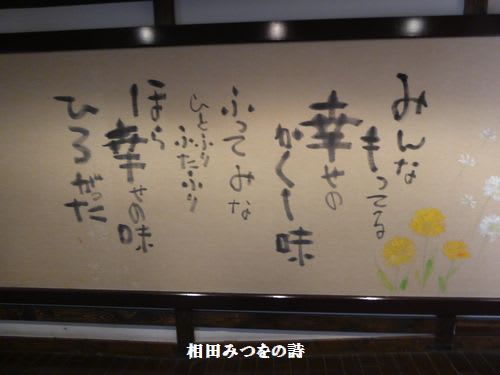

























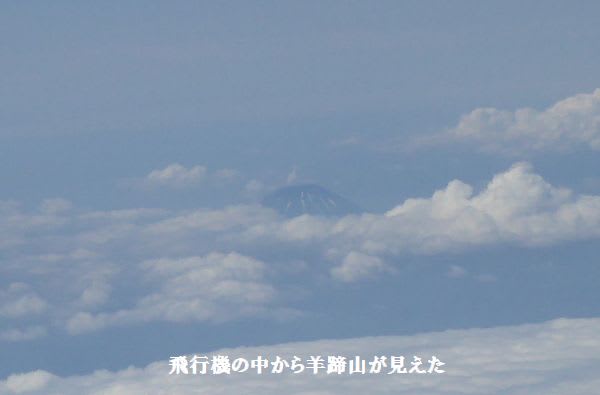
















 あいたい気持ちがままならぬ・・・・・・・
あいたい気持ちがままならぬ・・・・・・・












































































































