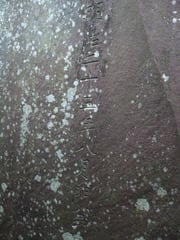白文を読んで下さった方による、書き下し文です。
河田菜風翁碑(1)に当たる部分です。
菜風君 没す。
二年を越て、
嘉謀(カボウ) 行實(コウジツ)を不朽に傳へんと欲して、
諸友 及び 門人と 之を圖る。
銘は 即ち 其の友 荒木孝繁に嘱す。
孝繁 嘆じて曰く、
「君 吾より少(ワカ)きこと九歳、
その死は 宜しく吾が後に在るべし。
然るに 不幸にして 先に逝けり。
即ち 後事の任は 吾れ 其れ 忍びんや。
然れども 吾 君と 篤きこと 衆の知る所なり。
義 辭し難し。」
遂に 之を 銘す。
嘉謀(カボウ)とは、「嘉猷(カユウ)」という語と同じように、、
よいはかりごと。 国を治めるための優れた計画のこと。
だそうですが、
今回は 人名です。
書き下し文が終わりましたら、現代語訳に移りますので、
その頃に 荒木孝繁氏と一緒に ㊟として書きます。
河田菜風翁碑(1)に当たる部分です。
菜風君 没す。
二年を越て、
嘉謀(カボウ) 行實(コウジツ)を不朽に傳へんと欲して、
諸友 及び 門人と 之を圖る。
銘は 即ち 其の友 荒木孝繁に嘱す。
孝繁 嘆じて曰く、
「君 吾より少(ワカ)きこと九歳、
その死は 宜しく吾が後に在るべし。
然るに 不幸にして 先に逝けり。
即ち 後事の任は 吾れ 其れ 忍びんや。
然れども 吾 君と 篤きこと 衆の知る所なり。
義 辭し難し。」
遂に 之を 銘す。
嘉謀(カボウ)とは、「嘉猷(カユウ)」という語と同じように、、
よいはかりごと。 国を治めるための優れた計画のこと。
だそうですが、
今回は 人名です。
書き下し文が終わりましたら、現代語訳に移りますので、
その頃に 荒木孝繁氏と一緒に ㊟として書きます。























 「藍香尾高淳忠」さんは、
「藍香尾高淳忠」さんは、