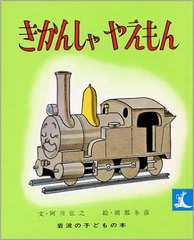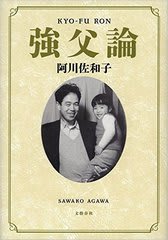河田菜風さんについての話の続きです。
「企画展 深谷にゆかりのある人々 5
このひとをしっていますか?
関流和算の大家 藤田貞資 ・
門弟五百数十名 中瀬きっての教育者 河田菜風」
の、パンフレットをいただきました。
こんな事が、書いてあります。

門弟五百数十名 中瀬きっての教育者 【深谷市中瀬】
河田菜風
1821-1880(文政4年~明治13年) 享年60
文政4(1821)年11月13日、榛沢郡中瀬村(現在の深谷市中瀬)、
河田十郎右衛門(じゅうろうえもん)の長男として生まれる。
諱を嘉豊(よしとよ)、字を公実(こうじつ)通称、を半内(はんない)、
号を菜風(さいふう)と称した。
菜風の由来は、生地の中瀬と、おいしい食菜の産地と、
名物の赤城颪(あかぎおろし)が吹く土地柄とを巧みに織り交ぜた雅号で、
郷里の地名や風土に因んだものとされている。
幼少の頃から その才能は 周囲の子らに比して優れており、
また、学を好み、中瀬の天台宗吉祥寺(きちじょうじ)の観海(かんかい)和尚に就いて
和漢の学を修めた。
吉祥寺は上州(群馬県)世良田長楽寺の末寺で、
観海は二十五世であった。
人格・識見共に備えた名僧で、
上州・武州に多数の門弟があった。
これらの門人中、菜風は観海が最もその将来に期待をかけていた高弟であった。
青年の頃の菜風は、筑前(福岡県)の宗像蘆屋(むなかたろおく)や
越中(富山県)の殿丘神通(とのおかじんつう)らが
諸国漫遊の途中に立ち寄ったので、
一時これら遊学の学者に就いて詩文・書画を学修した。
天保9(1838)年、自邸を教場として塾を開き、
近隣の子弟に教授を始めた。
この時、菜風は18歳であった。
10年後の嘉永2(1849)年、28歳の菜風は
塾名を正式に「宣興塾」と名付け、
盛大な命名披露の雅会を催した。
当日は 福田半香(ふくだはんこう)、中沢雪城(なかざわせつじょう)、
桃井可堂(もものいかどう)、代五渡(だいごと)、市川市月(いちかわしげつ)、
伊丹渓斎(いたみけいさい)、渋沢誠室(しぶさわせいしつ)、
斉藤南々(さいとうなんなん)、金井烏洲(かないうじゅう)ら
地元の著名な文人墨客が出席し、
席上それぞれ揮毫して 当日の記念とした。
この語、寺門静軒(てらかどせいけん)も菜風を訪れている。
明治5(1872)年、学生が発布され、
翌6年2月に中瀬小学校が開設された。
菜風は これを契機に35年に及ぶ「宣興塾」を閉じ、
村の教育顧問となって 後進の育成に協力した。
菜風の薫陶を受けた門弟五百数十名には、
地元・成塚の書家、正田晴圃(しょうだせいほ)をはじめ
県会議員、町長、小学校長として名を成し、地元の枢機に参画した人々が
多数輩出した。
明治13(1880)年1月3日没。
享年60.
後に、多数の門人知友によって
「河田菜風翁碑」が 菜風ゆかりの地に建立された。
ずいぶん詳しく書かれていますね!
観海さんの名前が書かれているのを拝見する事は、
極めて稀です!
そして、中瀬の吉祥寺境内にある「河田菜風翁碑」の写真があります。

これは、以前に私が撮った画像。
金井烏洲は、画家?絵師?でした。(
「歴史好き」)
齋藤南々は、芭蕉の句碑を立てた俳人でした。
いろんな人達と関わった方だったのですね。
10月10日までの会期の間に、ぜひ 訪れたいものです。
【展示会期・展示会場】
2016年9月15日(木曜日)~10月10日(月曜日、祝日)
深谷市川本出土文化財管理センター(川本公民館南側の建物)
入場無料
【開館時間】
午前10時~午後4時 (会期中は無休です)
【展示内容】
藤田貞資(ふじたさだすけ)…江戸時代に活躍した関流和算の大家
河田菜風(かわたさいふう)…門弟五百数十名を育てた教育者