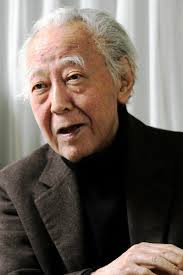
道徳と、倫理は、似て非なるものらしい。向きが違うらしい。それってどういう意味?
p78の第2パラグラフ。
これは、資本主義の基本的構造でして、それは、資本主義が生まれた最初からそうでした。しかし、それは、いまだに現代の資本主義の特徴なのですが、しかし、そのたくさんの要素が変化してしまったがゆえに、現代資本主義は特別な性格を帯びると同時に、現代人は性格構造に深刻な影響を受けてきました。資本主義の発展の結果、資本の一極集中がますます増大しています。大企業はその規模を拡大し続け、小規模な企業は搾取されます。こういった大企業に投資する資本家は、大企業を経営する働きからだんだん離れています。何千何百の投資家たちがその大企業を「所有」しています。経営陣の官僚が、高いサラリーを得てはいても、その企業を所有せぬまま、企業経営をしている、という訳です。この官僚制は、その企業の拡大や自分自身の権勢ほど、最大の利益を得ることに関心がありません。資本が集中し、強力な経営陣の官僚政治が登場したことは、労働運動の発展とパラレルです。労働者が連帯するにつれて、個人の労働者は、労働市場で自分のために良い買い物ができなくなりました。1人の労働者は、大きな労働組合に組織され、強力な官僚政治に導かれています。その官僚政治がその労働者の代わりに巨人に向かい合います。主導権は、良きにつけ悪しきにつけ、資本の分野でも労働の分野でも、個人から官僚政治へと、移っています。ますます多くの人が独立的であることを止めて、巨大な経済帝国の経営陣にますます依存することになります。
現代資本主義の特色は、その官僚政治でしょう。でもこれは社会主義でも一緒です。資本主義の特色ではなくて、現代の特色だからです。
その官僚政治は、システムの巨大化です。「個人がほとんどゼロ」だと言ったのは、かの加藤周一さんです。じゃぁ、「仕方がない」と言って諦めなくちゃぁ、ならないのか?
この問いの答えは、皆さんが出してくださいね。





















