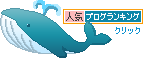本の冒頭には、
この堀内隆志さんの序文が
「僕の好きなもの」
というタイトルで、こう書かれています......
......つづくのだっ (゜0゜)/
==============================
この店を始めてから早10ヶ月が過ぎました。
アッという間という気もするし、
もう2、3年やっているような気もします。
そういえば、
何度も「店の名前は何と読むのか」と聞かれましたが、
いい機会なので説明します。
vivement dimancheはヴィヴモン・ディモンシュと読みます。
フランソワ・トリュフォーの「日曜日が待ち遠しい!」という
映画の原題(フランス語)から取りました。
(中略)
何曜日に行っても、
ここでは好きな事だけを考えて日曜日のようにのんびりしよう。
dimancheが皆様にとってそんな場所になればいいな、
と思います......(後略)
==============================
「......好きな事だけを考えて日曜日の様にのんびりしよう......」
成熟したカフェ文化を持つ国の言葉でつけられた名前を持つ
このお店のコンセプトには、カフェで過ごす時間に関しての
「大切なコト」が含まれている様に思います。
好きな事だけを考える......
この序文の後、
この本にはこのお店に集まるカフェを愛する多くの人達の
「トメドモナイ」カフェトークがエッセイ的に記されています。
会社員から店舗経営者、予備校講師、地方公務員にアルバイト。
そしてグラフィックデザイナー、イラストレーター、
ライター、TVディレクター、スタイリスト等のカルチャー組。
ゴンチチの二人やカヒミ・カリィ、ボニー・ピンク、
コモエスタ八重樫、ピチカートファイブの小西康陽、
クレモンティーヌ......
など音楽関係者の名前も目立ちます。
有名無名など関係なく全て一つのステージに並べられて、
自分の好きなことが自由自在に語られています。
どれをとってみてもとても個性的で素敵なエッセイ達で
今読み返してみても、
どれもそれまでの喫茶店文化から一歩踏み出した
日本の新たなカフェ文化の成長と定着、
先に記した黎明期から進展期に入った流れを
感じさせる雰囲気を纏っています。
そして実のところ、この本を
「素敵だな......」
と僕に思わせてくれたのは、
特に最後の部分になります。
様々な素敵なエッセイの後に、最後に三つだけ、
「喫茶魂」とタイトルされた、
更に素敵なインタビュー形式のエッセイが載っているのです。
一つは、
創業50年を超える京都
「六曜社 地下店」
のマスター奥野修さんのインタビューエッセイ。
一つは、
これまた京都の老舗、
日本のコーヒー史を語る上で避けて通れない名店
「イノダコーヒー」
のマスター、猪田彰郎さんのインタビュー。
もう一つは、
今はもう無いお店なのですが、以前北海道、札幌市にあった
「和田珈琲店」
というお店のマスター、和田博巳さんのインタビュー。
和田さんに関して言えば、
「ムーンライダース」というバンドの前身であった伝説のバンド
「はちみつぱい」のべーシストだった方。
かつての喫茶店と音楽との関係を感じさせてくれるエッセイとなっています。
音楽がまだ「アナログレコード」というパッケージ形態を取っていて、
少し高価で、誰もが気軽に買えない時代。
喫茶店はそれが珈琲一杯の値段で聞く事が出来る、
好きな音楽を仲間と一緒に聞けて、
存分に語り合うことも出来る大切な場所でもあった......
という事がエッセイから感じとれます。
この巻末にある三つの堀内さんのインタビュー記事の並びは、
カフェ文化以前にあった喫茶店文化へのリスペクトを欠かさないという
堀内さんの敬愛すべき姿勢も感じられます。
また、他の記事と同様に、
堀内さんもあくまで自分の好きなことだけを考え、
好きな人にだけ逢いに行き、
それを記しているということが
この本の雰囲気をとても「カフェ的」で、
素敵なものへと導いているように思えます。
最後に、
1997年9月に「ディモンシュ」に寄せられた
カヒミ・カリィ(アーティスト)さんの懐かしのエッセイを少しだけ......
==============================
パリに引っ越して約一年にちょうどなろうとしているのですが、
特にすごく趣味が変わったとか、
考え方が変わったという事はなくて、
やっぱりどこで暮らしても
基本的な部分は変わらないんだなぁと分かったのが、
海外に住んで一番実感したところかもしれません。
(中略)
......パリのカフェというのは東京で言うと、
コンビニエンスストアとファミリーレストランが一緒になって
もうちょっと風情があるような所というか、
なので、東京にあるフレンチ・カフェとは全然位置が違うのです。
(中略)
......パリのカフェは特に何かなくても、
なんとなく入りたくなるコンビニとか、
一杯のコーヒーで長くずっといられる、
それから物思いにふけっていたりもできるようなそんな場所なのです。
それで長い一日の太陽の下、
こんなふうに何かを書いたりしている訳です......(後略)
==============================
さて、
黎明期を終えた日本のカフェ文化の方は、
コレからどんな風に育って行くのでしょうか。
個人的には宿題をやるような場所に育っていってほしくは無いのですが......
でも、まぁ、
とても楽しみにしたりなんかしているのです (゜ー゜)

京都「イノダ珈琲」の歴史を感じる素敵な珈琲カップと
可愛くて思わず買って来てしまったミルクピッチャー。
古いピンぼけの携帯写真でふ(T.T)

お店は少し前に一度火災にあってしまい、
建替えた後は少しモダンな雰囲気の店になってしまってますが、
僕が最初に行った時は、
まだ京都の「町屋作りそのままの建物」の時で、
中庭などもあって独特の雰囲気を纏ったお店でした。
今も昔も憧れの珈琲店の一つです。
この堀内隆志さんの序文が
「僕の好きなもの」
というタイトルで、こう書かれています......
......つづくのだっ (゜0゜)/
==============================
この店を始めてから早10ヶ月が過ぎました。
アッという間という気もするし、
もう2、3年やっているような気もします。
そういえば、
何度も「店の名前は何と読むのか」と聞かれましたが、
いい機会なので説明します。
vivement dimancheはヴィヴモン・ディモンシュと読みます。
フランソワ・トリュフォーの「日曜日が待ち遠しい!」という
映画の原題(フランス語)から取りました。
(中略)
何曜日に行っても、
ここでは好きな事だけを考えて日曜日のようにのんびりしよう。
dimancheが皆様にとってそんな場所になればいいな、
と思います......(後略)
==============================
「......好きな事だけを考えて日曜日の様にのんびりしよう......」
成熟したカフェ文化を持つ国の言葉でつけられた名前を持つ
このお店のコンセプトには、カフェで過ごす時間に関しての
「大切なコト」が含まれている様に思います。
好きな事だけを考える......
この序文の後、
この本にはこのお店に集まるカフェを愛する多くの人達の
「トメドモナイ」カフェトークがエッセイ的に記されています。
会社員から店舗経営者、予備校講師、地方公務員にアルバイト。
そしてグラフィックデザイナー、イラストレーター、
ライター、TVディレクター、スタイリスト等のカルチャー組。
ゴンチチの二人やカヒミ・カリィ、ボニー・ピンク、
コモエスタ八重樫、ピチカートファイブの小西康陽、
クレモンティーヌ......
など音楽関係者の名前も目立ちます。
有名無名など関係なく全て一つのステージに並べられて、
自分の好きなことが自由自在に語られています。
どれをとってみてもとても個性的で素敵なエッセイ達で
今読み返してみても、
どれもそれまでの喫茶店文化から一歩踏み出した
日本の新たなカフェ文化の成長と定着、
先に記した黎明期から進展期に入った流れを
感じさせる雰囲気を纏っています。
そして実のところ、この本を
「素敵だな......」
と僕に思わせてくれたのは、
特に最後の部分になります。
様々な素敵なエッセイの後に、最後に三つだけ、
「喫茶魂」とタイトルされた、
更に素敵なインタビュー形式のエッセイが載っているのです。
一つは、
創業50年を超える京都
「六曜社 地下店」
のマスター奥野修さんのインタビューエッセイ。
一つは、
これまた京都の老舗、
日本のコーヒー史を語る上で避けて通れない名店
「イノダコーヒー」
のマスター、猪田彰郎さんのインタビュー。
もう一つは、
今はもう無いお店なのですが、以前北海道、札幌市にあった
「和田珈琲店」
というお店のマスター、和田博巳さんのインタビュー。
和田さんに関して言えば、
「ムーンライダース」というバンドの前身であった伝説のバンド
「はちみつぱい」のべーシストだった方。
かつての喫茶店と音楽との関係を感じさせてくれるエッセイとなっています。
音楽がまだ「アナログレコード」というパッケージ形態を取っていて、
少し高価で、誰もが気軽に買えない時代。
喫茶店はそれが珈琲一杯の値段で聞く事が出来る、
好きな音楽を仲間と一緒に聞けて、
存分に語り合うことも出来る大切な場所でもあった......
という事がエッセイから感じとれます。
この巻末にある三つの堀内さんのインタビュー記事の並びは、
カフェ文化以前にあった喫茶店文化へのリスペクトを欠かさないという
堀内さんの敬愛すべき姿勢も感じられます。
また、他の記事と同様に、
堀内さんもあくまで自分の好きなことだけを考え、
好きな人にだけ逢いに行き、
それを記しているということが
この本の雰囲気をとても「カフェ的」で、
素敵なものへと導いているように思えます。
最後に、
1997年9月に「ディモンシュ」に寄せられた
カヒミ・カリィ(アーティスト)さんの懐かしのエッセイを少しだけ......
==============================
パリに引っ越して約一年にちょうどなろうとしているのですが、
特にすごく趣味が変わったとか、
考え方が変わったという事はなくて、
やっぱりどこで暮らしても
基本的な部分は変わらないんだなぁと分かったのが、
海外に住んで一番実感したところかもしれません。
(中略)
......パリのカフェというのは東京で言うと、
コンビニエンスストアとファミリーレストランが一緒になって
もうちょっと風情があるような所というか、
なので、東京にあるフレンチ・カフェとは全然位置が違うのです。
(中略)
......パリのカフェは特に何かなくても、
なんとなく入りたくなるコンビニとか、
一杯のコーヒーで長くずっといられる、
それから物思いにふけっていたりもできるようなそんな場所なのです。
それで長い一日の太陽の下、
こんなふうに何かを書いたりしている訳です......(後略)
==============================
さて、
黎明期を終えた日本のカフェ文化の方は、
コレからどんな風に育って行くのでしょうか。
個人的には宿題をやるような場所に育っていってほしくは無いのですが......
でも、まぁ、
とても楽しみにしたりなんかしているのです (゜ー゜)

京都「イノダ珈琲」の歴史を感じる素敵な珈琲カップと
可愛くて思わず買って来てしまったミルクピッチャー。
古いピンぼけの携帯写真でふ(T.T)

お店は少し前に一度火災にあってしまい、
建替えた後は少しモダンな雰囲気の店になってしまってますが、
僕が最初に行った時は、
まだ京都の「町屋作りそのままの建物」の時で、
中庭などもあって独特の雰囲気を纏ったお店でした。
今も昔も憧れの珈琲店の一つです。