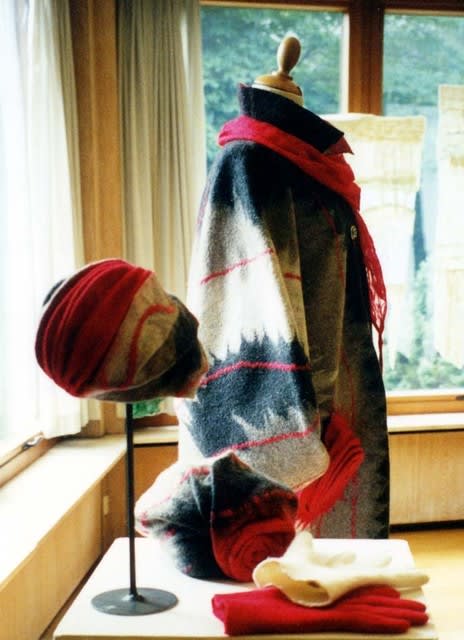◆橋本真之. 作品122「連鎖運動膜(真昼の星々)」(内部) 1981年7月~
photo:高橋孝一
photo:高橋孝一

◆橋本真之 作品111「運動膜」(内部) 1976年9月~1977年5月制作

◆橋本真之 (奥) 作品111「運動膜」 (中) 作品123 「運動膜」(真昼の星々) 1981年11月~1982年制作 (手前) 作品114「運動膜」(二層の水面) 1978年2月~8月制作

◆橋本真之 作品125「重層運動膜」 1982年3月~5月制作
2002年7月10日発行のART&CRAFT FORUM 25号に掲載した記事を改めて下記します。
造形論のために『方法の理路・素材との運動⑥』橋本真之
世に行なわれることが作品制作の第一義ではないにしても、揮身の作品発表が黙殺されるということは苦しい。ことに自らの力を明確に自覚していれば、なおのこと苦い。脆弱なデッチあげ仕事や、模倣作家がもてはやされている中で、沈黙する他ないのは苦しい。全くの黙殺。今も志す者の十中八九がこの憂き目に会っているはずである。
概念芸術の席捲する中で、私の発表は新人の時代錯誤と受け取られていたに違いない。本質のところで、『造形芸術がなおも可能であるか?』が問われていたのである。中国では文化大革命が吹き荒れて、旧体制は破壊しつくされていた。60年代末から70年代にかけての学生運動と反芸術、そして概念芸術の過熱の中で、私の造形思考は殆ど無意味と思えたのに違いない。絵画も彫刻も、無効の存在と化していた。まして、工芸世界は体制べったりの仕事か、あるいは、いまだにモダニズムの残滓に追従しているに過ぎなかった。この時代に、欺瞞なしになおも造形行為が可能か?私に突きつけられていた論調の最たるものは、アドルノに代表されるような言論の風だった。
『文化批判は、文化と野蛮の弁証法の最終幕に直面している。アウシュヴィッツのあとで詩を書くことは野蛮である。しかもこのことが、なぜ今日では詩を書くことが不可能になってしまったかを教える認識さえ触んでいるのだ。‥‥』(テオドール・W・アドルノ)
現実にこれらの文章が、正確に私のまわりで流通していた訳ではなかった。けれども、当時を思い返えす時、アドルノの一文ほど、私を圧迫していた状況を鮮明に要約するものはないのである。
1976年夏、個展会場から搬出して来た「運動膜」で、仕事場の中はいっぱいだった。搬送用に作った鉄のフレームごと仕事場に積み上げて、ようやく次の仕事を始める空間を作った。鉄は屋外に出せば、すぐに錆が来て腐蝕に耐え得ない。いかなる塗装も、いずれ腐蝕する。私は後先を考えずに、小さな仕事場で大きな作品を作ってしまったのである。苦い黙殺の壁の前で、私には鉄という素材は限界だった。この先、鉄で作品を造り続けていれば、次々と倉庫が必要だ。私の意気沮喪は、怒りと裏腹に、深く自らの感情を押し殺さねばならなかった。かって造った大きな鉄の林檎と、「凝着」二点は外に出した。
内部から外部へと、ひとつながりの金属の膜状組織で成り立っていて、外部を造ることが、即、内部を造ることになる作品の、根本の構造の意味は、全く理解されなかった。あるいは、無効な造形上の探求と見なされたのであろう。私はこの「運動膜」という六っの独立した部分で成立している全体を、ひとつひとつ造り替えながら、制作を続けて展開する考えに至っていたのだが、鉄を放棄せざるを得なかったことで、振り出しに戻らねばならなかった。(注1)
仕事を続けるには、雨風にさらして保管できる素材でなければならない。このままでは黙殺のままに、作品は消滅することは明らかだ。私の時代は甘くない、と覚悟したのである。かってアルミニウムも真鍮も叩いたことがあったが、いずれも、その腐蝕状態が私を気乗りさせなかった。金や銀は素材として高価に過ぎて、はなから私の手におえるものではなかったし、ステンレスも叩いて見たが、私には硬過ぎて肘に響き過ぎた。どう考えても、永く叩き続けられる素材ではなかったのである。銅の魅力は、その柔らかな抵抗感と、保存状態の経緯を現わす多様な錆にある。その錆色は「水中古」の青、「土中古」の緑、「伝世古」の黒褐色と言われるように、(注2)その色によって、どのような経緯で伝えられたのかが様々に推察できるのである。また、望むならば、薬品で錆を意図的に発生させることも可能である。金敷の上で銅板を叩くと、鉄の場合は金槌をはね上げるのとは対称的に、金槌が銅に喰い付く感じになって、次の一撃を打ち降ろすためには、力を入れて引き上げねばならない。それは沼地に足を踏み入れて、足を取られるような感触だった。私は手元にあった厚さ1mmの銅板を叩いて、制作を再開した。銅の熔接は、自己流だが小さな作品で何度か経験している。ただし、小さな作品を扱ってはいたが、大きな作品にも、そのままで通用するとは思えなかった。酸素とアセチレンガスの混合による火力と銅板への熱伝導を考慮した火加減と、作業速度の習熟が必要であるが、とりあえずの接合のための役にはたった。私は「運動膜」六点をひとつの作品に凝縮した形態として造るつもりだった。厚さ1mmの銅板は、鉄の強度と違って、大きくなるにつれて衝撃と自重で歪み始めた。これらのことが、強度を求めて、構造を複雑にして行くきっかけとなったのである。鉄と違って、銅は一度火を入れた部分は、必ず徹底的に叩きしめねばならない。さもなければ、銅の柔らかさは外的な衝撃に歪む。このことは、叩きしめるために、作品に当て盤を持った左手が入る穴を開けることの、有効性を考えるきっかけになったのでもある。鉄から銅に替わることが、必然的に作品空間のあり方を根本から変化させたのである。穴を開けずに制作することも可能だが、そのことに執着し続けていたら、おそらく、作品世界の仕組は別な方角を目ざすことになったのに違いない。穴を開けることで、銅板は外展し内展し、そして、重層化した作品の内部と外部とを、同時に見ることができるものになって行った。そのことによって観照者は、中心部から外へ外へと展開する制作の経緯を、追認することができるのである。
この一作に丸々八ヶ月かかった。屋外に出して雨水を溜めた。かって我が家にあった、狭い中庭の泉水が持っていた空間と湿度が、そこに在った。雨水が溜まり、蒸発し、また雨水が溜まる。水面と銅膜とが接する内壁が、一番先に酸化して緑青を発生させる。いわゆる「水中古」である。永い間に水面が上下することで、緑青が小きざみに震えた線状の層となって現われる。自然の循環が、私の仕事の内に浸入して来たのである。最終的な錆色を見たくて、薬品で緑青を出しても見た。銅板が重層化すると共に、水面もまた重なる形となった。この事は、次の仕事での構造として、意識的な出発となった。厚さ1mmの銅板は、屋外の作品としては、あまりにひよわな感じがする。強度を求めて、厚さ1.8mmの銅板に替えた。別の作品では1.2mmに替えた。1.6mm、1.5mmと試みたが、0.1mmの厚さの違いが熔接に影響するのである。そして作品は中庭の空間を、さらに強く意識したものになり、再びふたつの部分を分散させるものとなった。作品の軸性はあるが、アンバランスな形態を持ち始めた。中心軸を持った小さな動きだったものが、一方に大きく動きを取り始めたのである。そして、作品の軸が動きを持ち始めて、シンメトリカルな軸構造による均衡は、芝々破られることになった。中心軸の垂直性が持つ、動きのない安定感が、重苦しさとして私の感覚を圧迫し始めたのである。おそらく、この感覚の揺れこそが、私の造形思考の基底で動いていて、貝の成長文様のように、環境からの刺激と生理的反応として、私の造形の様態を動かしているのである。私が作品を自らの惑星と呼ぶのも、この内的な感覚の揺れの反映としてなのであり、そのことが思考展開に揺れをもたらして、再び作品構造を動かすものとしてなのである。
工芸的造形物の多くが、回転体の軸構造を基本としている。私が鍛金技術によって造形的出発をしたことの重い意味は、ここにある。西欧近代に発生した抽象彫刻の造形の成り立ちと、私の造形が根本的に異なるところは、実のところ、ここにある。石彫とブロンズ彫刻の技術上の展開が産んだ彫刻と、近代技術の産んだ鉄鋼彫刻の構成主義の埓外にあった工芸技術。その鍛金技術の中から発生した、私の造形の方法の理路が、これまでの造形世界と別種の世界構造を持ち始めるのは、当然といえば当然の成り行きなのである。
私は絵画・彫刻が主導して来た造形上の習慣を、因習として放棄した。「林檎」を突き抜けた時、私はこの仕事が何に成り得るのか解らなかった。運動する膜状組織「運動膜」概念の発見とは、作品世界の構造としての定義であった。この仕事が造形の問題であることに間違いはないと思ってはいたが、私にとっての造形が何であり得るかを、美術・工芸という枠を突きくずした上で、自ら立ち上げねばならなかったのである。
闇雲な探求は、一方で重層構造をことさらに展開して、ドリルの穴を無数に開ける方向に向かい始めた。それは、これ以上の穴が開けば、あるいはこれ以上の大きな穴になれば、膜状組織の崩壊をもたらす限度まで進めざるを得なかった。構成をあふれて、過剰な展開となったが、それは望むところだった。運動膜にひとつのドリルの穴が開けられる瞬間、それは内部から見ていると、光の噴出である。そして空気が流通しはじめる。私は銅の膜状組織を流通する風の音を聞いた時、そこに風の形を見る思いがした。かって「林檎」にドリルで穴を開けたが、同じドリルで穴を開ける行為が、かってとは意味が異なっていた。かっては、表現行為の自己否定としてのドリルの穴であったり、ふたつの林檎の空間的関係を見い出そうとする方位としての穴であったが、ここにあるのは膜状組織の全面的肯定としての意識化である。内部も外部も、表も裏も、等価な存在として顕在化させるための無数の穴なのである。ひとつひとつの穴の関係をどうすべきか?迷い迷いドリルの穴を開けるのだが、次第に穴を開ける行為が自動運動と化して行く。そして、無数に開けた穴は、内部を、すなわち幾層もの膜状組織を透視させることをもたらした。
ある日、日食が起きた。作品に開けた穴を通して、内部空間に無数の光点が射し込んでいる。そのひとつひとつの光点が日食を起こしていた。すなわち、このひとつひとつの光点は、それぞれが光源の太陽の形だったのである。内部の銅膜や、溜った雨水の底に、日食している太陽が散乱していた。けれども、穴から光点を結ぶまでの距離が短かければ、それはドリルの穴の形が光点となっているのであり、ある焦点距離を超えると、光源の形がそこに結像しているのである。木立の木もれ陽が地上に落ちていて、それらもまた日食していることに気付いた時、揺れ動く太陽の形の散乱に、めまいを覚えた。
私は空を振りあおいで、そこにあるひとつの三日月形の太陽の形を見た。そして、太陽光におおわれた青空が、そこにあるはずの真昼の星々を打ち消していた。作品の内面には、星空が拡がっていた。この入り組んだ空間の構造を見出した時、私は詩をも呼び寄せたのであって、自ら詩を唄ったのではない。これは、いわゆる私の表現ではあるまい。私の作品構造が、存在間の感応のエネルギーを物理的に呼び込んでいるのである。この現象のひとつひとつを読み取るのは、観照者の力次第なのである。私もまた、「運動膜」の前で一人の特殊な観照者なのでもある。
(注1)この作品構造の考えは、「作品変換」として、後の「果樹園―果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実」に受けつがれることになる。
(注2)中国古銅器の錆色に対する呼称である。中国の戦乱の中で先祖から伝えられた銅器を持って避難することができない時、井戸の中に沈めて避難したり、湿地に埋めたり、乾燥した畑に埋めたりされていたものの、緑青の色が、それぞれ異なるところから、水中古、土中古、と呼ばれ、伝世されて緑青のふいていない黒褐色のものと区別された。
(注2)中国古銅器の錆色に対する呼称である。中国の戦乱の中で先祖から伝えられた銅器を持って避難することができない時、井戸の中に沈めて避難したり、湿地に埋めたり、乾燥した畑に埋めたりされていたものの、緑青の色が、それぞれ異なるところから、水中古、土中古、と呼ばれ、伝世されて緑青のふいていない黒褐色のものと区別された。