最近、雨が続いて気温も急降下しています(今は外気温7℃の表示)。
雨上がりの蜘蛛の巣に大粒の水滴がくっついて巣を浮き上がらせています。

今日の「日本国家概況」(2年)は、
数週間学習を続けてきた日本の教育についてまとめのグループ討論をしました。
メインテーマは「ゆとり教育と詰め込み教育のメリット・デメリット」で、
自分たちが受けてきた中国の学校教育(完全な詰め込み教育)と、
日本が約10年間施行して止めた「ゆとり教育」を体験に基づいて比較することです。
2年生はクラスの人数が12人しかいないので、3人で1グループになり、
討論は中国語でもいいが、まとめの発表は日本語ですることとしました。
この学年は、どの学生も何とか日本語で発表できるレベルを保持しています。
と言うか、「日本語で話しなさい」と言われたら、その通りに頑張るのです。
(つまり、そうでない学年も存在するということが、これでお判りでしょう(笑))。
発表では、
「高校時代の教育環境が劣悪で、知識の詰め込みだけでなく、
50~70名もの生徒を一教室に詰め込んで授業をしていた」、
「先生の要求が多くて、圧力(ストレスのこと)を強く受けていた
(例:朝6時からクラスでジョギングする、毎日あまりにもたくさん宿題を出す、など)」、
「学校と寮の往復で、自由度が低い(男女交際はどの学校でも公的に禁止)」、
「知識を覚えるのに忙しくて、興味のあることをじっくり深く勉強するチャンスがない」、
「先生も親も成績を非常に重視して、期待に沿わないと厳しく叱責される」など、
実体験に基づく詰め込み教育の弊害が噴出しました。
良い所はないのか聞くと、
「学費が安い(800元~1900元/年)」、
「よく勉強するので知識が増え、成績がよくなる」
という利点があげられました。
学費は日本の公立高校で今いくらぐらいなんでしょう。
いくらなんでも1年に800元=15000円てことはないでしょうね。
破格の安さです。
よく勉強すれば知識が増える、というのも確かにその通りですが、
その知識が思考を深めるものに成り得てきたのかについては、
多くの学生たちが「ノー!」と言っていました。
また、勉強すれば成績がよくなるというのも全員に当てはまることではない、
と学生は認識しています。
中国も(は?)相対評価なのだそうです。
クラスまで成績順に分けられ、A組がトップ、次の成績がB組というようになっており、
成績が最悪のクラスに対しては先生たちも投げやりだそうです。
かつての日本にもこんな学校はあったのでしょうか?
私は日本の超辺境の地の出身なので、
昔の日本のメインストリーム教育というものを知りません。
という訳で、学生たちは「ゆとり教育」に熱い、熱い賛意を表明していました。
学生が主役であること、自由が多いこと、興味・関心が育成されること。
これが中国の、と言うか、菏澤学院の2年生が学校教育に強く願うことです。
「日本に留学したい。しかし、日本で何を専門に勉強したらいいか分からない。
特にこれと言って興味・関心がないので。」
とは、先日4年生の一人が言っていた言葉です。
私は、
「日本に留学するのもいいけど、ノルウェーかフィンランドはもっといいんじゃない?」
と要らんことを言って授業を終えました。
帰り道、宿舎近くの柳の木がきれいでした。












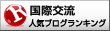



















 (←嬉し涙)
(←嬉し涙)




 )
)







