夏目漱石(金之助)は1867(慶応3)年、江戸牛込、現新宿区生まれの江戸っ子だ。
1916(大正11)年に亡くなるまで49年しか生きなかったが、
一人の人間としては内在する力の全てを出して生きたのではないだろうか。
漱石の作品や関連書籍を読むに従い、
彼のイメージが次第に私の心の中で形を成してきたが、
それは、満身創痍で、頑固に、底知れない忍耐力を発揮して死ぬまで粘る人間の姿だった。
そもそも、生い立ちがたいへんだ。
名主の五男坊(末っ子)として生まれた時、母親は高齢での出産を恥じたという。
生まれてきたことを恥じられた子だった。
生後4カ月で古道具屋か小間物屋かに養子に出されたが、
一歳で養家が変わり、結局は養家の塩原夫婦の不和のため九歳で生家に戻された。
典型的たらいまわし。
戻った生家で厄介者だったことが自伝的小説『道草』の一節に書かれている。
「実家の父にとっての健三(註・主人公)は小さな一個の邪魔物だった。何しにこんな出来損ないが舞い込んできたか、と言う顔付きをした父は、ほとんど子としての待遇を彼に与えなかった。今までと打って変わった父のこの態度が、生みの父に対する健三の愛情を根こそぎにして枯らし尽くした。(中略)
実父から見ても養父から見ても彼は人間ではなかった。むしろ物品であった。ただ実父が彼を我楽多として取り扱ったのに対して、養父には今に何かの役に立ててやろうという目算があるだけであった。」
養父が金之助の籍を「塩原」のままにしておきたがったのは、
将来、給仕にでもしてお金を養家に入れさせるためだと直接本人に語ったという。
漱石は後に「当時の自分はよく壊れずに耐えたものだ」と書いているが、
これが漱石のトラウマ=消えない傷になったのは明らかだ。
「トラウマを抱えながら、壊れずに耐え続ける」ことが、漱石の一生だった。
その中から、「自分本位」「人間の目的は生まれた本人がつくる」という、
揺るぎない漱石の個人主義が形成された。
只者ではない人に出くわす度に心が震えるが、
この間から私の心の心拍数は、またしても爆上がりだ。

↑夏目家のあった牛込馬場下町ではないが、近くの江戸川の桜満開の風景。
東京名所写真帳1910(明治43)年刊行より




















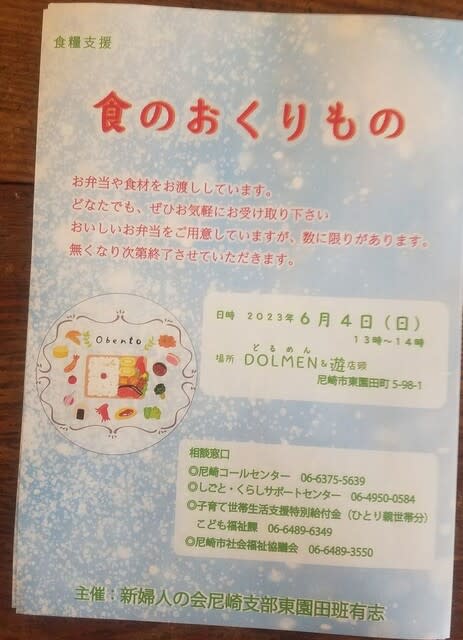




 朝、部屋で雨量が多いと分かる雨音を聞き、少し憂鬱になる。
朝、部屋で雨量が多いと分かる雨音を聞き、少し憂鬱になる。




