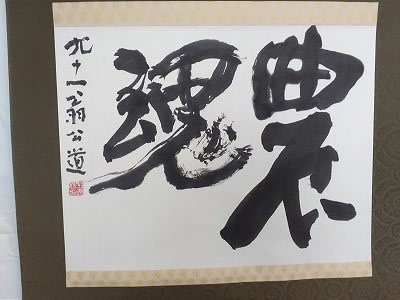16日のブログで野菜畑のおもわぬ台風被害を、18日のぶろぐでは、台風対策、野菜のスリム化について報告しました。
特に、虎の子のトウガラシ類は、今年、青枯れ病に勝てるかどうかの最終段階に入っていたので、ぜがひでも、生き抜いてもらわないといけなかったのです。そこで、台風の前日、大慌てで実をすべて取り去り、枝をギュッとまとめて支柱に縛り付けてスリムにして、強風をやり過ごしました。
こうして、とにかく台風は無事にパス。
で、あれから5日弱の今朝、畑をのぞいてみました。

当然ですが、異常なし。

ギュッと縛ったピーマンは、スッと上へ伸びています。
よく見ると・・

実が大きくなっているではありませんか。
シシトウも、

近寄ってみれば、

ビッシリと実をつけています。

さっそく収穫した結果はこれ。

台風前に、大慌てで行った5日前の収穫(下写真)と較べてみると・・・。

ほとんど同じですが、今日の方が色艶が良い。

今回、気がかりであったのは、縛って内側になった花のことです。かなり強く縛ったので、行き場を失い、実がうまく育たないのではないか、との懸念がありました。
上の写真の右側が通常の実、左側が内側になった実です。日光が直接当たらないので色白ですが、まあ、良しでしょう。それに、内側にある実は、10個に1個くらいの割合で、思ったよりも少なかったです。実も、葉や枝同じで、日光を求めて外側へとせり出すのですね。このことは、十六ササギでハッキリと観察することができました。
ところで、野菜を縛って育てるのは、垂直栽培と言われる方法です。成長軸を真っ直ぐにすることにより、野菜のホルモン分泌が良好となって根が良く育ち、地上部の生育が促されます。結果として、良い野菜が長く収穫できます。
実は、この場所のトウガラシ類は当初、この垂直栽培で育てていました。が、途中で少し気を抜いた隙に、枝が大きく広がってしまい、中央へ縛り付けるのが難しくなり、そのまま伸びるにまかせていたのです。ところが、台風来襲!の非常時、強風に対処するため、無理やりに枝をまとめて支柱に縛り付けました。はからずも、垂直栽培を再開することになったのです。
その結果、5日弱でこの収穫。
台風対策、スリム化の効用ですね(^.^)