今日は小春日和の穏やかな日になりました。
街路樹の葉もそろそろ茶に染まっている木も多くなり、落ち葉も増え、少しずつ冬の準備が始まった津軽です。
でも、針葉樹は相変わらず生き生きとした緑色で、周囲の木の赤や黄色とのコントラストが美しいです。
ふと、針葉樹はいったいどこで休息をとるのだろうか?などと考えました。
さて、今日から休暇の私と連れは、車でその津軽路を青森市へと向かいました。
目的の一つは映画「チェルノブイリハート」を鑑賞するため。60分の短いドキュメンタリー映画ですが、最初から現実をつきつけられて、涙が流れました。
この映画、2003年アメリカで制作された映画です。
マリアン・デレオというドキュメンタリー映像作家の女性が作りました。
この作品は2003年にアメリカのアカデミー賞・短編ドキュメンタリー部門でオスカーを受賞。

25年前に起こって、すでに「過去」になったはずの「チェルノブイリ」は、決して過去になったのではなく、広島や長崎の核爆発の後遺症や遺伝子の異常で被曝2世、3世にも被害が続いているのと同様に、今も尚、後遺症をはじめ、現在も生まれてくる子供達にガンなどの病気や精神的病、脳の異常、心臓の病気、先天異常、流産、死産などが多く起こっているという現実があります。
チェルノブイリから30キロ離れた地域でも、今もなお、子供達に異常がたくさん出ていて、日本の30キロ圏内の子供達は今もまだそこで生活している現実を見る時、これでいいはずがない、と叫びたくなりました。
チェルノブイリのあるウクライナや、隣のベラルーシでは、子供達の中に「チェルノブイリハート」がたくさん出ています。
初めてこの映画のタイトルを見た時、私は、「チェルノブイリの心」のことだと勘違いしていました。
「チェルノブイリハート」というのは、心のことではなく、「心臓病」のことです。
放射能の影響から、子供達の心臓に穴が開くという病気が多発しているそうです。
手術を受けてなんとか助けられる子供も居ますが、しかし、死んでいく子供達も多いのです。アメリカから来ている医師が手術を担当していました。
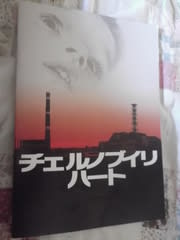
パンフです。
そして、ベラルーシ・ミンスクの放射性ヨウ素による子供達の甲状腺ガンの多発。
衝撃的だったのは、遺棄乳児院「ナンバーワン・ホーム」。精神障害や身体障害のために親から捨てられて施設にいる子供達が最近も増えているということです。
その子達を世話している女性看護師が乱暴で、マリアン監督は、「その子にもう手をかけないで。」と言って、その女性を撮影中に一瞬だけ去らせた事態が起こったほどです。
そして孤児院では、放射能の影響なのか、脳が大きくなりすぎて、それが頭と同じほどのこぶの塊となり、それが後頭部についている子、腫瘍の悪化で腰やおしりが大きく重く思うように体を動かせない子供、水痘症の子供などいました。地元の医師達も、この現実を見て、いつも泣いているそうです。
こんな子供達を日本に連れてこられたら、もっと高度な医療で治療できたのでは?と思いますが、ベラルーシなどでは、技術があっても、予算がないため、子供達に十分には治療できる環境にはないとのことです。
日本で今、福島の子供たち、関東の子供達を中心に、疎開したくても様々な理由で、土地をはなれられずに、我慢を強いられている現実があります。
政府や東電が、避難したくてもできない人々に対して、何の賠償金、補償金を払わないために、子供達が避難できないでいます。その間、どんどん被曝していく子供達。
一日も早く、福島から離れて疎開、避難するべきだと思います。
そのためには、国が早く補償する事です。
ウクライナ、ベラルーシの現実が、そのまま日本の福島、関東の現実にならないためにも、早く、一日でも早く、子供達を放射能汚染から遠ざけること、これが大切です。
生々しい映像もありますが、是非この映画を観て下さい。
ここあでした。
街路樹の葉もそろそろ茶に染まっている木も多くなり、落ち葉も増え、少しずつ冬の準備が始まった津軽です。
でも、針葉樹は相変わらず生き生きとした緑色で、周囲の木の赤や黄色とのコントラストが美しいです。
ふと、針葉樹はいったいどこで休息をとるのだろうか?などと考えました。
さて、今日から休暇の私と連れは、車でその津軽路を青森市へと向かいました。
目的の一つは映画「チェルノブイリハート」を鑑賞するため。60分の短いドキュメンタリー映画ですが、最初から現実をつきつけられて、涙が流れました。
この映画、2003年アメリカで制作された映画です。
マリアン・デレオというドキュメンタリー映像作家の女性が作りました。
この作品は2003年にアメリカのアカデミー賞・短編ドキュメンタリー部門でオスカーを受賞。

25年前に起こって、すでに「過去」になったはずの「チェルノブイリ」は、決して過去になったのではなく、広島や長崎の核爆発の後遺症や遺伝子の異常で被曝2世、3世にも被害が続いているのと同様に、今も尚、後遺症をはじめ、現在も生まれてくる子供達にガンなどの病気や精神的病、脳の異常、心臓の病気、先天異常、流産、死産などが多く起こっているという現実があります。
チェルノブイリから30キロ離れた地域でも、今もなお、子供達に異常がたくさん出ていて、日本の30キロ圏内の子供達は今もまだそこで生活している現実を見る時、これでいいはずがない、と叫びたくなりました。
チェルノブイリのあるウクライナや、隣のベラルーシでは、子供達の中に「チェルノブイリハート」がたくさん出ています。
初めてこの映画のタイトルを見た時、私は、「チェルノブイリの心」のことだと勘違いしていました。
「チェルノブイリハート」というのは、心のことではなく、「心臓病」のことです。
放射能の影響から、子供達の心臓に穴が開くという病気が多発しているそうです。
手術を受けてなんとか助けられる子供も居ますが、しかし、死んでいく子供達も多いのです。アメリカから来ている医師が手術を担当していました。
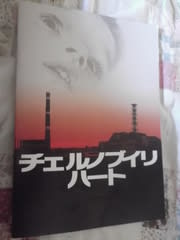
パンフです。
そして、ベラルーシ・ミンスクの放射性ヨウ素による子供達の甲状腺ガンの多発。
衝撃的だったのは、遺棄乳児院「ナンバーワン・ホーム」。精神障害や身体障害のために親から捨てられて施設にいる子供達が最近も増えているということです。
その子達を世話している女性看護師が乱暴で、マリアン監督は、「その子にもう手をかけないで。」と言って、その女性を撮影中に一瞬だけ去らせた事態が起こったほどです。
そして孤児院では、放射能の影響なのか、脳が大きくなりすぎて、それが頭と同じほどのこぶの塊となり、それが後頭部についている子、腫瘍の悪化で腰やおしりが大きく重く思うように体を動かせない子供、水痘症の子供などいました。地元の医師達も、この現実を見て、いつも泣いているそうです。
こんな子供達を日本に連れてこられたら、もっと高度な医療で治療できたのでは?と思いますが、ベラルーシなどでは、技術があっても、予算がないため、子供達に十分には治療できる環境にはないとのことです。
日本で今、福島の子供たち、関東の子供達を中心に、疎開したくても様々な理由で、土地をはなれられずに、我慢を強いられている現実があります。
政府や東電が、避難したくてもできない人々に対して、何の賠償金、補償金を払わないために、子供達が避難できないでいます。その間、どんどん被曝していく子供達。
一日も早く、福島から離れて疎開、避難するべきだと思います。
そのためには、国が早く補償する事です。
ウクライナ、ベラルーシの現実が、そのまま日本の福島、関東の現実にならないためにも、早く、一日でも早く、子供達を放射能汚染から遠ざけること、これが大切です。
生々しい映像もありますが、是非この映画を観て下さい。
ここあでした。









