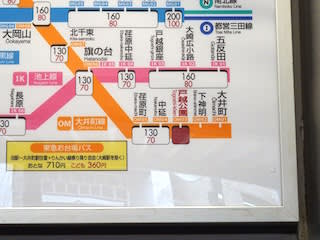「東急大井町線途中下車」シリーズの終了が近くなってきました。取り上げた順番はランダムですが、ほぼ、二子玉川駅から大井町駅へ向かうように進めています。
戸越公園駅周辺を歩いた時に、「今日はここで終わろうか」と思いました。朝、うちを出る時には北千束、荏原町および戸越公園の各駅を回ることだけを考えていたからです。しかし、時間に余裕がありました。それに、下神明駅と大井町駅を残すと、次に訪れる機会が何時になるのかわからなくなります。そこで、この二つについても歩き回ることとしました。

戸越公園駅から電車に乗ってもよいのですが、隣の駅まで1キロメートルも離れていないので、歩くこととしました。大東文化大学法学部に助教授として着任した2004年から、都営三田線、東急目黒線(終了)、東急池上線、東急多摩川線、東急田園都市線(終了)、そして東急大井町線と「途中下車シリーズ」を「待合室」とこのブログに掲載してきましたが、一日に複数の駅を回るために歩き続けるのは、今回が初めてです。実際には大した距離にならないのですが、2015年8月28日は曇天で、この時期にしては涼しかったのでした。8月下旬ですから、さすがに汗をかいてきましたが、東京都23区内を歩くのは楽しいもので、苦にはなりません。
電車に乗ると一瞬ですが、上の写真のような雑木林(?)が見えます。歩いていると非常に目立つので気になります。しかし、何の手がかりもありません。名所などであれば案内板の一つはあるはずですが、見当たりません。確実なのは、北に大崎高校、南に青陵高校があって、その東側、品川区豊町三丁目にこの光景が広がるということだけです。

しばらくすると、上に東海道新幹線、下に湘南新宿ラインや横須賀線が通る線路の踏切があり、そこを渡ります。正式には東海道本線ですが、かつては貨物線で品鶴(ひんかく)線ともいいました。そもそも、湘南新宿ラインという路線は正式に存在しませんし、横須賀線の正式な区間は大船~久里浜です。単に、東海道本線に乗り入れているというだけなのです。京浜東北線という路線が存在しないことは、少しでも鉄道に関心のある方なら御存知でしょう。東京~大宮は東北本線、東京~横浜は東海道本線、横浜~磯子~大船は根岸線です(東京~桜木町が東海道本線、桜木町~大船が根岸線という解説を読んだこともありますが、どちらが正しいのでしょうか?)。
踏切を渡ると二葉一丁目・二丁目です。旧荏原区の町で唯一、品鶴線より東に位置しており、東端と表現してもよいでしょう。遠くに大井町駅周辺の高層建築物が見えるため、荏原地域の他の町とは少し違う空気が流れているようです。
二葉一丁目を歩き続けると、豊葉の杜学園に出ます。名称から「私立学校か?」と早合点してしまいそうですが、品川区立の小中一貫校です。同区では6校目となります。「豊」は豊町、「葉」は二葉のことでしょう。

品川区と言えば学校選択制度です。勿論、学区域は指定されているのですが、区内であれば小学校または中学校を選択できるのです。実際に決めるのは親であることが多いでしょうから、自分の子に行かせたい学校を、様々な面を比較しつつ選ぶのでしょう。同区では、受入数より応募数が多い学校については抽選を行っており、同区のサイトでも見ることができます。
学校選択制度については弊害も指摘されていますが、今回はそれを論じることを目的としておりませんので、記しません。

私が歩いたのは2015年8月28日で、川崎市では既に新学期が始まっているのに対し、東京都ではまだ始まっておりません。しかし、たくさんの親子が校内から出てきました。小学校・中学校のみならず、幼保一体施設二葉すこやか園、および地域センターも併設されているので、すこやか園の園児と保護者ではないかと思われます。
豊葉の杜学園は、完全な新設校ではなく、品川区内にあった小学校および中学校を統合の上で設置されたものです。同校の公式サイトにある「豊葉の杜学園の成り立ち」によると、2011(平成23)年に荏原第三中学校と荏原第四中学校が統合され、豊葉の杜中学校となって開校します。その2年後、つまり2013(平成25)年に杜松小学校、大間窪小学校および豊葉の杜中学校が統合し、現在の豊葉の杜学園が設置されました。
学園の建物は、この、自動車用のスペースは狭く、両側の歩行者用のスペースは広い道路をはさんで両側にあります。

もう少し歩くと、大井町線の高架、さらに目指す駅がはっきりと見えてきます。その手前に、品川区立二葉図書館の案内が出ていました。こちら側は裏なのでしょう。
この図書館の手前まで、大井町駅方面から都道420号鮫洲大山線が片道一車線ずつの道路として伸びています。しかし、地図を見ていると、そこで途切れるような形になっています。よくわからないところもありますが、どうやら、「東急大井町線途中下車(12) 戸越公園駅 その2」に登場した、ひだまり公園のそばの交差点を通る道路のようで、大崎高校のそばで途切れています。つまり、二葉図書館のそばから大崎高校のそばまでが未開通ということです。

これから本格的に事業を開始するということでしょうか。既に品鶴線の所までは土地が確保されているようで、立ち退きなども済まされています。開通が何年後になるのかはわかりませんが、完成すれば戸越公園、武蔵小山駅、池尻、三宿、淡島などへ行けるということになります。高層建築物が手近に見えるようになったことは、大井町駅に近づいているということでもあります。

東海道新幹線の高架橋の側です。将来は都道420号になるこの部分は、現在、自転車置き場になっています。「住吉踏切」という案内板が出ており、品鶴線が地上を走っていることがわかります。

ここも将来は道路になるのかもしれませんが、児童公園があります。蛸の形をした滑り台です。

あと何年、ここに滑り台が残っているでしょうか。それとも、ここは公園として残り続けるのでしょうか。