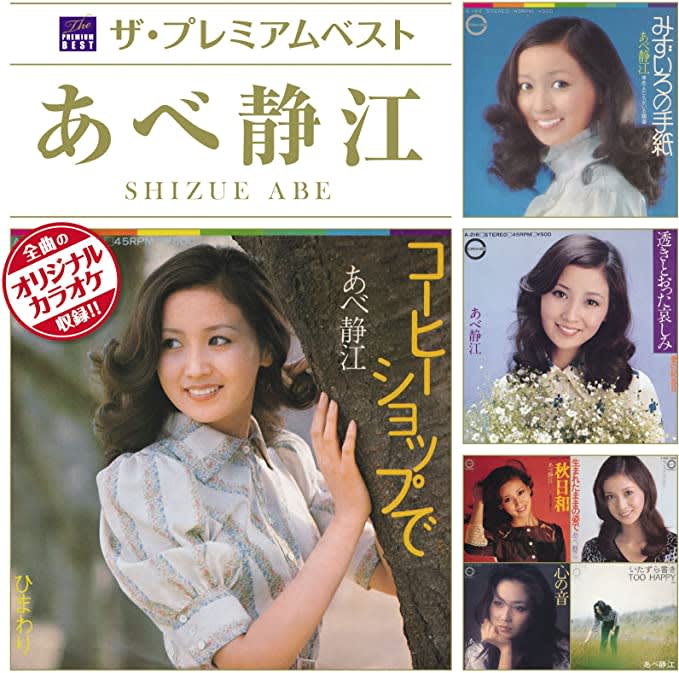『世界的なアウトドア用品メーカー「パタゴニア」(米国)の日本支社が、支社の労働組合代表を務めるパート従業員の女性に対し、年内での雇い止めを通告したことがわかった。労組はパートの雇用期間を「最大5年未満」に制限する会社側への抗議を目的に、代表の女性が中心となって結成された。労組は「不当な雇い止めだ」として、団体交渉などを通じて撤回を求めていく方針だ。』という記事が目に留まった。
というのは、30年近く前、関連会社に業務部長として出向していた時、雇い入れていた契約社員の雇用形態について、かなり突っ込んで議論を重ね、運用していたので、関心が強かったからである。当時、出向者と派遣社員を除くプロパー社員は、経費削減を主目的に全員1年契約の契約社員で、1年毎に契約更新し、4回更新(最長5年)を限度として運用していた。自分の理解では、契約は、期間の定めのない契約(当時60才)か1年契約しかなく(5年契約などは不可)、有期の場合は、1年毎に更新するか雇い止めするかを決める。但し、判例から、5年以上更新していると雇い止めができず、終身雇用せざるを得なくなるので、4回更新を限度とする運用をしていたのである(裁判で会社側が負けている)。しかし、関連会社の業務内容からして、業務に精通するには、ある程度長い期間が必要とするので、5年で雇い止めをした場合、スキルの伝承ができなくなる恐れがあった。接客部門なので、終身は困るが、10年程度は働いてもらいたいという会社側の強い希望もあり、着地点を模索していたのである。
我々が生み出したスキームは、1~5年までは、時給扱いの1年更新として、5年目以降は、それまでの契約との継続性を断ち切り、新たに月給扱いの1年更新という一からの契約を新たに結ぶというものであった。人事評価制度の整備を前提とし、優秀でない者は、契約を終了させ、優秀な者だけを次の契約に進めるスキームである。1年更新を何となく5年も続けていると雇用問題が発生するため、契約の継続性を断ち切るため、年休その他厚生制度もすべて一旦白紙に戻し、新たな契約をスタートさせることにした。その新契約も5年を最長とすることとし、10年の時点でどうしても優秀で継続して雇用したい場合は、無期の正社員として雇用する方針を打ち出したのである。また、10年目で雇い止めをしても裁判では勝てるものとの判断である。最終的には、雇用問題が発生する前に関連会社の再編が発生し、当初のスキームは最終ステージまで実施されなかった。
当時、航空業界では、キャビンアテンダントを正社員ではなく1年契約の契約社員として採用するスキームが実施されようとしていた。人件費削減が主目的だが、60才前後のキャビンアテンダントによる接客サ-ビスなど想像するだけでぞっとするイメージだったので、説得性があった。キャビンアテンダントは、最初の3年間(安全策で5年を3年に短縮)は、1年更新の契約社員として雇用し、3年後に、正社員として雇用を継続するかを決める段取りであったようである。しかし、当時、亀井静香運輸大臣が、キャビンアテンダントは安全を担う大事な任務があるので、契約社員など認めず、正社員雇用すべきと強く主張し、すったもんだした経緯があった。
シンガポール航空のようなアジアの航空会社の多くは、キャビンアテンダントに年齢制限を設けていて、常に若い乗務員がサービスをしていたが、欧米や日本の各社は、正社員雇用をしていたので、高年齢の乗務員をいっぱい抱えていたのである。今やLCCなるローコストキャリアがたくさん生まれ、様相がだいぶ異なってきた感がある。安い人件費で若くて優秀な社員を揃えたい会社側と高齢になっても安定して雇用してもらおうとする従業員との間の仁義なき戦いがいまでも続いているといえよう。今でも正規雇用、非正規雇用の格差が大きな社会問題になっているが、このようなニュースを見ると複雑というか胸が痛む思いである。