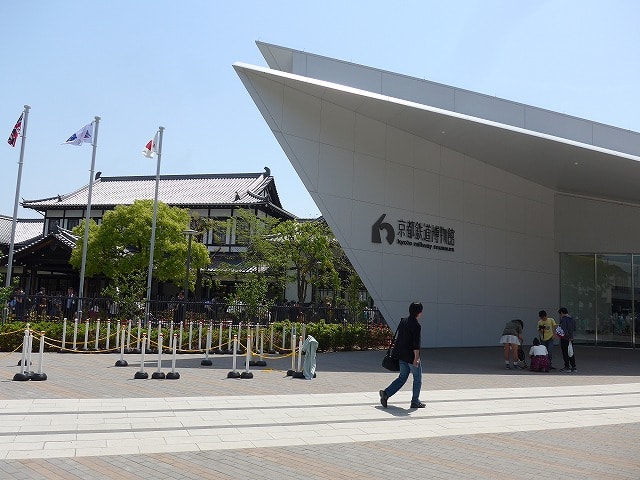京都では、四季に合わせて非公開文化財の特別公開をしています。(今期は5月8日まで)

主催は寺院ではなくて公益財団、説明員は学生が実習としておこなっています。拝観料が一箇所で800円と高めなことが難点ですが、まあ文化財の維持に協力する意味もあろうかとは思います。

青蓮院の方から歩いていったので、普段は通ったことのない黒門から入りました。入ってすぐのところにはお城のような石垣が残っています。

楓の若葉には赤い花が咲いています。竹とんぼの羽のような花弁?がついています。実が風でよく飛ぶためにでしょうか。

御影堂は修理中で入れませんが、法然上人御堂(集会堂)は無料で誰でも入ることができます。ここでは法要を執り行っていました。その奥に、大方丈と庭園があり、それらを特別公開していました。

知恩院の七不思議を説明するパネル。今回は、「抜け雀」の実物襖絵をみることができました。大方丈の菊の間の襖絵は狩野信政が描いたもので、あまりにも出来栄えがよいため、描いたスズメが飛んでいってしまったという不思議です。

大方丈の内部は撮影禁止なので、説明パネルで紹介します。
庭園に出て、池と石、緑の木々を眺めました。

屋根瓦ならぬ、本物の鷺が立っていました。

あやめ。池泉回遊式の庭園です。

新緑といっても、明るいの、暗いの、丸い葉、尖った葉など見飽きません。

「二十五菩薩の庭」
知恩院所有の国宝「阿弥陀如来二十五菩薩来迎図」を元にして、造られた庭です。臨終の時に念仏を称えれば、阿弥陀如来と二十五菩薩がお浄土へ迎えてくださる様子を示すものです。配置された石は阿弥陀如来と二十五菩薩を、植え込みは来迎雲を表しています。