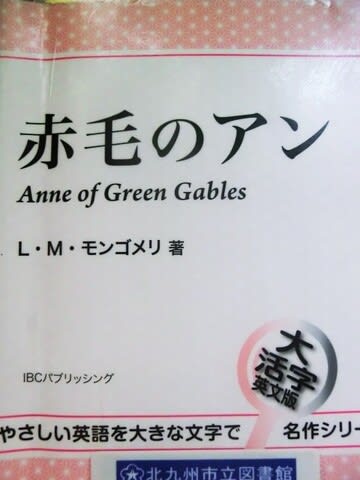『黄砂の籠城 上下巻』と対になる本です。
清国、義和団、漢民族側からみた 『義和団の乱』とは、どういう意味を持っていたのか?
”歴史認識”は双方で違って当然です。 中国人作家が書いたのか?と、中国語が母国語の人が読めば、信じるのではないか?と思われる程の内容に、作家魂を感じるというか、脱帽するしかないですね。
「逆説の日本史」でも、義和団のことは取り上げられていたのですが、井沢さんと根本的に同じ歴史観だと思います。
すなわち、清国の朝廷は腐敗していた。イギリスによるアヘン戦争、スペインなどキリスト教国家は、布教により植民地化。
前半のリアルな描写は、虐待やレイプ、暴力経験者は目を背けたくなるでしょうし、辛すぎて読めないかもしれません。映像であれば、「・・・・・な映像が流れます」とテロップが流れそうな場面が多かったです。漢民族同士の暴力や、いざこざ。神父が少女たちに対して…😨 弱い者が暴力の犠牲になり、誰が味方が敵か分からない無秩序な状況…
「いまこそわかる。光緒帝の近代化改革を頓挫させたのは誤りだった。一生の不覚に違いない。明日以降も朝廷が存続しうるなら、なすべきことはひとつだけだ。西洋に学び、日本の明治維新に倣い、合理的な国家をめざそう。古き良き仕来りなどと、誰がいった。伝統と保守へのこだわりが何千何万もの命を散らせたのだ。 (323ページ14行目~324ページ1行目から抜粋)(井沢さんも同じことを書いていた)
西洋に学び、日本の明治維新に倣い、近代化を推し進める。日本には吉田松陰がいた。欧米に学ぼうとした吉田松陰は米国戦艦に乗り込み、米国へ渡ろうとしたが失敗。そして高杉晋作もいた。彼は清国へ実際に行き、汚染した汚物垂れ流しで飲めない川で腹を壊し、「これが世界の中心の清国か!?」と、目が覚めた。彼は攘夷を捨て、「朱子学では勝てぬ」と実感。 清国のお土産に小型銃を買い、坂本龍馬にプレゼントしたんだったね。伊藤博文や井上薫、桂小五郎など同志もいた…吠えろ晋作!「朱子学では勝てぬ! 『逆説の日本史』より
「黄砂の進撃」では、いわゆる維新の先駆けとなった獅子の役を元、舟乗りの張さんがつとめています~ 実在した人かどうか分かりませんが、彼は疑問を持ちながらも義和団のリーダーとして、あくまで義和団は民衆の代表であることにこだわりながら、(清国の官軍に組み込まれた後も)行動します。
最後に漢民族の農民たちも皆、日本の後を追うべき。すなわち学ぶべきだと (日本人は農民も読み書き出来ることをさりげなく盛り込み)仲間に訴え、列強側には、「教会の抑圧によって虐げられた民衆が立ち上がったことが義和団の始まりだった」と、伝えようとする。 ここも当然、作者の歴史観が反映された箇所であり、自分にとっても納得の歴史認識。 この辺りの近代史は、中国人は殆ど書いていないらしいので、『黄砂の進撃』が世に出たことは、歴史小説史においても、大きな意義があるのではないでしょうか~

最近、ご紹介した『生きている理由』清国の皇女たちが逃げ出すシーンから始まります。義和団の乱、真っただ中から話が始まり、日本人により育てられた川島芳子の少女時代が描かれており…
「はいからさんが通る」読みたい!

同じく、伊藤博文が活躍する、こちらの本も是非ぜひ~お勧め👍
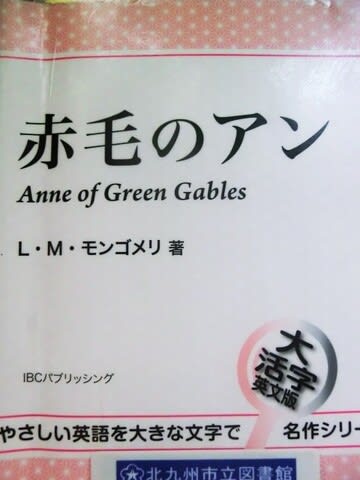
今夜はこちらを読みました。『赤毛のアン』モンゴメリ
日曜日深夜放送のスーパーマンの前のまえくらいにドラマも放送されていました。
小学校の図書室にも置いてあったアンシリーズは、私も読んでいますが、英語で読むのは初めて!
中学レベルの英語で巻末には単語辞典もあり👌
中高の英語の授業でよくやらされた、辞書を引きひき、英文和訳 😨 ではなく、読み物として楽しめます。

先週、エアコンを買いに行った際、帰りに立ち寄った書店で購入した 『ラジオビジネス英語』6月号です☆
4月から~ ちゃんと続いております~はい✋
シャドーイングの他、語句や表現を学べるだけでなく、著名人のインタビューでは、色々な考え方、生き方に触れられる点も飽きないですね💕
(雑誌は除いて、今年86,87冊目)