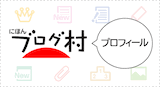与党・自由民主党の国会議員有志がつくる「日本の尊厳と国益を護(まも)る会」の来る 10/27に持たれる会合に、安倍前総理が出席される由。正式会員に加わるかは未定だが、より真に近い我国の尊厳と国益の為に資するなら 是非参加の上大いに議論を交わされるが良いだろう。左派容共勢力は快く思わないだろうが、そんな方を気にしていては 前述の目標を果たす事など永遠に叶わないだろうから。
さて 安倍前政権路線の基本継承を明言された菅(すが)総理が、就任後初の外国歴訪に赴かれた。最初の訪問国はヴェトナム国。同国首相との首脳会談に臨み、露骨な海洋政策を進める中国大陸の動きを牽制すべく持たれた「開かれたインド・太平洋構想」への理解を求め、又 日越間での新型コロナ・ウィルス感染症で停滞した経済関係を立て直すべく 二国間のビジネス面などの往来緩和、定期航空路の再開やマスクなど医療用品などの供給路「サプライ・チェーン」の多様化などが話し合われ、合意を得た所もあった様だ。次の訪問国はインドネシア国だが、同様に実りあるものとなる事を望みたい。
こうした総理大臣初め 政治家など公人の外国訪問を、よく「外遊」と称するのはよく知られる所なるも、拙者はどうも今一つこの言葉を好感できずにいる所。以下、某ネット記事を引用して、この言葉の意味と その概要を復習してみようと思う。
「外遊の意味」
外遊とは 留学や研究、視察などを目的として外国を訪問することを指す。特に政治家など公人が外交目的で 諸外国を歴訪する事に対して使われることが多い。二国間と多国間がある。外遊の「遊」は「他所の土地に出かけること」であり「遊説(ゆうぜい)」「遊学」などと同様である。
「外遊の概要」(人物敬称略)
日本の内閣総理大臣として 初の外遊を行ったのは、太平洋戦争中の 1943=昭和 18年にアジア各地を歴訪した東條英機である。戦後は 1951=同 26年の吉田 茂を皮切りに、外遊が首相の職務の一つとして一般化していった。首相の初外遊は米合衆国になることが多い。日米同盟重視の立場から、首相就任後に真っ先に訪米して合衆国大統領に顔見せすることが慣例視されていたこともある。
日本の国会議員の場合は 政治日程上国会閉会中や自然休会中に行われることが多く、例年政治休戦の時期になる大型連休ゴールデン・ウィーク中、8月、年末年始には与野党共に多くの議員が外遊に出かける。
閣僚の外遊については 大臣規範で閣議了解とされている。また国会開会中の国会議員や閣僚の外遊については 衆参両院の議院運営委員会理事会で了承を得る慣例がある。
舛添洋一は 東京都知事在任中の「都市外交」と称して外遊を積極的に行っていたが、その内容が東京都の産業発展や都民の生活向上に結び付くものではなく、多額の費用をかけて行ったため 大きな批判を浴びた。(引用ここまで)
まぁ 舛添元知事の芳しからぬ下りは余分だったかもだが、以上一読して意味を再確認しても尚、拙者はどうもこの言葉を好感できずにいる所だ。総理にせよ与野党国会議員にせよ、本来は職務であるはずの外国出張に当たる行為が恰も遊興であるが如く曲解されかねず、何とか上手い言い換えができないかとも愚考する次第。それこそ「外交行程」とか「外国出張」でも良いと思うのだが。
こうした言葉や表現の問題につき、国民市民を的確にリードすべきが 新聞や TVなど報道メディアの大きな使命のはずだが、未だどの社局からも有力な動きはみられない。「遊興」にも取れる「外遊」の言葉を残す方が、或いは敵対する政治家など公人の貶めに利用できる可能性があるからなのか。事実とすれば、何とも卑しい魂胆だと揶揄されても仕方がないと思うがどうか。今回画像は、今夏改装成った 長らくの当地のシンボル・名古屋 TV塔の雲を頂く姿を。足元を名古屋地下鉄東山、名港、桜通の各線が通ります。