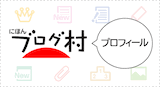かねて計画されるも、中国大陸由来の新型コロナ・ウィルス感染症流行の影響などで延期されていた 海上保安庁の無人航空機による警戒活動の可否検討に向けた実機による試験が開始された様だ。我国の周辺情勢緊迫化を考えれば当然視野に入れられるべき事共であり、成功を収める事を期待したい。
残念ながら当該無人機はまだ国産化されておらず、米合衆国、ジェネラル・アトミクス社製のシーガーディアン MB-9B型機でまず 1機が投入され、青森県の空自八戸飛行場を拠点に 11月途中までの試験に臨む。当然かもだが、試験飛行に際しては 米国人関係者の協力が不可欠で、所謂 PCR検査の厳重実施など 流行続く前述感染症対策を十分に行った上で実施される由。
現行の海保航空機には、広範に亘る洋上監視に加え、海洋資源や生態系調査に関する調査にも可能性を秘めているとされ、前述目的のフライトなどで最低でも 5人の乗員を要するそうだが、無人機となれば 拠点にての管制要員 2人で事足りるとかで、今後予想される人員不足の問題にも柔軟な対応が可能となる。又 無人機故に懸念される安全面も、住宅地を避けての飛行が計画されている様なので、その方もまず万全といえるのではないか。
今回の実証実験予算は約 9億円の由だが、勿論決して小さい金額ではない。そこで一案だが、現在そのあり方が議論されている日本学術会議を民営移行させ、捻出した額を海保の警戒力強化に回してはどうかとも思うものだ。沖縄・尖閣近海における中国大陸船舶の不穏な出方を初め、日本海側では北鮮などによる大規模な不法操業の問題もある。加えて今後の人材難を考えると、洋上警備への無人機投入は時代の流れという見方もできると心得るものだ。
今回試験に臨む無人機は、米合衆国本国では軍用無人偵察機として認識されているそうで、その事を左派容共勢力が捉えて騒ぎ立てそうだが、海保の活動はあくまで海自の安保活動とは一線を画するもの。「海の警察」としての任務が主なだけに、日本学術会議民営化の暁には、その「必要とされた」予算の多くを海保の更なる近代化やデジタル時代への的確な対応にでも割いた方が良かろう。
最近の周辺情勢をざっと見渡しても、我国にとり より困難の度を増し ているのは事実だろう。考えたくはないが、そうした周辺国や政治勢力の不穏な動きは、常に注視しておくべきとの声はよく聞く所。洋上監視や警戒にしても、新時代に合った手法を目指せる様 各方面の心がけは万全を期す必要があろう。今回画像は、先年の 伊勢神宮近くを行く JR参宮線の様子を。丁度伊勢湾が外洋と接する近所に当たる所。以下に、関連記事をリンク致します。(NHK 10/15付) https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012663761000.html<iframe id="google_ads_iframe_/6974/SankeiNews/Inread_0" style="border: 0px currentColor; vertical-align: bottom;" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/6974/SankeiNews/Inread_0" width="1" height="1" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" data-google-container-id="4" data-load-complete="true"></iframe>