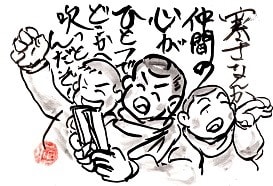そんな施設とわかっていて就職したんだろといわれたら弁解のしようはない。好条件が揃う公立の保育所に入りたいと誰もは切望するが、それが叶うのは少数の恵まれた保母たちだった。杏子はゼミの教授の後押しがあってさえ、やっと入れたのが、この施設だった。
面接をしてくれたのは、主任だった。
「うちの場合、結婚した保母さん、ほとんど寿退園されるんよ。みなさん幸せになってはるわ。だから現場は若い保母さんが多いの」
結婚したらやめて頂きますと、念を押されたと思った。妊娠ともなれば、もうほかに選択肢はあり得ない。
志島は喫茶店のオーナーである。杏子が高校生の時に知り合った。社会人がひとつの趣味を楽しむグループへ参加したのが、きっかけだった。趣味に打ち込む生真面目な志島に、自然と杏子の心は奪われていった。
「夢なんやろ。それ実現せい、後悔せんように。やり遂げたら結婚しよう。それまで待ったる。待つぐらい、なーんてことあらへんわ」
短大を卒業した日、志島はきっぱりといった。ひと回り年上の恋人は、言葉に説得力があった。誠実な志島は、口にした言葉を違えず、杏子の夢をいつも応援し続けた。
「結婚するん?」
キミが訊いた。子供たちの寝顔を眺めていた杏子は、不意を突かれて、すこし狼狽えた。
「どうして?」
「なんとなくやけど。幸せそうな顔やもん」
退職が決まり気が緩んだようだ。事情を知らないキミにさえ、見透かされてしまった。
「子供の寝顔が、あったかな気持ちをくれるから、幸せを感じたんよ。結婚やなんて、そんなことあるわけないやん」
弁解口調になるのを、なんとか誤魔化した。
「ふぅ~ん。そうなんや」
キミは納得いかないのか、小首をかしげた。危ない危ない、嘘ついて円満退職する企みが、もしもばれたら厄介だ。杏子はそーっとお腹に手をやった。ごく自然を装う仕草だった。
妊娠三か月だが、お腹はまだ目立つほどではない。きびきびと働く姿からは、誰も妊娠を想像しまい。保育園をやめる最大の動機ではあるが。
「どうしても仕事が諦めきれないというんなら、俺には何も言えへん。ただ、仕事はやり直せるけど、俺たちの赤ちゃんに、もう一度は……あらへんやろ」
志島は「絶対産め!」と要求しなかったが、その胸の内は手に取るように読み取れた。
「どんなことがあっても、杏子が結婚する気になるのを待つことは、変わらへん。ただ……心配でたまらんのや、中絶でお前が傷つく思たら。体はもちろんやけど、気持ちかて傷つく。新しい命を絶ち切って、なんとも思わん杏子やないもん。根っから優しいのに……」
言葉を濁す志島の真意は、杏子の胸をえぐった。宿った新たな命を軽んじはしない。それでも、始めたばかりの仕事を、小さいころから夢見ていた保母さんを、中途半端な形でやめることが、正しいのか誤りなのか?懊悩するばかりで、答えが導き出せない。
「杏子が出す解答は俺の解答でもあるんや。絶対受け止めてやる。じっくり考えてみろ」
「無責任だよ、保は。当事者やんか、保も」
「そやな。でも答えをだすのは杏子や。重い命の判断をつけな、先に進むことなんかできひん。母親になるかどうかを決めるんや」
「うん……わかった……考えてみる」
杏子が見やった恋人は懊悩の渦中にあった。志島は葛藤する心を持て余している。杏子以上の当事者意識に、志島は苛まれていた。

面接をしてくれたのは、主任だった。
「うちの場合、結婚した保母さん、ほとんど寿退園されるんよ。みなさん幸せになってはるわ。だから現場は若い保母さんが多いの」
結婚したらやめて頂きますと、念を押されたと思った。妊娠ともなれば、もうほかに選択肢はあり得ない。
志島は喫茶店のオーナーである。杏子が高校生の時に知り合った。社会人がひとつの趣味を楽しむグループへ参加したのが、きっかけだった。趣味に打ち込む生真面目な志島に、自然と杏子の心は奪われていった。
「夢なんやろ。それ実現せい、後悔せんように。やり遂げたら結婚しよう。それまで待ったる。待つぐらい、なーんてことあらへんわ」
短大を卒業した日、志島はきっぱりといった。ひと回り年上の恋人は、言葉に説得力があった。誠実な志島は、口にした言葉を違えず、杏子の夢をいつも応援し続けた。
「結婚するん?」
キミが訊いた。子供たちの寝顔を眺めていた杏子は、不意を突かれて、すこし狼狽えた。
「どうして?」
「なんとなくやけど。幸せそうな顔やもん」
退職が決まり気が緩んだようだ。事情を知らないキミにさえ、見透かされてしまった。
「子供の寝顔が、あったかな気持ちをくれるから、幸せを感じたんよ。結婚やなんて、そんなことあるわけないやん」
弁解口調になるのを、なんとか誤魔化した。
「ふぅ~ん。そうなんや」
キミは納得いかないのか、小首をかしげた。危ない危ない、嘘ついて円満退職する企みが、もしもばれたら厄介だ。杏子はそーっとお腹に手をやった。ごく自然を装う仕草だった。
妊娠三か月だが、お腹はまだ目立つほどではない。きびきびと働く姿からは、誰も妊娠を想像しまい。保育園をやめる最大の動機ではあるが。
「どうしても仕事が諦めきれないというんなら、俺には何も言えへん。ただ、仕事はやり直せるけど、俺たちの赤ちゃんに、もう一度は……あらへんやろ」
志島は「絶対産め!」と要求しなかったが、その胸の内は手に取るように読み取れた。
「どんなことがあっても、杏子が結婚する気になるのを待つことは、変わらへん。ただ……心配でたまらんのや、中絶でお前が傷つく思たら。体はもちろんやけど、気持ちかて傷つく。新しい命を絶ち切って、なんとも思わん杏子やないもん。根っから優しいのに……」
言葉を濁す志島の真意は、杏子の胸をえぐった。宿った新たな命を軽んじはしない。それでも、始めたばかりの仕事を、小さいころから夢見ていた保母さんを、中途半端な形でやめることが、正しいのか誤りなのか?懊悩するばかりで、答えが導き出せない。
「杏子が出す解答は俺の解答でもあるんや。絶対受け止めてやる。じっくり考えてみろ」
「無責任だよ、保は。当事者やんか、保も」
「そやな。でも答えをだすのは杏子や。重い命の判断をつけな、先に進むことなんかできひん。母親になるかどうかを決めるんや」
「うん……わかった……考えてみる」
杏子が見やった恋人は懊悩の渦中にあった。志島は葛藤する心を持て余している。杏子以上の当事者意識に、志島は苛まれていた。