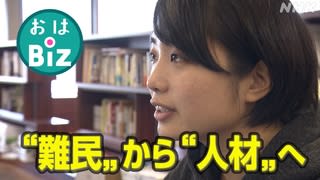NHK23.01.04(水)

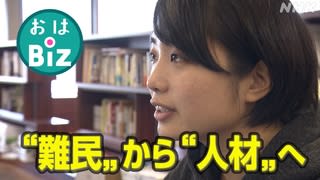
ロシアによるウクライナ侵攻から、2月で1年になります。ウクライナからの避難民は2,220人にのぼっています(出入国在留管理庁・2022年12月21日時点)。
各地で続く紛争や政情不安から難民・避難民として日本にやってきた人たちを、“支援が必要な人”から“人材”へと捉え直し、企業への就職を支援しているのがNPO「WELgee(ウェルジー)」代表の渡部カンコロンゴ清花さんです。“難民を雇用する”というこれまでにない支援の形をどのように築いてきたのか、そして難民と共生する社会を作る意味とは。副島萌生アナウンサーが聞きました。
副島アナウンサー
―よろしくお願いします。私たち同い年なのですが、取り組まれていることが相当すごいですね。お話しできるのを本当に楽しみにしていました。
渡部カンコロンゴ清花さん
うれしいです。テレビを見ても、ほかの人の仕事って自分より大人の人がやっているように見えます。お互いさまですね。
難民への雇用支援
―難民の方への支援は具体的にどういうアプローチで行っているのですか?
まずは日本にやって来た難民の人たちと出会うのですが、日本に来たのはいいけれど、日本の難民認定率はすごく低くてなかなか認定されない。とはいえ祖国に帰ったら危害が及ぶという、そのはざまに落ち続けている人たちがものすごくたくさんいることが分かってきました。いま結果が出るまで4年4か月と言われていますが、長いじゃないですか。
―認定までに4年4か月?
それだけ待っても約99%は認定がもらえない。大変な状況にあるものの、一人ひとりを見てみると、ユニークで、いろいろな経歴を持った志あふれる若者たちがいるぞというのが私たちのNPO「WELgee(ウェルジー)」の出発点です。さまざまな背景を持つ人たちをパイオニア人材として企業とつなげる活動をしています。
難民の若者たちの可能性を考えると、これが日本社会に生かされないのはもったいないし、本人たちも「支援してほしい」「保護してほしい」とだけ思っているわけではありません。ついこの間まで自分で起業して働いていたり、この先も勉強を続けていきたい、いつか平和になった祖国に戻って教育大臣になりたいとか。そう言っている人たちが、今はただ日々を過ごしているという状態です。
彼らを社会とつなげるって何だろうと試行錯誤をいろいろやってみる中で、企業とつながることで「自立」と「活躍」の2つを作れるのではないかと、就労やキャリアの支援活動が始まりました。
“逆境パッション”との出会い
―難民の方々、一人ひとりの可能性に気付いたのには、何かきっかけがありましたか?
学生のころ、日本にある教会がやっている難民の人たち向けの日本語教室で教師をしていました。教師と言ってもボランティアで、仕事を引退したシニアの方々や主婦の方、学生などが、週に1、2回日本語を教えるというものです。
そのボランティアの場で、いろんな話をする中で難民の人たちと普通に友達になったんです。「大学の時、何勉強してたの?」とか、「今度一緒にコーヒー飲みに行こうよ」とか。助けてあげるべき存在というより「もうちょっと話聞かせて」ってお互いに思う瞬間がポツポツと出てきたのが始まりだったかもしれません。
また、大学の時にはバングラデシュに2年間滞在したことがあります。ミャンマーとの国境付近にある先住民族の人たちが暮らしていた場所で、長らく紛争地だったところです。そこで、自分の国に弾圧される形で故郷を失ったり、命を失ったりする人たち、自分の国に消されていく人たちがいるということを初めて知りました。
一方で、いろいろな難関をくぐり抜けてたどりついてきた人たちと出会っていく中で、ネガティブな印象というよりはむしろ…“逆境パッション”を感じたんです。
―逆境パッション?
心の中に、逆境を乗り越えてきたパッション、志がある。でもそれの出し先が分からないし、使い方も分からないし、うずうずしているんだろうな、きっとっていう。
そういうことを関わっていく中で知るプロセスがありました。
支援のしくみ「ジョブコーパス」とは?
―難民の人たちを就労にまで結びつけるのは、かなり難しい道なのではと思いますが、具体的にどのような取り組みをしているのでしょうか?
「ジョブコーパス」という仕組みで4つのステップを通して支援していきます。まずは何よりも心の準備、「レディネス(readiness:準備)」と呼んでいます。難民になる過程で、政府やマフィアにだまされたり、何度も何度も裏切られてきた人が中にはいて、私たちのことも信頼しない、できないと、警戒している場合があります。お互い信頼関係ゼロのところから、徐々に信頼関係を作っていきます。
望んで日本に来たわけではないかもしれないし、予想のつかないことだらけだけど、「ここからもう1回、人生再建してみるぞ」っていう心の準備ができている状態がレディネス。それを高めていくための「置かれた状況を知る」というファーストステップです。
―就職活動の際の自己分析みたいなものですか?
自己分析に入るひとつ手前ぐらいですね。
日本の就活ってすごく独特なんです。自分のスキルを売る、ジョブ型で交渉していくのではなくて、まず一般職で入って、いろいろな仕事ができるようになるための訓練・研修が最初にたくさんあったり。持っているスキル、やってきたスキルよりも、会社へのカルチャーフィットとか、忠誠心がまだ求められているとか。
そういう経験をしてこなかった人にとっては何を求められているか分かりようがないので、企業文化、就活文化を知ってもらうためにいろいろな企業で仕事をしている人から話してもらおうと、ボランティアで参画している現役の社会人メンバーから就活やキャリアの話をしてもらう、ざっくばらんな会を定期的に開いています。
―そこを経ると?
第2のステップ、「メンターシッププログラム」です。
ここでのメンターは、自分のキャリアや人生を考えていく時に、話を聞いたり、悩みも打ち明けられたりする、お兄さんお姉さん的な存在です。日本社会で今働いているメンターと、難民申請中の就活中の方、1対1の組み合わせ。じっくり3か月かけて壮大な人生の棚卸しをして、レディネスをさらに高めていきます。
「家族が祖国で今どうなっているんだろう、自分だけ助かっちゃった」とか、「日本語もできない中で何ができるか分からない」、「今就活すべきか、来月の家賃のためにバイトに専念した方がいいのか分からない」そういうことを1対1でメンターの人に相談していきます。メンターはとことん聞くことを心がけ、受け止める。時には厳しいことも伝えます。関係性を築きながら、ここはじっくり3か月やっていきます。
―この段階を経ると?
「スキル開発」です。専門的な仕事に就くにも、やっぱり日本で働くには日本語が必要だよねと。業務を英語でできる会社や部署もあるのですが、最低限の日本語の会話ができるほど、入ったあとキャッチアップしやすいです。ネイティブにはならずともこの国で人生再建しようという時に、その国の言語は大切だなと感じているところです。
日本語だけでなく、ITスキルを伸ばしたい人は外部の会社と共同して学ぶなど、ハードスキルを高めていく段階もあります。
このスキル開発を経て、最後のステップ「キャリアの伴走」に入ります。ここでキャリアコーディネーターがつきます。難民人材だけでなく、登録して下さっている企業にとっても初めての一歩だったりするので、丁寧に伴走します。面接にはもちろん行きますし、インターンシップやお試し雇用をはさみながら正規の雇用につなげていく。
難民申請中は「特定活動」というビザで、不安定なものなので、企業が雇用スポンサーになれる段階になったら「技術人文知識国際業務」というビザに変更するところまでをサポートしていきます。長い道のりです。
“伴走”に込めた思い
―「伴走」という言葉を使っているのはなぜですか。
やっぱり就労支援じゃなくて、就労伴走事業なんだと思います。導いてあげるだけではなく、共に走っていくし、前に進めない時だってあるよと待つことも、キャリアコーディネーターのすごく大切な素質だと感じます。
難民だけじゃないですよね。人生常に頑張れないし、いろいろな逆境にぶつかりながら生きてるし、ちょっと休憩しようって思うことが誰にだってあります。”頑張らなかったら人生終わりだ”というのは、自己責任論にもつながっていくと思うんです。頑張れない時にも、「横にいるよ」って存在がひとりでもいれば、多分また歩きだせるから。そういう存在が実は社会にたくさんいるよって、一度は国を失ったような人たちにも言える社会になっていたら、あったかいなと思いますね。
難民の雇用が企業にもたらす変革
―これまでで何人ぐらいがキャリアに結びついたのでしょうか?
300人ぐらいの人たちに伴走していきながら、最後の最後の雇用に至ったのが20人ですね。さらに先の難民申請中のビザから働くビザに変えるところまでいった人が6人。その6人はもはや難民認定をゴールにしていません。企業で活躍する人材としてのビザを持っているので、法的にもさらに自由に働くことができ、海外出張も行けるんですよ。
―企業は雇うにあたって、きれい事だけではいかないところもありそうです。難民や避難民の方を受け入れることで企業が得られるメリット、どんな声が届いていますか?
それは本当に大事な点です。慈善事業としてとか、難民がかわいそうだからとりあえず短期で雇用するなどでは続かないんです、お互いに。企業の人にとっては、良いことだからやってみたかったけどうまく行かなかったっていう経験になりますし、難民の人にとっては、また足場を失ったという話になります。だから、お互い人として向き合いながら続けていくことを念頭に置いたマッチングと定着サポートをやっています。
企業にとってのメリットは大きくは3つでしょうか。
まずは「イノベーションの創出」になるということです。全く違うバックグラウンドを持って会社に入ってきてくれる存在がいることで、閉塞感を打破したり、新しいビジネス展開を考る時に、これまでのやり方と違うアイデアが出てくる。
具体的にはヤマハ発動機さんのケースがあります。アフリカにビジネス展開するときに、昔アフリカで起業していた難民の若者が雇用されたんです。アフリカの感覚値みたいなものがチームに何もない中でやっていくより、イノベーションを生む起爆剤人材になる。それは難民と企業が出会ったことで生まれる価値だと思います。
もう1つは、「社員の意識が変わっていく」ことです。ある企業の方が、難民の方が入ったことで丁寧にコミュニケーションを取らなきゃいけなくなって、時間がかかるようになったと。ただそれをやるようになったら、日本人社員のコミュニケーションもすごくよくなったそうなんです。
―それは面白いですね。
これまで気付かなかったけれど暗黙の了解で終えてしまっていたり、分かると思いこんで飛ばしていたコミュニケーションがあったときに、難民の方が入ってきて「分かりません」と言う。そこで、実はすり合ってなかったとか、思い込みだったということに気づく。それによって社員さんたちが変化していくという声を聞きますね。
そしてもう1つは、「企業の価値向上を対外的に伝えられる」ことです。企業の価値として、社会にプラスになることをしたり、社会に負荷をかけないことが大きな軸だと考えられるようになってきています。「ビジネスと人権」の流れは国がリードする形でも起こっていますが、単にサプライチェーン上に人権侵害がないか点検しますということだけでなく、「人権侵害の中から来た人たちがうちで活躍しているんですよ」ということが評価されると、自分たちの価値が高まっていくことにもなる。そういう連鎖がいま起き始めています。
企業が努力しなければいけないことはもちろんありますし、簡単には進みませんが、やってみるとまだ見ぬ何かが生まれる。長い目で見たら企業にとってもユニークな経験になるのではないでしょうか。
活動には壁も…
―とはいえ日本の難民認定率は1%以下。G7主要7か国で最低というこの数字をどう見ますか?
低いですよね。海外の方からインタビューを受けたりする時に、日本はどのぐらいの人たちを国の枠組みの中で保護して、そのうち何割ぐらいの人たちに関わっているの?と聞かれることがよくあるのですが。日本は国としての難民認定率は1%に満たない状況で…と説明すると「えっ?じゃあ認定されない人は何をしているの?」と、すごく驚かれます。
―取り組みに対して反発の声もあるのですか?
そうですね。反発の種類も本当に色々です。私たちのような若い女性がこういう活動をすること自体が気に入らないみたいな反発も当初はすごい多かったです。初めての活動を新聞に小さく取り上げてもらったところ、すごく炎上したり。”こういうやつらがいるから難民が日本に来て治安が悪くなる”といった声もありましたね。
今も聞くのは「日本にも困っている人がいるのに、なぜ難民を支援するのか」という意見ですね。人によっては「日本の子どもの貧困のほうが圧倒的に大切なイシューなのに」って考えていたり、他にもっと大変なことがあるのにそれを解決せず、なぜ難民のことをやるのかという考えだったり。そういうコメントをする方々に本当に精力的に向き合われているものがあって、その中でのもどかしさがもしかしたらあるのかもしれません。
一方で全然違う“移民アレルギー”みたいな形で、「自国民を差し置いて」っていうコメントが出るのかもしれません。今、欧米などでも“ウクライナ疲れ”があって「なぜウクライナの人たちに食べ物とシェルターを用意してるのに、この国のホームレスには何もしないんだ」っていうようなデモが起こっているのは事実なので。「なぜ自国民の前に?」という問いは多分これからも立ちはだかるし、難民を自国民より優先しろという話をしているわけでは全然ないとしても、そう聞こえるんだなということは私たちも学んでいます。そのうえで、どんな伝え方をしていけばいいかを考えていますね。
「難民」という人はいない
―私も含めて、難民の人たちと普段接することがないので、なかなか自分ごととして捉えられないところもあると思います。どうしたらより多くの人にとって身近な問題になると思いますか?
“難民の人と同僚になる”みたいな、そんな入り口を作りたいと思っています。やっぱり“テレビの中の課題”として見ているので、「ウクライナの方々を雇いたい」とお電話を下さる企業の方も「どこに行けば、どうすれば会えるのかも分からない」と。
また、「難民に向いている仕事ってなんですか?」という質問をいただくこともあります。よかれと思って、何かしら仕事を与えてあげたいと思って、「難民に向いている仕事とは?」と。
ただ、それは「人間に向いている仕事なんですか?」って聞くくらい答えがない質問です。出会った難民の人の分だけ、向いている仕事の数があります。もともとエンジニアをしていた人もいれば、看護師、ジャーナリスト、弁護士をしていた人もいます。失業率が高くて仕事に就けなかったから自分で会社を興した人、貿易をやっていた人もいれば、マーケターもPRの人も…。だから「難民に向いている仕事」はないんです。
そういう意味でも、私たちのような存在が、難民の人たちと社会をとことんつなげる役割を果たしていきたいです。どんな職種でもきっと難民人材の活躍に挑戦できます、と。
「自分の会社にもナイジェリアの人いてさ」とか、「実はシリアから昔、日本に難民として逃れてきたプログラマーと一緒に働いているよ」とか。そういうことが周りの人たちに、いろいろなポジティブな影響も与えていくと思うので。
―一人ひとり持っている可能性は違うっていうことですよね。ひとくくりにしない、難民という言葉でくくらないというか。
難民問題に向き合いながらこのプログラムを作ってきたんですけど、やればやるほど「難民っていう人間はいない」と感じます。もちろん難民に適した支援策は何だろうとか、難民認定率とか、難民という言葉には向き合わざるを得ないのですが。
でも難民になった人たちもなりたくてなったわけじゃないし、人生の目標が難民になることではない。3か月前まで自分が難民になるなんて全く考えていなかった人たちだっています。そんなことを考えると「難民という言葉でくくっている限り、やがて前に進めなくなるだろう」と自覚したところがありますね。難民という言葉自体を日本の社会の中でアップデートできるといいなと思っています。
“どんどん伴走”の1年に
―先ほど「ウクライナからの避難民を受け入れたい」っていう企業も出てきたと言っていましたが、ウクライナ避難民の方も受け入れているんですか?
2022年は、本当に“カオスオブカオス”でした。これまではアフリカとアフガニスタンの方の相談がいちばん多かったのですが、ウクライナの方の相談件数がそれを抜いたんです。でも先日、ひとり正規雇用で就職が決まりました。初出勤の前にうちのオフィスに来てくれて、「行ってくるね」って。
―すごい。この1年くらいで?
彼女は半年ぐらいの伴走でした。もともと本人が持っていたいろいろな経験や、「ばっちり合うかもしれない」って思って下さった職場があったから。あとはやはりウクライナ避難民の人たちに対しては、身近さや、何かしてあげたい気持ちがあるんですね。問い合わせも増えているし、すごくいい出会いも生まれています。
―悲しい状況ではあるけれども、今、難民・避難民に対する関心は高まっているように感じます。ウクライナ以外も含め、今後どう取り組んでいこうと考えていますか?
関心がワッて上がったときに関心で終わると、どこにも着地しません。これから時間はかかるし、お金は集まらないというフェーズに入っていくのですが、“関わりしろ”は本当にここから増えていくので、どんどん多くの人に関わってほしいと思います。
世界中で1億人の人が故郷を追われています。難民支援のプロだけでは解決できない規模の課題になっているので、どんどん伴走できる人を増やしていこうと議論をしているところです。ここでとことん伴走して着地させていくことが腕の見せどころだなと思いながら、踏ん張りながらも楽しく進めたらいいなと思っています。
【2023年1月5日放送】
https://www3.nhk.or.jp/news/contents/ohabiz/articles/2023_0105.html