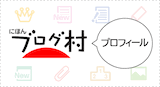クロクモソウ によく似た エゾクロクモソウ があることを知ったのは一昨年のことだった。
何気なくパラパラと拾い読みをしていた図鑑の記事で初めて知ったのだった。
撮り溜めた自分の写真を点検していると両者の画像が見つかった。
一昨年の北の又の調査では坪倉の河原で両者を確認した。
葉の特徴で区別して確認はできたのだが残念なことに坪倉へは開花期に調査に行けなかった。
クロクモソウ の葉は切れ込みの数が少なく丸みのある鋸歯になっている。
花の絵は 立山 室堂で出会った株。
エゾクロクモソウ の鋸歯は尖っており数も多い。
花は棚場で開花させた花だが 熱帯夜の続く土地柄では長く持ち続けることは出来ないようだ。