日曜朝、楽しみに見ていたNHK大河ドラマ「黄金の日日」が終わった。
昭和53年(1978年)作品の再放送で
歴代大河ドラマの中でも人気作のひとつだったという。
群雄割拠する安土桃山時代。
泉州・堺はどの軍事勢力にも加担せず、商人たちが自治を守る自由経済都市だった。
その堺に、豪商今井家の下働きながら、貿易商を夢見る青年・助左(のちの呂宋(ルソン)助左衛門)がいた。
何事にもひた向きな仕事ぶりに、主人の今井宗久はもちろん、
千宗易(のちの利休)たち堺の人々は助左を温かく見守る。
さらには、木下藤吉郎や石田三成、高山右近など戦国武将たちまでも
助左の才覚を認め支援の手を差し伸べるのだった。
ついに助左は自分の船を持ち、ルソン交易を皮切りに豪商への道を歩みだす。
しかし、激動する時代は助左の運命を飲み込もうとする。
堺の富を我が物にせんとする権力者たちが助左の前に立ちはだかったのだ。
大切な友、そして愛する人を次々に失いながらも
助左は権力者たちに敢然と立ち向かう。堺の自由と人々の尊厳を守るために。
原作は城山三郎。
「黄金の日日」が放映された昭和53年は私が社会人となった年だ。
当時、本を読むなら、「太郎さん」「次郎さん」「三郎さん」と教えられたもので
その三郎さんこと、城山三郎の経済小説は、社会人一年生の私に
大人の仲間入りをしたような高揚感を味合わせてくれた。
ちなみに「太郎さん」とは司馬遼太郎、「次郎さん」は新田次郎のことだ。
司馬遼太郎の歴史観には共感することが多く、
社会人生活を通じて参考になることが多かった。
とりわけ「坂の上の雲」では日露戦争、旅順攻略戦のくだりを何度も読み返し、
二〇三高地からの景色を見たくて旅順まで出かけたくらいだ。
また、新田次郎の「富士山頂」など山岳小説からは
ずいぶんと勇気をもらったものだが、聞くところによると
某大手コンサル会社は「八甲田山死の彷徨」を
今でも人材研修の教材として使っているらしい。
話がずいぶんとずれてしまった。
次回話を戻して続く。
黄金の日日 1話 オープニング
NHK交響楽団による壮大なテーマ曲。
フィリピン沖で撮影されたという落日の映像とともに
自分にとっては、このドラマの見どころのひとつだった。











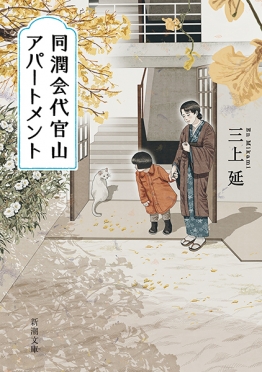














 ひがし茶屋街 金沢市東山
ひがし茶屋街 金沢市東山
 朝もやの港区あたり:新宿超高層ビルから
朝もやの港区あたり:新宿超高層ビルから




