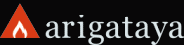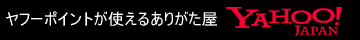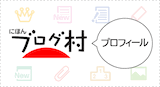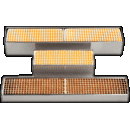薪ストーブ暮らしが大好きでブログ書いてます。
燃焼のこと、薪作りやメンテナンスのこと、そんな写真と駄文で毎日更新!
薪ストーブ|薪焚亭
もう分かってる人もいるでしょうが一応種明かしです

いよいよ最終回です。
驚愕の温度? 451.3℃ のつづきですね。
実は、今回の細工ってのは、もう随分前からやってみようと思ってたことなんですが、仕事部屋では料理もしないし、お湯さえも必ずしも沸かさなきゃならないという訳でもなかったので、それでずっとペンディングだったんですよね。
それが今回、仕事部屋に珈琲の香りをとパーコレーターを買ってしまったので、使えないんじゃしょうがないってんで急遽細工をしたのです。
ただ、これは基本的には真似しないでくださいね。 たぶんメーカー保証は受けられなくなりますから。 それでもいいよって人はどうぞ自己責任でやってください(笑)
確かにこの方法だと強烈な熱を得ることができるので、これまでダッチウエストのコンベクションシリーズを使ってて、トップ温度に不満があった人には有効だとは思います。 これだけ熱くなれば、これまでコトコト煮物がメインだったトップでの調理バリエーションに、フライパンでの焼き料理も加わりそうです。
さて、細工ですが、やったことは何てことはなくて、二次燃焼室の触媒カバーであるリフラクトリーに少し穴を開けただけなんです。 これはアンコールの二次燃焼室と同じ材質で、とても軟らかいセラミックなのでカッターナイフで簡単に刻めます。
穴は写真の位置でちょうど触媒の中心位になってます。 大きさはそれこそテキトーです。 実際焚いてみて分かったのであとの祭りですが、もう少し小さくても良かったかなと思ってます。 なので、熱すぎるのがイヤになったら、ガスケットあたりで半分くらい塞いでしまってもいいかも知れないですね。 でもまぁこれで大丈夫でしょう。

穴を開けた訳ですから、とうぜん排気の流れは変わりますが、まぁ最終排気なのでこれ自体は大した問題じゃないでしょう。 たぶん(笑)
知らない人も多いと思いますが、実は昔のダッチウエストの薪ストーブにはリフラクトリーなんて無かったんですよ。 天板の下はもろに触媒でした。 正確に言うと、触媒の真上に15センチ角程度の取り外し可能なグリドルがあったんです。 なので、あの頃のダッチの薪ストーブはトップが熱々で調理が今よりも得意だったんですよね。
1980年代のコンベクションシリーズだった224、264、267、288など、全部そうでした。 それが1990年以降になるとリフラクトリーが間に挟まれるようになったのですが、何か問題でもあったんでしょうかね?
そのあたりの経緯については、残念ながら自分はまったく知りません。

もし、どうしても穴を開けてみたいという人は、この半分くらいの大きさから試してみたらいいと思います。 くどいようですが、あくまでも自己責任でね(笑)
まきたきてー発電所 毎日の発電実績
コメント ( 24 ) | Trackback ( )