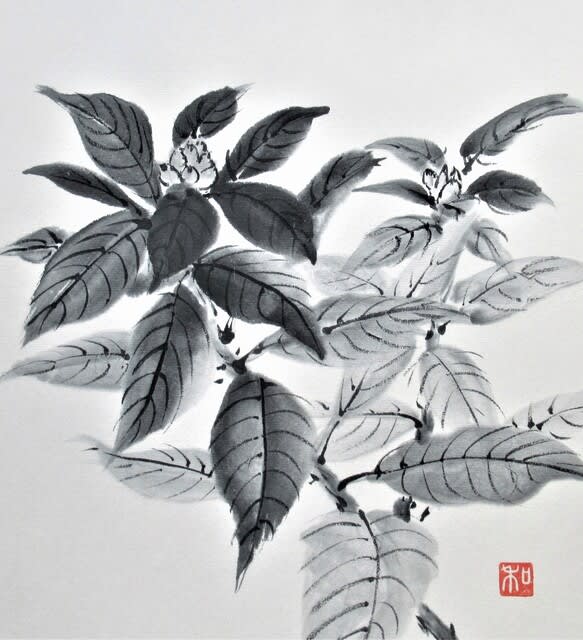小カブが最も旨い時期になりました。
当地方も、先週に積雪があり、冷え込みが一段と強まりました。
冬になると、野菜は寒さから身を守るため体内に糖分を蓄えます。小カブも甘味と旨味が増し、今が正に旬と言えます。
当地方も、先週に積雪があり、冷え込みが一段と強まりました。
冬になると、野菜は寒さから身を守るため体内に糖分を蓄えます。小カブも甘味と旨味が増し、今が正に旬と言えます。

葉も濃緑の伸び伸びした葉から、低温で少し黄ばみ締まった姿になってきました。

品種は昔と変らず「耐病ひかり」。
種播きが9月24日と例年より少し遅く、11月半ばから収穫を始めました。
当初、株間10~15センチのやや密植の状態から、順次大きくなった小カブから穫っているので、現在は株間15~20センチと丁度適当な状態になっています。
種播きが9月24日と例年より少し遅く、11月半ばから収穫を始めました。
当初、株間10~15センチのやや密植の状態から、順次大きくなった小カブから穫っているので、現在は株間15~20センチと丁度適当な状態になっています。

初めは生育にバラツキが見られますが、生長が早いものから収穫されていくので、今時分になると全体の小カブが揃ってきます。

収穫始めのように一つ一つ確かめなくても大体適当な大きさの小カブが穫れるようになっています。
それでも、やはり畝の中央付近は少し遅れている株があり、少し葉をかき分けて見ます。

「耐病ひかり」と言う品種は、蕪が大きくなっても美味しく食べられるのが利点です。とはいっても、やはり、生育日数が長くなってくると、次第に繊維分がでて硬く感じられるようになります。
今がピーク、最も手頃な大きさで滑らかな舌触り、甘味と旨味、一番美味しい小カブを楽しむことができます。葉や茎も味が出て美味しい。
収穫したときのカブの姿も絵になります。

洗い立ての純白の蕪は目に眩しいほどです。
この白い蕪の部分の本体は茎で、根はその下に付いている尻尾の部分です。これがダイコンとの大きな違い。土の中に入っているのはこの尻尾の部分だけですから、触っただけで穫れてきます。

今、食卓には毎食のように小カブの浅漬けが出ますが、飽きることがありません。