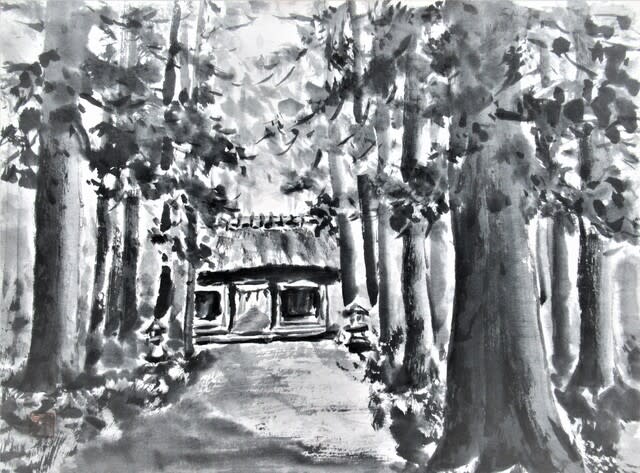画仙紙 半切1/3

2019年10月、台風19号の被害に目をつぶりささやかな旅を決行。信州から甲州に足を伸ばしました。
甲府市には仕事がらみで行ったことはあるのですが、その時は観光は出来ずじまい。
一度は訪ねたいと思っていたのが昇仙峡。絵になりそうだという予備知識を得ていたからです。
渓谷に沿って遊歩道があり、断崖や奇岩、滝などが次々に現れ変化に富んだ渓谷美を楽しめます。
画のモチーフになりそうなスポットも多々あります。
その中の断崖絶壁の代表的なところが覚円峰。
その上で覚円禅師が修行されたところからその名が付いたと言います。
霧が立てば一瞬中国の黄山や武陵源を想起させるような景観と言ったところでしょうか。
もっとも黄山や武陵源を実際には見たことがないので大げさと言われるかもしれません。