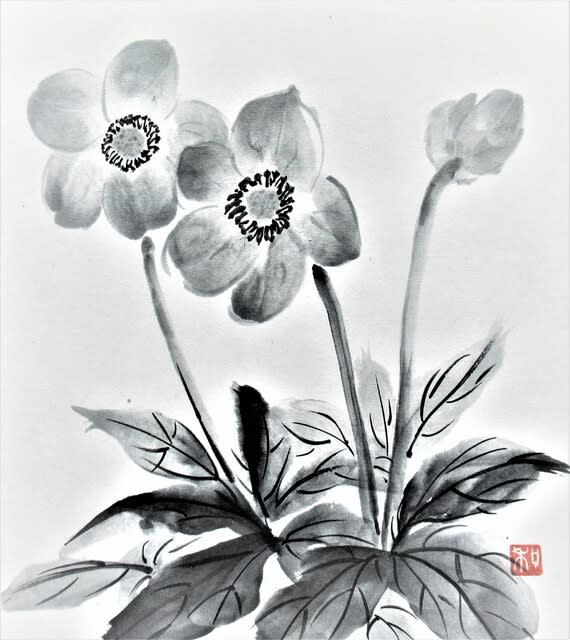ダイコンとニンジンを本格的に穫り始めました。
今年、ダイコンは1週間ほど間隔をおいて3回に播いています。
今年、ダイコンは1週間ほど間隔をおいて3回に播いています。

収穫しているのは1回目の8月23日に播いたもの。
10日ほど前から肥大の良さそうなものを確認しながら穫り始めました。
今はどれも同じくらいに太ってきたのでどれを穫っても良さそうです。
今はどれも同じくらいに太ってきたのでどれを穫っても良さそうです。

品種はタキイ種苗の「耐病総太り」。
生育は概ね順調。台風が来襲しそうだというので急遽土寄せしたりということもありましたが、結局大したことはありませんでした。
ただし、最近は過乾燥気味です。
畑が粘土質で緩い傾斜になっているので、曲がりやすいのはやむを得ません。
生育は概ね順調。台風が来襲しそうだというので急遽土寄せしたりということもありましたが、結局大したことはありませんでした。
ただし、最近は過乾燥気味です。
畑が粘土質で緩い傾斜になっているので、曲がりやすいのはやむを得ません。

2本引き抜きました。

曲がりはあるもののこの時期としてはまずまず。
長さは十分ながら、「耐病総太り」としてはまだ若干物足りません。
尻までしっかりと肉が付くまで太るにはもう少し時間が必要。
肌は綺麗で、最近は夜も冷えてきたので味が乗ってきました。
こちらは2回目、3回目に播いたダイコン。
長さは十分ながら、「耐病総太り」としてはまだ若干物足りません。
尻までしっかりと肉が付くまで太るにはもう少し時間が必要。
肌は綺麗で、最近は夜も冷えてきたので味が乗ってきました。
こちらは2回目、3回目に播いたダイコン。

品種は全て「耐病総太り」。
何れも順調に生育していますが、一雨欲しいところではあります。
3回目のダイコンは主に冬囲いに回ります。
ダイコンは年々消費が減っており、作付けを減らしています。
こちらはニンジン。
何れも順調に生育していますが、一雨欲しいところではあります。
3回目のダイコンは主に冬囲いに回ります。
ダイコンは年々消費が減っており、作付けを減らしています。
こちらはニンジン。


間引きが遅れ少々混みすぎになりました。
ウスカワマイマイが繁殖するなど芳しくありませんでしたが、今月早々に間引きを兼ね肥大の良さそうなものから穫り始めました。
最近の異常乾燥で、土が固結気味で引き抜きにくい。スコップを使いながら収穫しました。
肥大や揃いはイマイチといったところ。
ウスカワマイマイが繁殖するなど芳しくありませんでしたが、今月早々に間引きを兼ね肥大の良さそうなものから穫り始めました。
最近の異常乾燥で、土が固結気味で引き抜きにくい。スコップを使いながら収穫しました。
肥大や揃いはイマイチといったところ。

茎葉が茂りすぎ、いわゆる葉勝ちの状態になったようです。肥料が少し効き過ぎかもしれません。

これは2回目に播いた冬ニンジン。

12月からの収穫予定で、一部は囲いに回ります。
間引きも遅れ気味ながら1回目ほどではありませんでした。
茎葉も1回目ほどには茂っていません。この程度なら問題なさそう。
ダイコン、ニンジンとも囲いも含めて約半年間穫り続けるつもりです。
間引きも遅れ気味ながら1回目ほどではありませんでした。
茎葉も1回目ほどには茂っていません。この程度なら問題なさそう。
ダイコン、ニンジンとも囲いも含めて約半年間穫り続けるつもりです。