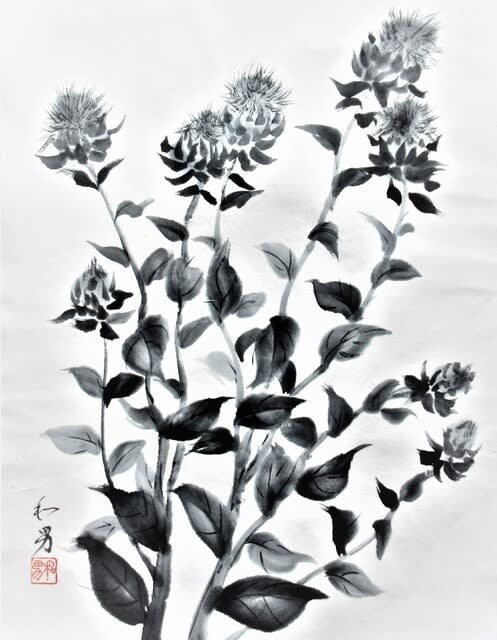イネは田植えをしてほぼ50日。生育は順調です。
5月は強風が吹き荒れた日もありましたが、総じて言えば高温乾燥。
そして、6月は初めこそ不安定な天候で気温も低めだったものの、その後は異常なほどの高温乾燥です。
当地方の平年の梅雨入りは6月12日。今年は6月23日に少しばかりの降雨がありようやく梅雨入り。
空梅雨の様相となっています。
当地方は梅雨入りすると多少なりヤマセによる気温の低い日が出現することが多い。
今年はまだ1日もなし。そもそもこれほど雨の少ない6月は記憶にありません。
こんな天候なのですからイネの生育は進んでいると考えるべきでしょう。
草丈も伸びているようです。
分けつも順調で茎数も多くなっています。
最終の1株の目標茎数は25本。
勿論バラツキはあり、30本を超えるような株も相当数あります。
20本に達しない株も僅かありますが、これは植付け時の本数がごく少なかったものでしょう。
全体的に見れば早々に目標茎数に達したと見て、先週末から田んぼの水を切り、中干しに入りました。
少々雨は降りましたが、この田んぼはスムーズに水が抜け小さなひび割れが見えています。

こちらは別の田んぼ.
こちらは少しバラツキがあり、茎数がそれほど多くありません。
田んぼの均平を図るため土を少し引いたのが影響しているようです。
それでも多くは茎数25本には達しています。
中干しをするのは特定の時期に限定されます。
穂の元になるいわゆる幼穂形成期には水が必要になります。こちらも同じく先週末に水を切りました。
周囲の方は乾いてきましたが、中ほどはまだかなりぬかるんでいます。
イネの茎数は穂の数に直結するので少なければ当然減収します。
しかし、多ければ良いというものではありません。
イネの能力には限界があり、天候もベストの条件になるとは限りません。
必要以上に茎数が多く米粒が過剰になるとくず米が多発し、品質が低下します。
そこで中干しを行うのです。
中干しは、田んぼの水を切ることで無駄な分けつを抑えます。
また土に酸素を供給することで根の活力維持にも効果があるとされています。
そして、土が固まるため秋の刈り取り作業がやりやすくなる効果もあります。
これは別の田んぼ。
一見揃いが良く十分な茎数に達しているようです。
中干しは田んぼの表面に小さな亀裂が出るくらいに乾かすのが目安になります。
この田んぼはこれまでしばしば水の無くなる時がありました。そのため乾きも早いようです。
亀裂が出て、中ほどまで乾いてきました。
中干しの期間は10日くらいで、いわゆる幼穂形成期に入る頃までです。
田植えの早い我が家の田んぼは生育が進んでいると思うので、7月初め頃まで、遅くとも7月5日までには水を入れる必要があります。
しかし、現実は理屈のようにはいきません。普通中干しは梅雨期の真っ只中になります。
一枚の田んぼでも周囲や高いところから乾いていくので容易に全面が均一には乾きません。
水を切りたいときには雨が降り、必要なときには雨が降らない、天候は皮肉に出来ています。
そして7月は穂の元になる幼穂が生長する最も重要な時期。当地方ではヤマセと格闘する時期ですが今年はどうでしょう。