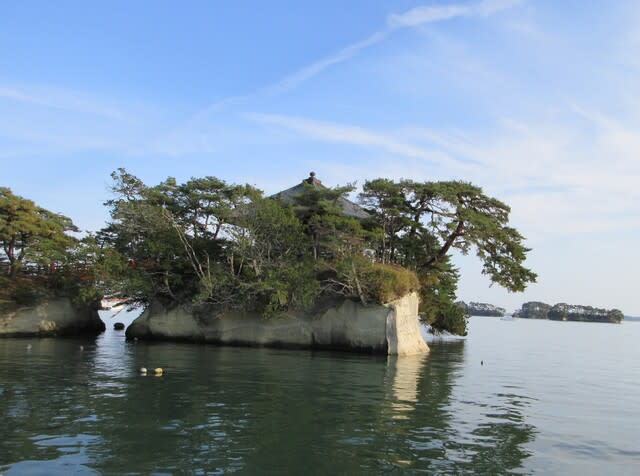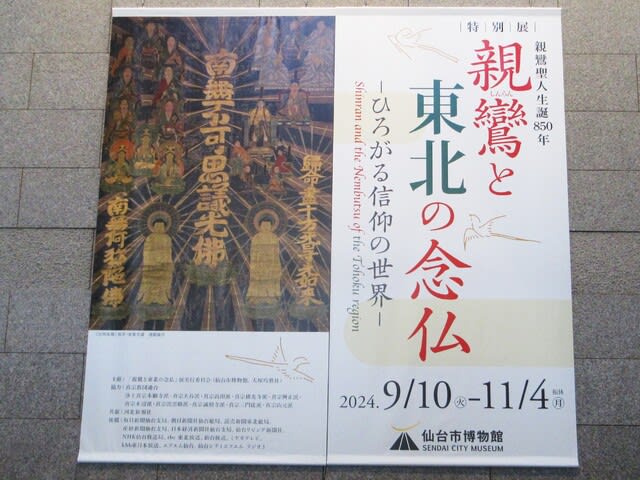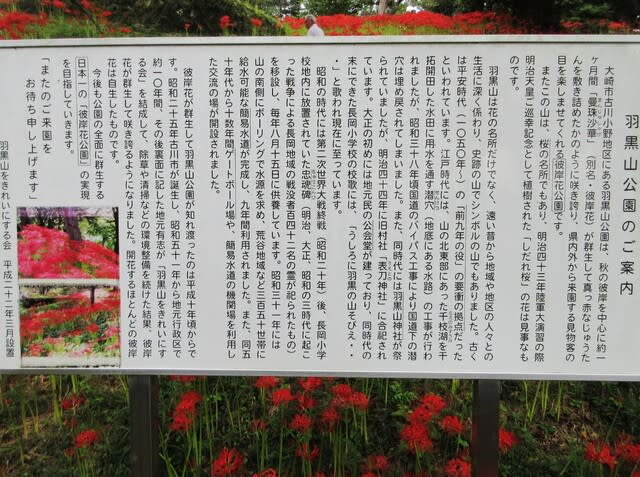たまたま所用で出かけたついでに、白鳥を見ようと思い立ちました。
これまで何度か訪ねていますが、暫くぶりです。
当県には白鳥の飛来地がかなりあり、有名なのはラムサール条約にも登録されている県北部の伊豆沼・内沼です。
県南部にも次第に増え小規模ながら数カ所の飛来地があります。最も古いのがこちら。

東北本線東白石駅に近い阿武隈川支流の白石川で、松ヶ丘河川公園(白鳥公園)という名前は今回知りました。

対岸が東北本線東白石駅。丁度貨物列車が通ったところ。東北自動車道白石ICからもほど近い場所です。

当地は白石市と思っていましたが、今回改めて標識を確認すると蔵王町分でした。市町境に位置します。
以前訪れたときはもっと多数いたと思いましたが、大分少なくなっていました。

餌を求めて一時飛び立っている可能性もあります。近くの麦畑で啄んでいる姿を見かけました。

近づいても全く逃げるそぶりを見せません。最近は餌付けを止めていると聞いていましたが。

数的にはカモの方がはるかに多い。のんびりと日向ぼっこをしていました。

この地は大正時代に身を挺して川で溺れた生徒たちを救った小野訓導殉職の地としても知られています。

ちょっと移動したところで眼前にくっきりと蔵王連峰が見えました。

白銀の蔵王連峰が綺麗に見えるチャンスはそうありません。この季節は見えるときはクリアに見えます。
全く予定していなかったのですが、急遽絶景ポイントから撮ってみることにしました。
白鳥公園からは北方向、東北本線北白川駅の近く。流れている川は白石川、中央に橋が見えるのが東北新幹線。

小生の場合、狙って撮ることは殆どないため単なる偶然、運任せです。このくらいクリアに見えるのは珍しい。

蔵王連峰は、蔵王山(ざおうざん)と呼ばれることが多いのですが、蔵王山という単独峰はありません。
お釜のある刈田岳を中心に北東から南西に宮城県と山形県を跨ぐ多くの峰が連なる連峰です。
このポイントから見えているのは宮城県側で宮城蔵王あるいは表蔵王、南蔵王と呼ばれることもあります。

次いで、逆に南に移動し、東北新幹線白石蔵王駅のほど近く。

左手前に見えるのが東北新幹線の白石蔵王駅。白銀輝く蔵王連峰が迫力ある姿を見せてくれました。

一帯に雪が全くないのが残念。今年は特に降雪が少ないですが、雪に覆われる時は肝心の蔵王が見えないことが多い。
この地点からだと蔵王連峰でもいわゆる南蔵王といわれる峰々が望めます。左から不忘山、屏風岳が綺麗に見えます。

中央にはみやぎ蔵王白石スキー場のゲレンデが見えます。今年山は1mを超える積雪に恵まれ喜んでいることでしょう。
思いがけず川辺の白鳥と白銀の蔵王連峰を撮ることが出来ました。