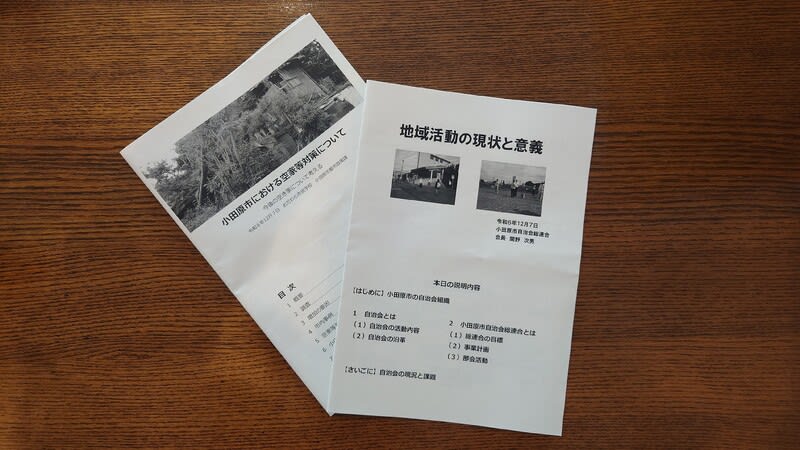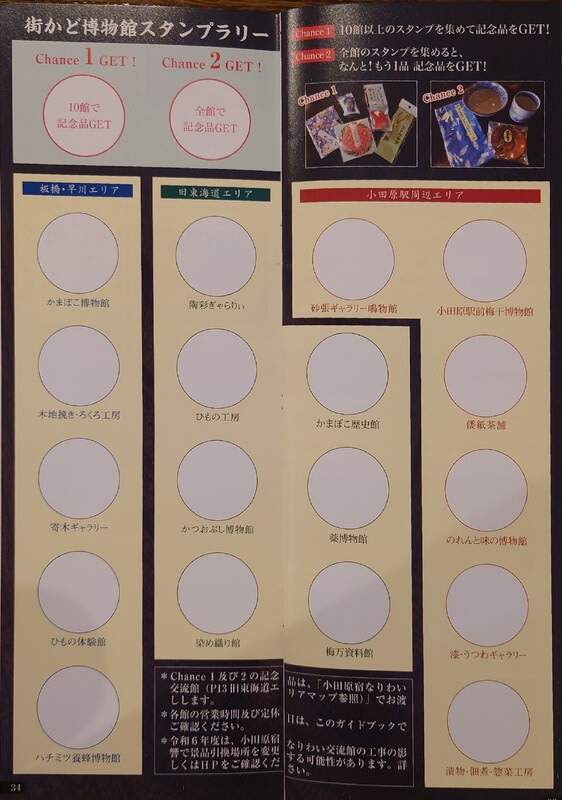今日はおだわら市民学校の14コマめ
松永記念館での講習だ
最寄り駅は箱根登山鉄道の箱根板橋駅

ちと可愛げな駅舎だね
駅からの徒歩途中に雰囲気のある建屋が

醤油醸造を営んでいた内野さんという方の店舗兼住宅だったところだ
さて今日の会場は松永記念館
明治から昭和にかけて電力王と呼ばれ、茶人でもあった松永安左エ門とは こちらへ
今日の講義は茶道が中心

もうお気付きだろうが、俺的にはあまり興味ない内容だった
その後さら~っと建屋をいくつか案内された
室内の映像をSNS等に揚げる場合は許可が必要とのことでここに載せれないが、
住居としていた老欅荘は「削ぎ落とした美しさ」と言える美があった
こここだけでも訪れる価値があるだろう
講習が終わり外に出ると

梅が咲き始めてるね
さあこれから小田原は
梅 ⇒ 河津桜 ⇒ 春めき桜 ⇒ ソメイヨシノ ⇒ シャガ
と続く華麗なリレーが始まるぞ (^^)
駅まで帰る途中で TEA FACTORY 如春園(じょしゅんえん)で昼食にした


外観も内部も雰囲気よし♪
それになんたって 美味いっ

今日は海老カレーの気分だった
車じゃないから勿論 飲むし v(^^)
ああなんか今日も いい日だったな











 ←クリックで拡大
←クリックで拡大 ←クリックで拡大
←クリックで拡大