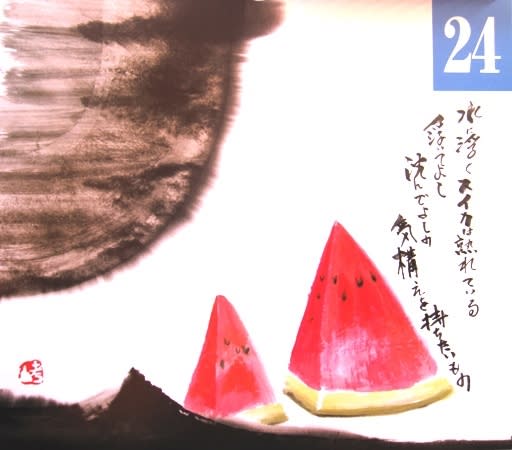【加瀬英明・石平著、ワック株式会社】
「中華人民共和国は同じ穴の狢(むじな)である太子党と、共産青年同盟団の赤い貴族たちの、およそ三百ファミリーの盗賊集団によって支配されている」「中国共産党が2021年に、創立百周年を祝うことはできないと信じている」――。ユニークなタイトルに加え、まえがきの歯に衣着せぬ物言いに引かれた。「『公』のある日本と『私』しかない中国」「すべて自分のものとする中華の幻想」など8章の構成で、加瀬・石平(せき・へい)両氏の対談を通じて中国の独特な文化と行動様式がどのように形成されてきたかを掘り下げる。

加瀬は1936年生まれの外交評論家。福田・中曽根内閣で首相特別顧問として対米折衝に貢献、伊能忠敬の玄孫でもある。一方の石平は1962年中国・成都生まれで北京大学哲学部卒。88年に来日し神戸大学大学院文化学研究科博士課程を修了、2007年日本に帰化。中国や日中関係問題を中心に精力的に執筆、講演活動を展開している。
加瀬は中国を中国人たらしめているのは儒教と漢字であるとし、漢字は「悪魔の字」とまでいう。「楔形文字や漢字のような難解な表意文字を持った文明は、支配階級だけが読み書きできて文字を独り占めし、蒙昧な人民に対して圧制を行った。それに対し、アルファベットや日本のかな文字のような表音文字を持った文化は、文字が容易に普及し識字率が高かったから健全に発展した」。石平も「漢字は結局、コミュニケーションの手段であるよりも、最初から命令の手段だった」とする。
加瀬は「科挙」が中国の発展を阻んできたとみる。「人材登用のため清朝が滅びる寸前まで1300年も続けた。科挙は全国を激しい受験戦争に捲き込んで創意を奪った」。中国で汚職の多発が問題になっているが、中国では古くから「升官発財(しょうかんほつざい)」(官になれば財がいっぱいたまる)といわれてきたそうだ。中国語には日本語にない「清官」「官禍」といった言葉もあるという。賄賂を取らない清潔な役人は極めて珍しいということの裏返しだろう。
石平は「中国には家族があって公がない。その根底には儒教がある」という。日本も儒教を取り入れたが、「本質が全然違う。日本の儒教は中国の儒教の言葉を借りて、日本人の価値観を語ったもの」。そして「何か事が起きると、相手〝に〟悪いと思うのが日本人、相手〝が〟悪いと思うのが中国人」と指摘する。加瀬も中国の儒教について「私欲を偽装するために用いられてきた」とみる。
加瀬は孫文が中国人を「一盤散砂」(大きな皿に盛った砂のようにすぐバラバラになる)と嘆いたことと、日本の「君が代」の中の「さざれ石の巌となりて」を取り上げながら「全く正反対の国柄である」と指摘。加瀬が「国名に『人民』とか『民主』が入っている国にろくな国がない」と言うと、石平も「徳がないからこそ、わざわざ徳の精神を唱える。人民不在だから、わざわざ人民をつける」と呼応する。
加瀬によると中国には「抜きがたい優越感と癒しがたい劣等感」が共存する。世界で最も優れた中華文明の継承者なのに、いつの間にか日本のほうがずっと先行していた。石平は日本側にも「昔は中国から教えてもらったという劣等感を払拭できずに、日中間には二重の錯覚がある」と指摘する。加瀬によると20世紀は「大帝国の解体の歴史」。石平は「いずれ中華帝国が解体し、中華連邦的な小国寡民になれば、民にとっても世界にとっても周辺国にとっても一番幸せ」と結んだ。