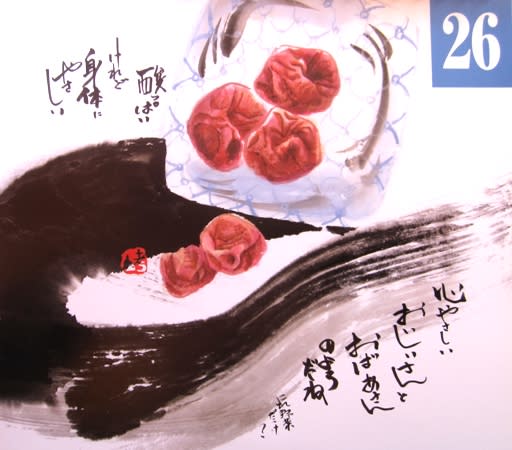【日本固有種、〝豊年満作〟由来説も】
けいはんな記念公園(京都府精華町)でマンサクの花が咲き始めたと聞いて早速行ってみた。まだ冬姿の「紅葉谷」。その一角に小枝に枯れ葉を付けたまま、黄色い可憐な小花がちらほら綻び始めたマンサクがあった。冬の日差しを浴びようと紐のような細い花弁を懸命に伸ばすさまは、まるでイソギンチャクのようにも、笛を吹くと紙が伸びるおもちゃの「吹き戻し」のようにも見えた。

日本原産の落葉小高木で、早春他の花木に先駆けて「先(ま)んず咲く」ため転じてこの名が付いたといわれる。いやいや、名前は枝の節々に花をたくさん付けるため「豊年満作」に由来する、との説もある。縁起がいいため農家の庭先に好んで植えられる。ただ地域によっては花がまばらにしか咲かないと、その年は不作になるという言い伝えもあるそうだ。
マンサクは主に太平洋側に分布する。同じ仲間に日本海側に多いマルバマンサクや中国地方の山地に自生するアテツマンサク(岡山・阿哲地方に由来)がある。この他の品種に花弁全体が赤色を帯びるアカバナマンサク、中心部が赤くなるニシキマンサクなど。外国産には中国原産のシナマンサク、北米原産で秋咲きのアメリカマンサクがある。このうちシナマンサクは花期にも枯れ葉が落ちずに残るのが特徴。けいはんな記念公園で撮ったこの写真もシナマンサクだった。
マンサクは枝がしなやかで弾力性に富むことや花の少ない時期に咲くことから、生け花や茶花として人気が高い。北陸や飛騨地方では「ネソ」とも呼ばれ、白川郷の合掌造りなどでは柱をしばる結束素材として古くから大切な役割を果たしてきた。かつては筏(いかだ)や背負い籠などの結束にも使われたという。マンサクは欧米で「Witch hazel(魔女の榛=はしばみ)」と呼ばれる。
静岡県浜松市の「乎那(おな)の峯」の群生地は県の天然記念物に指定され、毎年見頃となる2月中旬には「マンサクまつり」が開かれる。今年は17日(日曜)に開催される予定という。岡山県奈義町皆木や大分県久住高原、秋田県鳥海山などの群生地も有名。俳句の季語では早春。「まんさくや小雪となりし朝の雨」(水原秋桜子)。