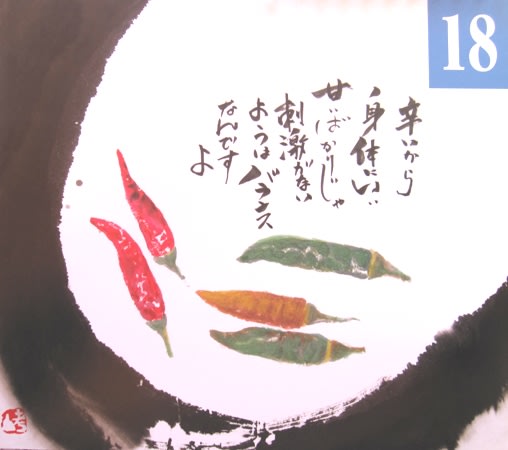【「毎日現代書 関西代表作家展」に特別陳列】
陶芸、篆刻、絵画、漆芸、木工、料理など様々な分野で類まれな才能を発揮した北大路魯山人(1883~1959年)。その芸術活動の出発点は書家としてだった。京都の上賀茂神社の社家に生まれた魯山人は10代半ばで当時流行していた「一字書き」の名手として名を上げ、21歳の時には隷書「千字文」で日本美術展覧会の1等賞を受賞した。22日まで大阪市の近鉄百貨店阿倍野店で開かれていた「第28回毎日現代書 関西代表作家展」に、その魯山人の書が特別陳列されていた。

展示作は横書きの「閑林」「娯泉石」「識法者懼」「山河走處」「玄遠」「獨歩青天」(写真)と縦書きの掛け軸「白馬入蘆花」「聴雪」の計8点。その両端には魯山人が焼いた花瓶「天上呉須花入」と「備前旅枕花入」が飾られていた。これらの作品の出展は「何必館(かひつかん)京都現代美術館」の協力による。何必館は日本画の村上華岳、洋画の山口薫、そして魯山人の作品の収集・展示で知られる。


魯山人は書聖といわれた中国の王義之や顔真卿の書に学び、良寛に傾倒した。展示作品は自由闊達な美意識を映すように、やや荒々しく躍動感と生命力にあふれていた。筆を取ると一気に書き上げたのだろう。良寛に心酔していた魯山人の書は次第に良寛の書に似ていったともいわれる。
魯山人の芸術観を端的に表した言葉に「坐辺師友」がある。自分の身辺や周辺の生活空間にあるもの全てが己の師であり友である。優れた美術品に囲まれて生活していると、自ずと創作した先人の心や工夫を学び取ることができる――。生前、傲慢・不遜と揶揄された魯山人だが、こうした批判や世間の名声には無頓着で、生涯を美の追求に捧げた。72歳の時には重要無形文化財保持者(人間国宝)の認定を打診されるが、これも固辞している。































 初代歌川豊国
初代歌川豊国