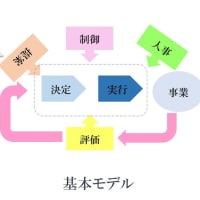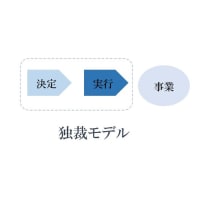自民党総裁選挙の様子を見ておりますと、何れの候補者の背後にもグローバリスト、即ち、世界権力の陰が見え隠れしています。自民党のみならず、今般、立憲民主党の代表に選ばれた野田佳彦元首相が、10%消費税増税を‘国際公約’として打ち出し、今日に至るまでの増税路線を敷いた‘張本人’であったことを思い起こしますと、野党の政治家達も世界権力の手の内にあるのでしょう。二頭作戦、あるいは、多頭作戦は、お手のものなのです。
グローバリズムが全世界の諸国を席巻するに至って既に30年余りの年月が経過しておりますが、その手法を観察しますと、グローバリズムの浸透方法が、新興宗教の勧誘の手法に類似していることに気がつかされます。その理由は、自己の‘教義’の絶対性の主張、無誤謬の確信、並びに信者に対する奉仕と犠牲の要求という、一般の人々を対象とした一種の洗脳を伴うからです。
実際に、グローバリズムの洗脳は、全世界に張り巡らされたマスメディアがその宣伝機関、否、布教機関となりましたので、その効果は絶大でした。80年代以降、グローバリズムは‘自由’の価値を纏って彗星の如くに現れ、自由で開放感に溢れた未来ヴィジョンを描いてみせたのですから。この結果、中国を含む何れの諸国でも、自由化こそ進むべき唯一の道であるとする信仰が広がり、規制緩和や民営化が推進されると共に、通商上の関税や非関税障壁のみならず、人の自由移動を促進するために国境まで取り払おうとしてしまいました。しかも、各国政府の取り込みに留まらず、大多数の人々をグローバリズムの信者にすることにも成功し、‘殉教者’の出現まで期待できるまでに信仰心が高まったのです。懐疑論者は異端者扱いとなり、批判の声も殆ど聞えない状態にまで至ったのですから、人類史上、最高の布教率であったのかも知れません。
しかしながら、グローバリズムとは、それが新自由主義という経済学上の理論の名で呼ばれたとしても、あくまでも‘理想’を説くものであって、実証性を伴うものでも、確約されたものでもありませんでした(しかも、経済の範囲を超えて社会全体の改革や人間の精神性にも踏み込んでいるので、より思想・宗教的・・・)。自由貿易主義のバイブルともされたデヴィット・リカードの比較優位説が世に登場した時期こそ、後に大英帝国として現れるイギリス、否、より正確には東インド会社による植民地化が進んだ時期と重なるのと類似しています(因みに、リカードは、オランダからイギリスに移住してきたセファルディ系のユダヤ人の家系に生まれている・・・)。そして、アレキサンダー大王の世界帝国の建設が、コスモポリタニズム(世界市民主義)を伴った点を考慮しますと、世界の一体化という理想主義には、異民族支配という隠れた目的が潜んでいるリスクを認めざるを得ないのです。理想を追い求めたはずが、現実はその逆なるという事例は歴史に枚挙に暇がありません。
そして、現実が理想の逆となる、あるいは、理想通りには行かない現実に信者達が気がついた時の対応も、どこか新興宗教団体と似通っています。疑問を抱く信者に対しては、‘信心が足りない’として、理想の実現に向けたより一層の努力を求めるからです。例えば、竹中平蔵氏をはじめとした新自由主義者の人々は、日本経済が低迷を続けている理由を不十分な自由化にあると主張しています。グローバリズムを信じた結果が日本国の今日の惨状であるにも拘わらず、それをさらに先に進めるように訴えているのです。
自然界でも、動物であれ植物であれ、外来種の出現により、これまで多様性を保つ形で自然に成立してきた生態系のバランスが崩壊し、特定の生物だけが蔓延ってしまう現象が問題視されています。また、高低差や濃度差などがある場合には、隔てる仕切りを取り除けば時間の経過と共に平準化されるのは当然の流れです。合理的に考えれば、自由と多様性の維持は両立せず、グローバリズムが全ての人々を豊かにするわけではないことは至極当然であるにも拘わらず、それがあたかも可能なように吹聴するのは、もはや‘グローバル教’としか言い様がないのです。
もっとも、グローバリズムの場合、結果が現実のマイナス現象として目に見える形で現れるのが、宗教との違いかも知れません。言い換えますと、否が応でも現実を突きつけられてしまうグローバリズムの方が、洗脳が解けやすいのです。この点、日本国民の多くがグローバリストの欺瞞や野望に気がついているからこそ、小泉進次郎候補の雇用規制の緩和、すなわち、解雇の‘自由化’の提言に対して強い反発を示したのでしょう。もはや、誰もが更なる自由化が国民に安心と豊かさをもたらすとする教説を信じなくなっているのではないでしょうか。そして、‘グローバル教’の宣教師の立場でもある政治家達こそ(あるいは、偽りであることを知った上での確信犯・・・)、最も洗脳が解けにくいという現実は、日本国民にとりましては、内外両面における重大な脅威なのではないかと思うのです。