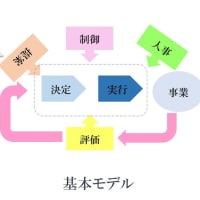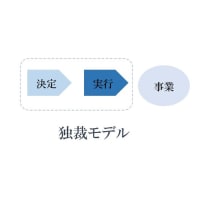イスラエル・ハマス戦争を引き起こしたネタニヤフ首相は、明白なる国際法違反であることを知りながら、あくまでも大イスラエル主義を貫く模様です。犯罪国家の汚名をものともせず、自らの“理想”を求めて暴走する同首相の背景には、シオニスムを含むユダヤ教原理主義があることは疑い得ません。ネタニヤフ首相にとっては、如何なるイスラエルの蛮行も、カナンの地をユダヤ人に与えた神の言葉の実行に過ぎないのです。同首相は、自らこそ神の忠実なる僕として自負していることでしょう。しかしながら、宗教的信念は、犯罪を合法化することはできるのでしょうか。答えは、否、に決まっています。
宗教に関する教科書的な説明に依れば、同じく一神教であっても、ユダヤ教は、ユダヤ人固有の宗教であり、‘ユダヤ人’という民族的な殻を脱して普遍化したのがキリスト教とされています。その理由は、『旧約聖書』が、あくまでもユダヤ人の歴史に関する記述で占められているからです。このため、同書をよく読みますと、様々な疑問も沸いてきます。例えば、ユダヤ12氏族の祖はアブラハムとされていますが、アブラハム自身は、シュメールのウル出身の人物であり、兄弟達もいます。このことは、当然に、アブラハムを共通の祖先とする部族の他にも、その兄弟達を祖とする人々もあまたの人々のみならず、アブラハムとは血縁関係にはない夥しい数の人々が存在することを意味しています。言い換えますと、基本的には『旧約聖書』は、ユダヤ人限定の聖典であり、普遍的な側面には乏しいのです。この側面については、マックス・ウェーバーの『古代ユダヤ教』に詳しいところです。
なお、『旧約聖書』に人類普遍の価値を見出すとしますと、それは、モーセの十戒を置いて他にないかも知れません。何故ならば、第一条の‘私以外の神を信じてはならない’を除きますと、およそ人類社会の一般的な道徳律―利己的他害行為の禁止―が、神からの命令として列挙されているからです。‘汝殺すなかれ’をはじめとして。もっとも、この普遍的道徳律についても、アブラハムがシュメール出身であったためか、古代メソポタミア文明の法典にも神授の形態で同様の記述が見られ、モーセの十戒がオリジナルではないようです。何れにしましても、それが神から授かった者であれ、何であれ、社会の安寧と人々の安全を護るための道徳律には、普遍性が認められるのです。
仮に、その後、『新約聖書』が現れなければ、『旧約聖書』は、自らの内輪だけで‘唯一の神’を信じるユダヤ人の聖典のままであったかもしれません。しかしながら、上述したようにキリスト教による普遍化は、『旧約聖書』から離脱、あるいは、その否定から始まるのではなく、同書と一体化する形で全世界に向けて布教されます。このため、ユダヤ教とキリスト教が混在するようなケースも見られるようになります。例えば、イベリア半島のマラーノ(ユダヤ教徒)のカトリックへの改宗によるユダヤ人カトリック司祭、とりわけイエズス会士の出現や十戒を基本教義とする太平天国の乱などは、キリスト教にユダヤ教的要素が入り込んでいる事例です。また、今日、アメリカの人口の4分の1を占め、同国最大の宗教団体とされるキリスト教福音派は、「ユダヤ人国家イスラエルは神の意志で建国された」と信じる人々であり、宗教的な信念からイスラエルを支持しています。たとえ、イスラエルが、十戒のみならずキリスト教が唱えてきた博愛主義に反する行為を行なったとしても・・・。
こうした現象は、キリスト教の世界宗教化に伴って、その母体となったユダヤ教の‘唯一神’が聖典の民、少なくともユダヤ教徒とキリスト教徒の共通の神となり、唯一無二の絶対神に昇格したことに起因しています。そして、民族的な神から普遍的な神への変化は、今日、ネタニヤフ首相が世界に向かって‘大イスラエル主義’を唱え、ユダヤ人がアブラハムの子孫をもって‘大ユダヤ主義’を主張する宗教的な根拠ともなっているのです。自らの支配の正当性を神に求める主張は、王権は神聖なる神から君主に与えられたとする絶対王制期の王権神授説にも通じます。
かくして、ユダヤ教並びにキリスト教徒の一部は、『旧約聖書』原理主義に陥っているのですが、これらの宗教の来歴を考えますと、ネタニヤフ首相の同書を根拠とした全パレスチナ支配の主張が、今日の国際社会にあって認められるはずもありません。アブラハムの子孫ではない人類の方が大多数であり、かつ、‘統治権神授説’もそれが通用するのは、せめてユダヤ教徒とキリスト教徒の一部でしかないからです。先ずもって、ネタニヤフ首相をはじめとした急進的なユダヤ人は、大イスラエル主義、並びに、大ユダヤ主義の限界を理解すべきではないかと思うのです。