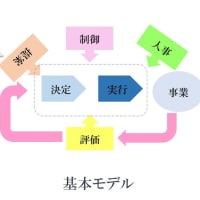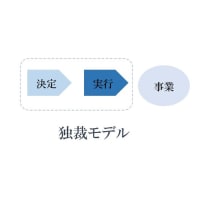自民党のパーティー券に端を発した政治資金の問題は、先の衆議院議員選挙にあって自民党の議席激減の一要因として指摘されたように、多くの国民に政治腐敗の元凶として認識されています。今般の一件では、収支報告書の記載における不正が‘裏金’として咎められたものの、企業・団体献金自体は、政治資金規正法等の法律に従っていれば許されています。このため、先の選挙では、立憲民主党や日本維新の会など、公約に団体献金の全面的な禁止を掲げた政党も現れることとなりました。とは申しますものの、企業・団体献金の禁止については、幾つかの側面から反対意見があります。果たして、これらの反論には、合理性や説得力があるのでしょうか。
今月10日に開かれた衆議院予算員会での石破首相の答弁からしますと、先ずもって、反対論の根拠としては、‘憲法第21条への抵触’が挙げられているようです。石破首相に依れば、企業献金の禁止は、憲法の同条が保障している表現の自由を侵害するというのです。企業による政治献金も、自らの政治的見解を自由に表現したものであるので、これを禁じることは企業の自由の侵害に当たる、とする論理です。
石破首相の同見解は、「禁止に反対するのは参政権侵害に当たると考えるためか」立憲民主党の米山隆一氏の質問に応えたものです。この米山氏の質問から、第二の禁止反対の論拠として、参政権の侵害も指摘されていることが分かります。こちらの方は、企業・団体による政治献金は政治活動の一環であるので、これを禁じることは、政治に参加する権利を侵害することになる、ということなのでしょう。
何れも、憲法違反を根拠とする禁止反対論となり、尤もらしくも聞えます。しかしながら、どこか詭弁のようにも思えるのは、人々の心の中に、公権力をお金で動かすことに対する内なる理性の声とも言える拒否感や懐疑心があるからなのでしょう。何故ならば、お金で公権力を買い取ることができるのであれば、公権力は、極少数の資金力のある人々に私物化され、大多数を占める資金力の無い人の声は、政策に反映されなくかってしまうからです。言い換えますと、民意に応えた政治ではなく、マネー・パワーを有する一部の人々の利益を叶えるための政治に堕してしまい、民主主義に反してしまうのです。
しかも、企業・団体献金の禁止が、これらの表現の自由や参政権を侵害したり、奪ったりするわけでもありません。献金とは、数ある表現手段の一つに過ぎず、請願制度の利用、陳情、要望書の提出など、政府の政策に対する自らの立場や要望を政治の場に届ける手段やルートは他にもあります。否、企業・団体献金の場合には、政治家は、資金を提供する特定の企業や団体の‘声’しか聞かないことになるのですから、むしろ刑罰の対象となる贈収賄に限りなく近い行為ともなりましょう。
企業の参政権侵害の指摘につきましても、企業・団体献金の容認は、政治参加の手段としての‘お金’の授受を公然と認めることを意味します。国民が個人レベルで参政権を行使する場である選挙制度にあっては、一票の格差が常々問題視され、最高裁判所などでも違憲判決が示されています。その一方で、企業・団体献金を集団レベルでの政治参加の手段と見なすならば、平等原則から著しく逸脱してしまうのです。‘見返り’を前提として献金する一部企業・団体のみに‘参政権’を与えることになるのですから。これこそ、憲法違反ともなりかねないのです。
因みに、日経新聞の「私の履歴書」欄にて日本政治の研究で知られるジェラルド・カーティス氏が自らの半生を綴っております。この中で、同氏は、資金力に乏しい一般の人が政治家になるためには、ある程度の献金やお金を受けとるのは仕方がない、との主旨の見解を述べておられました。この側面は、民主主義国家である日米とも変わりはないとしています。カーティス氏の見解は、被選挙権における機会の平等に注目した、もう一つの企業献金擁護論となりましょう。しかしながら、資金力のない政治家が献金を介して資金力のある一部の勢力の意のままに動き、政策を決定してゆくとなりますと、結局は、政治家の傀儡化による一部の‘富裕者のため政治’に至ってしまうのではないでしょうか(一方、国民のニーズは無視され、重税のみが課せられる・・・)。同士の両親は、ゼレンスキー大統領と同じくユダヤ系ウクライナ人なそうですが、腐敗大国であるウクライナの政治体質を是認しているようにも思えます。そしてそれは、今日のグローバリストとも‘世界観’を共有しているのかも知れません。
以上に、企業・団体献金における公権力の私物化問題について述べてきましたが、仮に、政治家自身が、企業の表現の自由や参政権を尊重すべきと考えるならば、政治資金に関する改革のみならず、より公平・平等に企業や国民が意見や要望を表明し得る制度を構築すべきです。政治家がマネー・パワーに取り込まれてしまう現状こそ改善すべきであり、資金力の如何に拘わらずに誰もが政治家となり得、また、政治と企業を含めた国民をむすぶための制度的な工夫が凝らされた、真の意味での民主的な国家を目指すべきではないかと思うのです。