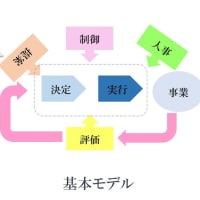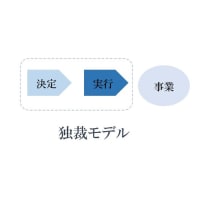民主主義と言えば、とかくに選挙における参政権と凡そ同義に捉えられがちです。かのエイブラハム・リンカーン大統領による「人民の、人民による、人民のための政治」という‘定義’も、民主主義の価値とは、‘人民’が自ら政治を行なうことにある、とするイメージを強めてきました。この民主主義の一般的なイメージは、共和制の連邦国家として誕生したアメリカ合衆国が民主主義の先端的なモデルとなってきたことにもよるのでしょう。しかしながらその一方で、議会制民主主義の歴史的な発展過程を振り返りますと、国民が参政権を得るに至った‘プロセス’を知ることができます。アメリカのように最初から民主主義国家として建国された国は少数であり、大半の諸国は、君主制から民主制への移行プロセスを経て今日に至っているのです。
議会制民主主義発祥の地は、イギリスとされています。もっとも、そもそも封建制度を経験した国や地域では、中世以来、身分制議会などが設けられたケースも多く、イギリスのみに議会が設置されていたわけではありません。中世の封建制度にあっては、封建契約を交わした主君と家臣の間で統治の諸権限が分散しているため、国王と雖も有力諸侯達のパワーは侮れなかったのです(このため、常々内乱や王朝交代が発生しやすい・・・)。イギリスにありまして議会が国政の中心機関となり得たのも(最も、イギリスの議会主権は、国王が臨席する議会を意味する・・・)、有力諸侯達が議会を国王に対する自らの抵抗の‘砦’としたところにあります。
1215年に成立した『マグナ・カルタ』は、イギリスの民主主義の起源ともされる国政上の重要な文書ですが(不成典憲法の国であるイギリスでは、今日でも、憲法的な役割を維持している・・・)、同文書にあって特に注目されるのは、議会の課税同意見です。そもそも『マグナ・カルタ』とは、ジョン失地王による一方的な諸侯に対する軍役や課税に起因する諸侯層の反乱に際しての‘和平合意’として作成されたのですが、その第12条にあって、国王は、議会(common counsel)に対して楯金や援助金を課す権限を認めています(この他にも、車馬や材木の挑発にも本人の同意を要するとしている・・・)。以後、紆余曲折がありながらも、イギリスの議会は、財政に関する権限を獲得してゆくのです。
同プロセスにあって重要な点は、課税、すなわち、為政者や政府が国民に負担を求める場合には、国民の合意を要するとする民主主義の価値の一面です。参政権をもって民主主義の実現とみる今日では、政治家自身が国民から選ばれた‘国民の代表’とするスタンスにあるため、むしろ、国民の課税同意見が忘却されがちです。実際に、先週の12月27日に、日本国政府は来年度の予算案を閣議決定していますが、過去最大の115兆円規模に膨れ上がっています。物価高の折、税収も3兆円の伸びを見せており、こちらの額も過去最高というのです。
ところが、日本国政府には、減税という発想は皆無のようです。「103万円の壁」についても、国民民主党が求めた178万円からは大幅に引き下げられ、与党案通りに「123万円」止まりとなりました。減税策は、基礎控除枠の拡大に限ったわけではないのですが、仮に、先の衆議院議員選挙にあって与党側が少数与党に転落しなければ、国民にはさらなる増税が待ち受けていたかも知れません。何れにしましても、日本国は、民主主義国家でありながら、かくも政府は国民負担に対して無神経で冷淡なのです。‘生かさぬよう、殺さぬよう’という江戸時代の言葉が現代に蘇っているかのようなのです。
先の衆議院議員選挙では、国民民主党の「103万円の壁」が一石を投じることとなり、政府も、与党の座を維持するために増税路線を軌道修正せざるを得なくなりました。この点、選挙が一定の効果を示した事例ともなるのですが、民主主義が普通選挙と同一視されている現状では、‘国民の代表(国会)の合意による予算案の成立’という建前の下で、政府による国民の合意なき一方的な課税という、強制徴収的な手法がむしろまかり通ってしまいます。そもそも、115兆円規模の予算が真に必要なのか、あるいは、負担者である国民に受益として還元されているのか、今一度、歳出について国民視点からの検証を加えるべきですし、政府による課税については、負担者である国民の事前合意を基本原則とすべきと言えましょう。
国民の財政に関するコンセンサスの形成については、今後、国民投票制度の導入と言った制度的な工夫を要しましょうが、現状にありましても、衆参何れであれ、各政党や立候補者に対して、増税案を含む税制に関する政策を公約の必須項目として記載を義務付けるべきなのではないでしょうか。普通選挙の実施は民主主義の入り口に過ぎず、国民が課税同意権を実際に行使し得る制度の構築こそ、政府の‘国民搾取体質’を是正し、財政民主主義を実現する道なのではないかと思うのです。