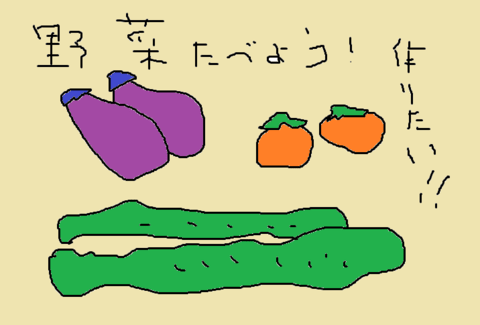
文春文庫の「散歩とカツ丼」(2013)というのも読んでいます。途切れ途切れではあるんですけど。
その中で、ああ、そうなんだなと思った文章に付箋をつけておきました。
漬物が家庭の幸福感と深く関わっていることを感じたのは、離婚寸前の頃だった。私は、崩壊しつつある夫婦なら誰でも感じる不安のなかで夕食の支度をしていた。残り物の野菜に塩をふってぎゅっと絞り、即席の浅漬けを作った。
それに箸をつけながら相手が言った。
「いつも浅漬けばかりだな。どうして糠漬けにしないんだ?」
夫婦が危機にあるときにどうしてできよう。私は心の中で叫んだ。
そうだったんだ。ぬか漬けが食べられるということは、まだどうにか関係はつながっていることなのかと、感心するところがありました。少し怖かった。

浅漬けなら気まぐれでできるが、糠漬けはちがう。作ったら最後、途中でやめることができない。日々の手入れを怠れば、たちまちカビがわいて修復困難となる。心の平穏があってこそ継続できる。結婚生活を象徴するような漬物なのである。
糠漬けにかぎらず、漬物の味は塩加減もさることながら、作り手の「幸福加減」で良しあしが決まる。
エッセイストの植松さんが断言するのは、このあとにものすごく幸福な漬物の場面が描かれるからで、こんな圧倒的なしあわせ加減というものがあるんですよ、という、どちらかというと、後半が目玉のエッセイなんですけど、私はこの単純な事実、漬物は、その家の幸福感によって生み出されるものなのだ、というのは発見でした。
私も、漬物作れたらいいんだけど、それは無理ですね。白菜漬け買ってきて、桃屋のキムチの素をまぶすくらいしかできないな。今はそんなことさえしていません。まあ、それはもう、ありがたいことでした。私は幸せです。奥さんは幸せなんだろうか。どうなんだろうな。



















