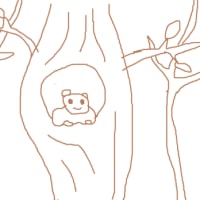今から三十年前、いつも使っていた大阪環状線・桜ノ宮駅。そんなに大きなターミナル駅ではなくて、川沿いで、そこから天神祭りに行けたり、淀川沿いの公園はいろいろだったり、高校の時の友人がいたりする、そんな駅がありました。大阪駅から見たら、その次は京橋で繁華街のある、京阪電車の走っている大きな駅の手前の、でも、近年リバーサイド高層住宅が次から次と立ち続けている、不動産関係の人には注目の街があります。
桜ノ宮駅とその近辺の説明を一生懸命していますが、そこで何があったんでしょう?
今から三十年前の冬の朝、桜宮で下りた私は、何かゴミを持っていて、そのころには設置されていた駅のゴミ箱に捨てようと思い立ちました。開いている部分から投げ入れたらいいのだけれど、ついつい余計なことをしてしまい、勢いをつけて投げようとタイミングと頃合いにばかり気を取られていました。
さあ、ゴミをポイとアンダースローで投げました。入りました。ガヅーン! キラキラキラ
何が起こったのでしょう。
桜ノ宮駅は、ホームは狭いし、鉄骨がむき出して屋根を支えています。下ばかり向いていた私は、ゴミ箱は見えていたけれど、ホームの壁側にあるむき出しの鉄骨が見えていなくて、投げたと同時に頭をぶつけたのでした。
頭をぶつけただけなら、イテッ、で済みました。でも、ぶつけると同時に、頭は歯を押さえつけることになり、上の前歯が下の前歯に強く瞬間的にぶつかったようです。そして、下の前歯は欠けてしまった。
一瞬の出来事だったので、何が起こったのかわかりませんでしたが、カリッと欠けた下の歯が口の中に残ったので、しばらくしたら歯がどうにかなったらしい、というのに気づいたわけです。
歯のトラブルは、突然にやってきて、すべてを一変させてしまいます。私は何度虫歯に詰められている金属をキャラメルで取られたでしょう。もう何度も何度も経験しています。近年はキャラメルだけではなく、ガムを食べただけで虫歯に詰めたものは取られてしまうので、もうガムも食べられなくなりました。
ホントに、情けないことだけど、暗い一日を過ごし、帰りも桜ノ宮から環状線に乗り、あそこで歯が欠けたんだと現場をしみじみ眺めたんだったかな。
いつもながらトホホの昔話、前にも書いたのかもしれない。それがどうしたんだろう。

そうでした。姨捨の話の続きを書かなくちゃ! 「大和物語」からの引用でした。おばあさんを息子は捨ててしまった。おばあさんは、山の中に置いてきぼりにされて、ついつい声を出しています。
「やや。」
と言へど、いらへもせで、逃げて家に来て思ひをるに、言ひ腹立てけるをりは、腹立ちてかくしつれど、年ごろ親のごと養ひつつ相添ひにければ、いと悲しくおぼえけり。
おばあさんが「これこれ」と声を掛けましたが、息子はズンズン遠ざかっていきます。でも、家に帰れば、妻にあれこれとおばあさんの悪口を聞かされた時には、「いいかげんにしてくれよ」とかなんとか、ついつい妻の話にのっかってしまったけれど、改めて考えてみれば、やはり育ての親である人を寂しい山の奥に放置した自分が許せなくなりました。さあ、どうしましょう。

この山の上より、月もいと限りなく明かく出でたるをながめて、夜一夜、寝も寝られず、悲しうおぼえければ、かく詠みたりける。
ふと空を見上げると、おばあさんを残した山の方から月が出てきたそうです。ということは、家の東側に山があったわけですね。何だかてっきり西側に山があるような気がしていたんですが、東の山から明るい月が出てきた。
もうそうなると、眠れません。気になることとお月さまをじっと対峙して、どうしたらいいのかずっと煩悶しなくてはならないのです。そして、昔の日本人は歌を詠んだそうです。それで解決するわけじゃないけれど、歌で自分に力を与えなくてはならない気分を持っていたんです。
わが心なぐさめかねつ更級(さらしな)や姨捨山(おばすてやま)に照る月を見て
私の心はもう居ても立っても居られないのです。いつまで経っても自分の声が聞こえる。「さあ、どうすればいいんだ。お前はそれで幸せか。お前のお母さんは、寒い山の奥でどうなるというんだ。」
そういう心の声を聞いて、姨捨山に光り輝く月を見ているのです。お母さんは寒くないだろうか、どうしているんだろう。そんなことがいつまでも私の心の中を渦巻いています。
と詠みてなむ、また行きて迎へ持て来にける。それよりのちなむ、姨捨山と言ひける。なぐさめがたしとは、これが由になむありける。
そういう歌を詠んだ男は、山の奥に向かい、おばあさんを迎えに行ったのでした。それから後、この山を姨捨山と名付け、人の心は落ち着かないことがあると、もういてもたってもいられなくなる、そういう風に言い伝えたそうですが、こうしたお話があったからでした。
ということを、昨夜ラジオで聞いたんでした。

そういえば、今村昌平さんが監督した「楢山節考」(1983松竹)は、カンヌでパルムドール賞を取ったそうで、私も直後に映画館に見に行きましたが、そのまんまにしか見えなかった。主演のおばあさん役・坂本スミ子さんが自らを捨ててもらうために、自らの前歯を砕いてしまう場面が、予告編でも取り上げられたりして、衝撃を受けたことがありましたが、見た感想は、そのまんま、お年寄りが捨てられていく話で、希望が見つからなかった。
今村昌平さんが57歳くらいでこの作品にチャレンジしている。どういう意味があったんだろう。
もともと今村昌平さんの映画って、見終わっても救いが見つからない、暗い気分が沈殿してしまうことが多かったんだけど、それをどうしてヨーロッパの人たちが評価するのか、三十五年前の私には、ただの異国情緒趣味で賞を与えたと思うしかありませんでした。

そもそも「楢山節考」とは、姨捨伝説に乗っかり、深沢七郎さんが43歳ころに書いた作品で、1957年に中央公論社から本が出ているそうです。翌年には木下恵介さんという大監督が田中絹代さんを主役にして映画化をしている。この時木下恵介さんは46歳だったそうです。
みんな中年のオッサンで、そういう人たちが、母性をテーマにした作品に取り組んでいる。
今村昌平さんは、少し遅かったけれど、自らがお年寄りに近づく前に、まず父母が年を取っていく。その姿を見て、「こんな親なんて、何だか荷厄介だな」と思う時があったのかもしれない。
「いっそのこと、どこか自分たちの知らない世界でのびのび暮らしてくれたらいいのに」などという虫のいいこと、身勝手なことを考える時もあったかもしれない。
そんなことを思った後、本当にそれでいいのかと思い直し、ふたたび父母と新たに向き合うこと、自らが年を取ることを前に、まず人は自らの親で考えていく、それを昔も今もみんなが経験し、何度も同じ道を通っていく、それは日本でも欧州でも同じで、答えはないけど、みんなでのんびりいつまでも一緒に暮らせたらいいのに、という漠然とした方向だけが見えてくるのでした。