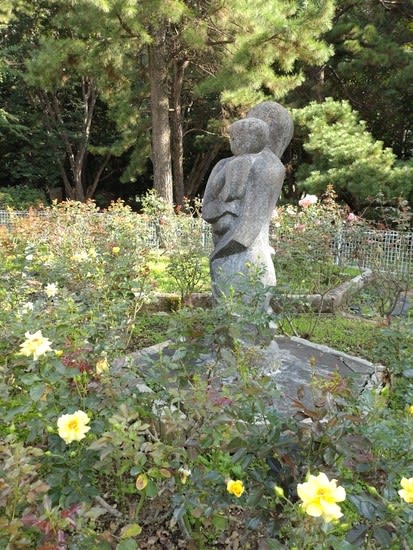昨日は東御苑の秋に咲くサクラを先にアップしてしまいましたが
今日は新雑木林を歩いた時に見た花や実を・・・
入ってすぐにある七草のコーナーではもうほとんど終わっていて、
「フジバカマ」(藤袴)が残っている位でした。
今日は新雑木林を歩いた時に見た花や実を・・・
入ってすぐにある七草のコーナーではもうほとんど終わっていて、
「フジバカマ」(藤袴)が残っている位でした。

七草の中にははいらないのですが「ナンテンハギ」(南天萩)
別名「フタバハギ」(双葉萩)が咲いていました。
別名「フタバハギ」(双葉萩)が咲いていました。

新雑木林の中には小さな流れがありその両脇に散策路があります。

この流れのそばでなかったのですが「シモバシラ」(霜柱)の花が見られました。


「ウド」(独活)がもう花が終わり、実が出来ていて
それも熟して濃紫色になっていました。
それも熟して濃紫色になっていました。

「ヤマホトトギス」(山杜鵑)が咲いているのが見られました。

新雑木林の中の大好きな散策路、ここに「オトコヨウゾメ」(男ヨウゾメ)や「マユミ」の実がみられます。

「オトコヨウゾメ」花は『小さくて白い可愛い花』です。


「マユミ」(真弓)の実はたった一つだけ残っていました。

他に見られた実は「ガマズミ」(鎌酢実)

「ミヤマガマズミ」(深山鎌酢実)

新雑木林を二の丸庭園の方に出たところでは「センニンソウ」(仙人草)が
見られましたがまだ髭のように見える綿毛がでていませんでした。
見られましたがまだ髭のように見える綿毛がでていませんでした。

「ノイバラ」(野茨)の赤い実が雑木林の中で趣きがあり素敵でした。

林の端では「ノコンギク」(野紺菊)が咲いていて、この後に行った
二の丸雑木林でも多く見られました。
二の丸雑木林でも多く見られました。

撮影日 2021年 10月16日