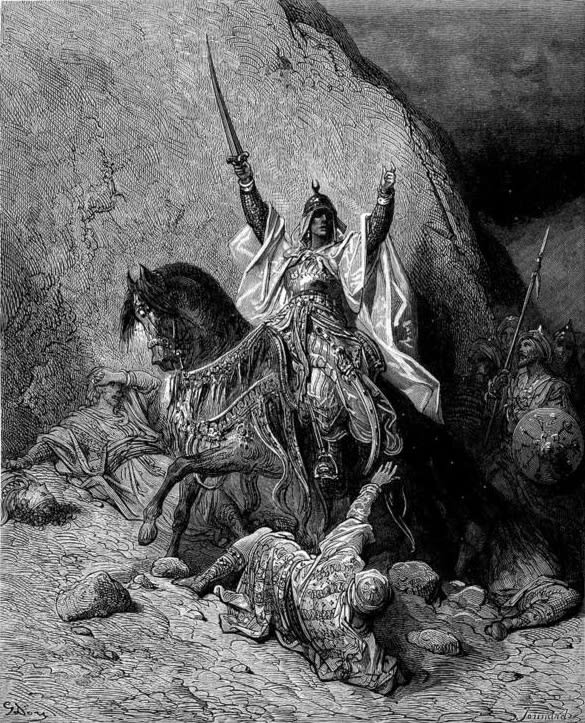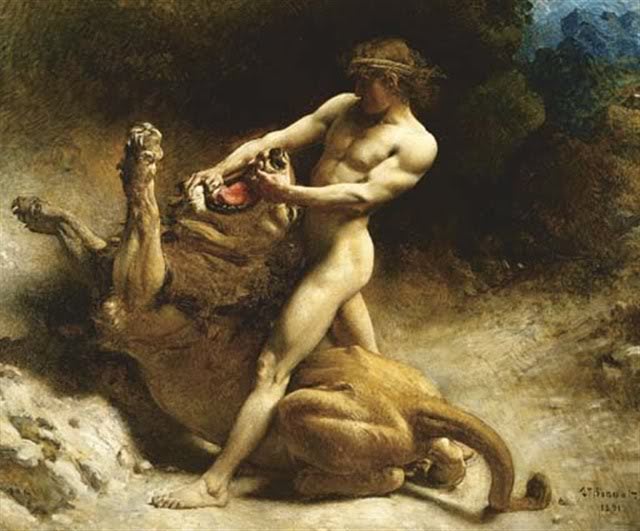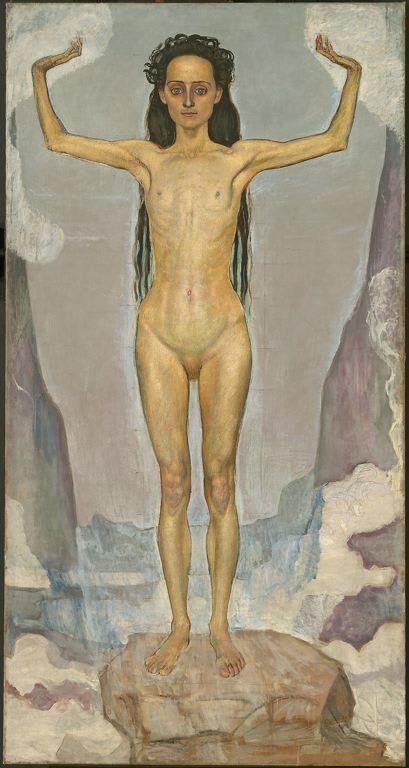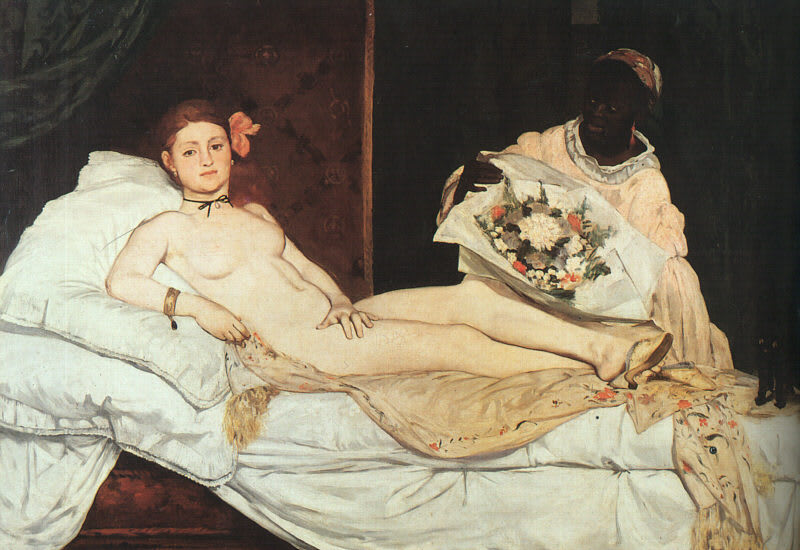No,135
ジョヴァンニ・ベッリーニ、「聖母子」、15世紀イタリア、盛期ルネサンス。
好きな画家のひとりなんだが、この聖母は女性ではないね。実に美しいが、これは聖女というより、男だよ。
男の、実に清らかな聖者の位に達したものを、女性に変換して描いたという感じだ。だから、美しいが、まるで女性らしさを感じない。ヴェールをとっても、長い髪はそこにない。たぶん、男のような短髪がある。
メッシーナの聖母などには、厚いヴェールの奥に、女性らしい匂やかな長い髪を無理やり隠しているような風情があったが、この絵の女性には、始めからその気配がない。
決して生むはずのない女性に、子供を与えているためか、まるで幼子イエスは教会の生誕劇に使う人形のようだね。
たぶん、ベッリーニは、身近に、聖母のモデルとできるような女性を見いだせなかったんだろう。ゆえに、ときに美しさを感じさせる、静謐な男を、女性に変えて聖母にしたのだ。
まあ、画家は、自分が美しいと感じるものしか描けないからなのである。彼が描くマグダラのマリアなども、美しく波打つ金髪を描きながらも、どこか色っぽさを感じないね。
淫らというのではなく、男も女も、女性を見ると、情感の表面が荒く揺れるような感覚を感じるものだ。要するに、動的になる。だがこの女性を見ても、情感は揺れない。まるで石のように静かだ。
つまりは、男だからだよ。
男を女にすると、こういうものになるという、一つの例かもしれないね。
ジョヴァンニ・ベッリーニ、「聖母子」、15世紀イタリア、盛期ルネサンス。
好きな画家のひとりなんだが、この聖母は女性ではないね。実に美しいが、これは聖女というより、男だよ。
男の、実に清らかな聖者の位に達したものを、女性に変換して描いたという感じだ。だから、美しいが、まるで女性らしさを感じない。ヴェールをとっても、長い髪はそこにない。たぶん、男のような短髪がある。
メッシーナの聖母などには、厚いヴェールの奥に、女性らしい匂やかな長い髪を無理やり隠しているような風情があったが、この絵の女性には、始めからその気配がない。
決して生むはずのない女性に、子供を与えているためか、まるで幼子イエスは教会の生誕劇に使う人形のようだね。
たぶん、ベッリーニは、身近に、聖母のモデルとできるような女性を見いだせなかったんだろう。ゆえに、ときに美しさを感じさせる、静謐な男を、女性に変えて聖母にしたのだ。
まあ、画家は、自分が美しいと感じるものしか描けないからなのである。彼が描くマグダラのマリアなども、美しく波打つ金髪を描きながらも、どこか色っぽさを感じないね。
淫らというのではなく、男も女も、女性を見ると、情感の表面が荒く揺れるような感覚を感じるものだ。要するに、動的になる。だがこの女性を見ても、情感は揺れない。まるで石のように静かだ。
つまりは、男だからだよ。
男を女にすると、こういうものになるという、一つの例かもしれないね。