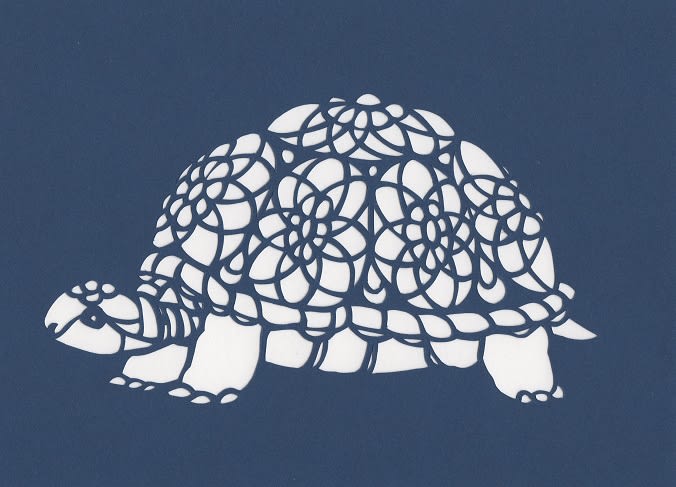昔、ある所に、かろてなの原という、とても美しい国がありました。
そこに住む人々は、みな穏やかで優しく、土地を守る優しい鎮守の神を、とても大事に、敬っておりました。かろてなの原を守れる神様は、カロマと、フツという名の、二柱の神様でありました。
フツの神様は、真珠の柱のように美しくたくましい、青年の神でありました。知恵深く、力あり、かろてなの人々には特に篤く慕われておりました。
しかしカロマの神様は、フツの神様の母神様でありましたが、とてもそうとは思えないほど醜いご様子をなさっておりました。全身を猿のような毛で覆われ、顔は齢を重ねすぎてひしゃげてしまった亀のように平たくしわくちゃで、手足は黒く枯れ枝のようでした。そしていつも、垢まみれの衣をずるずるとひきずりながら、珍妙な歌を歌いつつ、山河をはいつくばるように歩き回っているのでした。
だからフツの神様は、カロマの神様をとても嫌っておりました。実の母とは言え、かくも醜く、知恵もそう高くなく、することと言えば、毎日国中を意味もなく歩き回って、森の中に迷い込んだ人を驚かしたり、遊んでいる子供たちの中にいつの間にかまじりこんで、親たちから菓子をせしめたりするだけなのです。この神が、自分といっしょにこの国を治めているのだということが、フツの神様には、何とも合点がゆかぬことなのでした。
「実質的な仕事は、すべてわたしがやっているというのに、この方がここにいることに、何か意味があるというのだろうか? 天の大神様は何を考えておられるのだろう?」
フツの神様は疑問に思い、一度カロマの神様に、尋ねてみられました。
「母上様、あなたは、この国で、いったい何をなさっていくおつもりですか?」
するとカロマの神様は、もじゃもじゃの髪の毛の間から、いかにも哀れをそそる瞳で、フツの神様をじっとごらんになり、しゃがれ声でおっしゃいました。
「わたしはおまえの母だから、おまえのためにここにいたいのだ」
「わたしももう一人前ですから、一人でやってゆけますよ」
「でもおまえ、わたしはおまえの根であるから。おまえを支えてやりたいのだ」
「種はいつしか古い根を離れるものです」
「でも、わたしはここにいたいのだよ。おまえが病んだ時、すぐに手当てが間に合うように」
「わたしはこのとおり健康で美しいのです。ご心配なさらずとも、大丈夫ですよ」
「でもおまえ……」
カロマの神様が、なおも食い下がろうとするので、フツの神様はがまんがならずに、とうとう言ってしまわれました。
「実は先程、天の大神様からお達しがあったのです。かろてなの原は、これからフツのみが治めるようにと」
すると、カロマの神様は、瞬間、哀愁のたまった目をありありと広げられ、何かをいいたげに口を開きかけました。しかし何もおっしゃることなく、そのかわりに悲しげなため息をつかれました。そして、のろのろときびすを返すと、そのまま、とぼとぼとどこかへ去ってゆかれました。
「やれやれ、これでさっぱりした。これからこの国は、わたしの理想通りに、豊かに美しく成ってゆくことだろう」
カロマの神様のお姿が、山の向こうに消えてしまうと、フツの神様、安心したようにひとりごちました。そして、ご自分のお住まいである、かろてなの神殿へと帰るられました。
しかし、神様が神殿の御座の前に来られると、なんとそこには、すでに他の神様が座っておられました。フツの神様は驚いて、思わず「あなたはだれだ」とおっしゃいました。すると相手はニヤリと笑ってこう答えました。
「わたしはフツの神である」
「何をいう。フツはわたしだ。おまえはだれだ。嘘を言うのは、神ではないぞ」
「おまえは嘘を言ったではないか」
相手は、平然と、言いました。フツの神様は、はっと、言葉を飲みました。確かに、カロマの神を追いはらわんと、大神さまの名を語ってまで言ったことは、すべて嘘だったのです。相手は御座にふんぞりかえりながら、あざ笑うように言いました。
「……知らなかったのか。神が嘘を言えば、嘘が神になるのだ。わたしはおまえの言った嘘であり、今やおまえ自身でもあるのだ。そしておまえは抜け殻。もはや神でもなんでもなく、何の力もなく、ただ消えゆくしかない夢の影なのだ」
フツの神様は、震えながら、嘘の神を見上げました。確かに、その神様は、姿も声も、フツの神様と瓜二つでありました。ただ向背を満たす光ばかりが、妙にぎらぎらとしてあやしく、そのほほ笑みは優しげにも見えましたが、瞳の中には温みと偽った冷気が、近寄るものを傷つけようと待ち構える氷の刃のように、冷厳と居座っているのでした。嘘の神はゆっくりと立ち上がると、言い放ちました。
「これからはわたしがフツの神である。おまえは永遠にそこに座っているがよい」
するとフツの神様は、空気を抜かれるように見る間にしぼみ、神殿の隅の石壁に、染みのようにはりついてしまいました。
「ばかなやつめ」
嘘の神は、壁の染みとなったフツの神を指さし、長々とあざ笑いました。フツの神は何とか抗おうとしましたが、もう動こうにも動けませんでした。
さて、それからというもの、嘘の神はフツの神を名乗り、したい放題のことをしました。
「欲しいものは他人から奪え」
「女子と子供は卑しいから、いらなくなれば捨てればよい」
「他の国の者は蛮族であるから、殺してもかまわない。これらは神のお告げである」
彼は人間に、次々と嘘を吹き込みました。人間は、最初のうちは首をかしげていましたが、ほかならぬ神様のおっしゃることであるからと、最初は戸惑いながら、後はおおいに喜んで言うとおりの行いをしました。もちろん中には神に疑問をたてる人間もいましたが、そういう人間は、嘘の神が殺したり、追放したりして、ノミをつぶすようにていねいに除いていきました。そうして、美しく穏やかであったかろてなの人々は、次第にその質を、凶暴で、冷酷なものとしてゆき、他国の人々から人面の獣とまでさげすまれるほどになってゆきました。嘘の神の嘘は、際限を知らずに大きくなってゆき、やがて自分は世界を作った最も偉大なる神であるとまでいうようになっていきました。そして人々は、嘘の神の言葉だとも知らず、その言葉を信じ、ますます魔の境涯に深く沈んで行き、世界に嘘と悲しみを広げてゆくのでした。
「なんということだろう。……ああ、どうすればいいのだ……」
神殿の廃墟の隅にはいつくばりながら、フツの神様には、ただ悲しむことしかできませんでした。フツの神様は、何とかして、人々に正しいことを教えようとしたのですが、その声はだれの耳にも届きませんでした。嘘を口にしてからというもの、フツの神のその声は細く力なく、人間たちの耳はそれをとらえることができないのです。自分が何げなく口にした嘘が、このような結果を招こうとは……。フツの神には悔んでも悔やみきれず、ただ神殿の隅で毎日のように魂も溶けんばかりに泣き暮らすばかりでした。
「ああ、これも、母を追い出そうとした報いに違いない。母上、ばかな息子をお許しください。かなうことなら、もう一度お会いしたい。そしてこの重い悔いを伝えたい……」
フツの神は涙ながらにおっしゃいました。すると、そのとき、みょうに目の前が明るくなりました。フツの神様が顔をお上げになると、そこには、白い衣を纏われた、ふくよかで春の花のようにお美しい女神様が、立っておられたのです。お顔のまわりには虹のように穏やかな光が満ち、全てを知っているような静かな微笑みがお口元に宿っておられます。見たことのない女神様でありましたが、そのフツの神様を見つめる優しい瞳を見て、フツの神様には一目でお分かりになりました。
「ああ母上……帰って来てくださったのですね」
フツの神はひざまずくと、今までの自分の過ちをすべて告白され、深いざんげのお気持ちを告げられました。
「すべてはわたしがいけないのです。わたしの言った小さな嘘が、こんなにまで人々に苦しみと過ちをもたらしてしまうとは……」
すると女神さまは、やさいくおっしゃいました。
「今からでも間に合いましょう。さあ、いっしょにおいでなさい」
「どこへ?」
怒りを覚悟していたフツの神は、その優しいお言葉がにわかに信じられず、思わず顔をあげられました。
「魔の国へ赴いた人間たちを、追いかけるのです」
「しかし、一度ついた嘘は、取り返しはつきません。それに彼らはもうはるか遠くに行ってしまいました」
「わたくしは、足はのろのろとしておりますが、大事なことに遅れたことは一度もないのです。ほら、こうして、おまえを手当てすることにも、間に合ったでしょう」
女神はそうおっしゃると、フツの神様のこうべをやさしくなでられました。すると、フツの神のお体が、はりついていた壁からすっと外れました。しかしまだ、歩くことはできません。女神はフツの神を背負われますと、昔と変わらぬのろのろとした足取りで歩きだしました。
「さあいきましょう。わたくしたちは神。決して人々を、あきらめてはなりません」
「母上……」
カロマの神の暖かな背中の上で、フツの神は赤子のように涙を流されました。そして母神様のお気持ちも、天の大神様のお気持ちも、全てがわかったように思われました。
「あきらめては、なりません……」
そうして、フツの神と、カロマの神は、遠く離れてしまったかろてなの人々を追いかけて、今も歩いているのです。この世の終わりになる前に、もう一度めぐり会い、過ちをとりかえすために。
今も、黙々と、人々を追いかけているのです。
(おわり)
(2001年7月発行、同人誌ちこり22号所収)