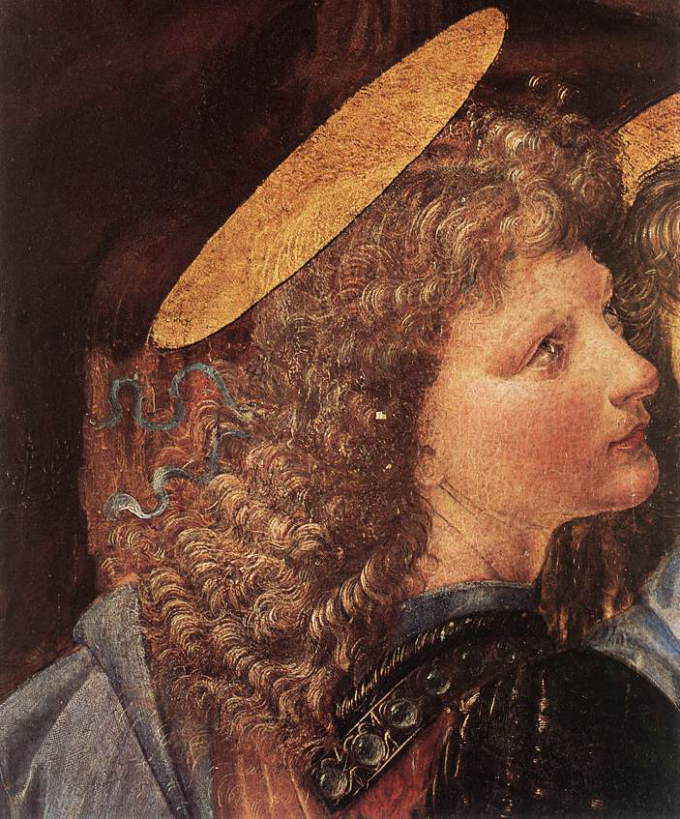連続性の夢、というのを見たことがありますか。連続ドラマのように、同じテーマが何度も続く夢。
それは私が大学を卒業し、社会に出て初めて大きな壁にぶつかった頃のこと。私は、幼稚園に行っている夢を見ました。それも、おかしいな、確か私はこの前大学を卒業したはずなのに、なんでまた幼稚園なんかにいるんだろ?と疑問に思いながら、席についているのです。
その何年か後、今度は小学校に通っている夢を見ました。同じように、確か私は大学を卒業したはず……と疑問に思いながら、小学生たちと並んで授業を受けているのです。こんな夢を、私は何年かおきに見ました。しかもそのたびに、中学生になり、高校生になり、大学生になり、だんだん成長していくのですが、毎回、おかしいな、確か私は……といつも疑問に思っているのでした。
そして、数年前に、ようやく夢の中で大学を卒業し、目が覚めた私は、ああ、きっとこれでこの連載夢物語も終わりかな、と思っていたのです。そうしたら、半年ほど前のこと、今度はなんと、新米教師としてバスで通勤する夢を見たのです! 確かにわたしは教育学部を出ましたが……。おいおい、まだ続くの?と目を覚ましてから思いました。
最初の幼稚園の夢から、18年経っていましたから、私は、社会に出てから、夢の中で、現実で学校に行く年月とほぼ同じ年月をかけて、夢の学校課程を終えたことになります。そして、教師として出勤する夢を見た頃は、現実ではちょうど、私が、自分の人生で為すべきことを確信できた頃でした。
学校を卒業しても、そこで勉強が終わりなのではないのですね。そこから、魂の教育のために、本当の学校が始まるんだ。そんなことを夢に教わった気がしました。
(2005年7月ちこり34号、コラム)