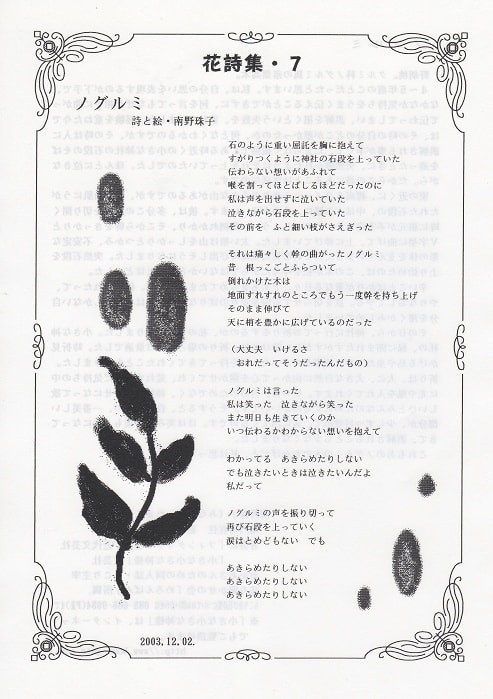明けていく東の空から射す光が、公園の木立の間をつらぬいて、あの奇妙な立札を照らした。わたしは、胸を冷たい水でふさがれたような、重い気持ちでそれを見た。今日もまた、一日が始まってしまったのだ。
わたしの残り少ない所持金は、それから二日のうちに、すべてなくなってしまった。しかしわたしにはもう、仕事を探して歩くような気力はなかった。昼の間は、公園の隅の灌木の影に隠れるように座って、公園を通る人々から身を隠した。時々、ハンバーガーの袋や弁当の箱をゴミ箱に捨てる人がいたときなどは、思わず、喉がごくりと動いた。
あたりがすっかり暗くなり、人気がなくなると、わたしは野良猫のようにあたりをうかがいながらゴミ箱の中に顔をつっこんだ。そして昼間に目星をつけておいた寿司屋のビニール袋を見つけて、中を探った。ネタがとれてシャリだけになったすしが二つ、まだ箱の中に残っていた。わたしは犬のようにそれに食いついた。ふたにへばりついていた飯粒をなめとり、ガリまで口に放り込んでばりばりと食べた。食べている間は何も考えなかったが、いつの間にか、わたしは泣いていた。熱いものが喉をのぼって、涙と鼻水が混じったものが鼻先からぽたぽたと弁当箱に落ちた。
(どうにかしなきゃ……)
わたしは、ベンチに寝転がって空を見ながら、思った。だが、一体、どうすればいいのか。考えようとすると、空がしんと冷たく澄んで、わたしのうす汚れたプライドをぎりぎりと締め付け、暗い奈落へ突き落そうとする。
(どうしようもないじゃないか)
この期に及んで、まだもがこうとしている自分に、わたしは嫌悪を感じたが、それは自分の馬鹿さ加減がわかっているからではなかった。ただ、少しの間でも、深刻な問題から逃げていたかった。何もかもがじぶんのせいなのだと認める一歩手前で、わたしの思考はうじうじと逃げ道を探っているのだ。
目を閉じると、わたしの思考はわたしの来し方へと流れた。
今から一年ほど前、わたしは勤めていたある大手の企業を辞めた。原因は、ささいな人間関係の摩擦だった。
子供の頃から、優等生として両親や教師にちやほやされて育ったわたしは、社会に出たら、プライドばかりが肥大した箸にも棒にもかからぬ人間になっていた。まわりの人間がみんな馬鹿に見え、仕事を覚えようともせず、自分ほど頭のいい人間はいないという顔をして、いばっていた。ちょっと気に入らないことがあると、すぐに他人と衝突し、物議を醸しだした。人の立場や心を思いやることなど一切なく、うまくいかないのは何もかも他人のせいだと思っていた。
そうこうしているうちに、わたしは次第に同僚たちに排除されるようになった。大事な会議や社員の親睦会なども、わたしを外して行われるようになった。後でわたしが抗議すると、「こんな馬鹿馬鹿しいことにエリートの君は関わらなくていいんじゃないの」などと、皮肉たっぷりな言葉が返ってきた。周囲を見回しても、わたしに味方するものはだれ一人いなかった。わたしは、自分のまわりにいつの間にか冷たい壁ができていることを知り、愕然とした。しかし、それでも、わたしは自分の落ち度を認めなかった。間もなく、わたしは上司に辞表をたたきつけた。だれもとめる者はいなかった。
粋がって辞めてはみたものの、現実の生活はすぐにわたしの肩にのしかかってきた。わたしを信頼しきっている故郷の両親には、仕事を辞めたことはできるだけ知られたくない。とにかく、生活費を稼ぐために、わたしは少ない知り合いのツテをたよって、ある大手の予備校の講師をした。しかし、そこも長くは続かなかった。
そこには、わたしと同じように、大学は出たものの、人間関係で挫折して会社をやめ、講師をしている人間が数人いた。わたしは、ヘドが出るほど、彼らを嫌悪した。彼らのプライドを支えているものは、ただ一つ、学歴だけだった。彼らは、日差しに溶かされてアスファルトにべっとりと貼りついた飴玉のように、世間にも、自分にも、甘えていた。彼らは毎日、学校や予備校で得た知識を並べては自分が知的に優れていることを誇示しようとしていたが、それは、受験勉強以外のことをしたことがない人間が、子供が必死に親に取りすがるように、受験勉強という島に取りすがっているだけに過ぎなかった。彼らの存在を支えているのは、受験勉強だけなのだ。そして、わたし自身も、紛れもない彼らの同類なのだ。わたしはようやく、うすうすとそのことに気づき始めた。予備校の講師という仕事が、結局わたしにのこされたただ一つの似合いの場所だったのだろうか。しかしわたしにはそれが耐えられなかった。
予備校の講師を辞めたわたしは、それからこうして宿無しに成り下がるまで、アパートにこもってほとんど外に出ずに過ごした。もう、未来も、人生に対する希望も、何もかもがわたしを取り残してどこかに消えてしまっていた。自己嫌悪と、劣等感と、両親や教師に対する根深い憎しみだけが、わたしの心を満たしていた。わたしは孤独だった。だれも、わたしに手をさしのべてくれる人はいなかった。わたし自身でさえ、わたしを見離そうとしていた。
わたしは、ベンチに横たわって空を見ながら、いつしか唇を曲げて声もなく笑っていた。何に対して笑っているのか、わからなかったが、笑うという行動は、不思議に今のわたしの心を幾分軽くする作用をもたらした。わたしは、一つ息をつくと、窮屈そうに体をよじらせて寝返りをうった。するとわたしの目に、あの立札が入った。
(水面……)
わたしの脳裏で、再びなにかが動いた。わたしは頭を起こした。遠い昔にセットされたタイマーが、何かの拍子にはっと目覚めたかのように、わたしの奥で、何かがぎりぎりと音をたてて回り始めた。
(洋子……)
不意に、眉間がばちっと弾けた。それと同時に、色の白い、愛らしい瞳をした少女の顔が、ありありと脳裏に浮かんだ。だが、それが誰なのか、まだわたしにははっきりとは思い出せなかった。風もないのにどこかでこずえが騒いで、わたしは何げなく上を見上げた。そして目を疑った。トラックのように巨大な海ガメが、ゆるゆると手足を動かしながら、上空を泳いでいた。
わたしの口から、ちいさな悲鳴がもれた。すると、それに気がついたのか、海ガメは、ゆっくりと首を曲げて、わたしを見た。海ガメは、わたしの目の奥の奥まで見通すような深い静かな眼差しでわたしを見下ろすと、ゆっくりと、口を動かした。その声は聞こえなかったが、わたしにはカメが何を言っているのか、なぜか理解することができた。
(見ろ…)
……見ろ? どこを?
すると突然、まわりの風景が、すべて変わった。カメも、夜空も、公園の木立も、ゴミ箱も、立て札も、すべて消えて、わたしは、古ぼけたベンチといっしょに、真昼の山野木立の中に呆然と立っていた。
下を見下ろすと、細い木立の間から、昔わたしが通っていた小学校の校舎が小さく見えた。その景色には確かに見覚えがあった。わたしは、目をぱちぱちさせながら周囲を見回した。すると、わたし自身は一歩も動かないのに、景色がどんどん動き始めた。わたしは、ベンチの上にしりもちをつくと、海の真ん中で流木にしがみつく遭難者のように、背もたれをしっかりつかんだ。
景色は、丘の木立の間に刻まれた細い道を、頂上に向かって歩いていた。そして景色が移っていくに従って、わたしの心は恐怖を感じ始めていた。これ以上、進んではいけないと、わたしは思った。わたしは、何かを思い出すのを恐れていた。だが、景色はわたしを無視して、どんどん進んでいく。そしてわたしは目を閉じることもできない。
不意に木立がなくなり、目の前に草原が広がった。そのとき、耳元でかわいらしい鈴のような声が響いた。わたしははっと顔をあげた。みずみずしい黒髪をした少女が、わたしの方を見てほほ笑んでいた。
きん、と、頭の奥で何かが折れる音がした。闇が、少女の顔を一瞬のうちに塗りつぶした。
どれくらい時間がたったのか、目覚めた時にはもう、空の高い所に太陽がのぼっていた。わたしははっと起き上がり、まわりを見回した。すると公園の中で遊んでいた子供たちが、物珍しそうにこっちを見ながら、ひそひそ話をしていた。わたしはいたたまれなくなり、バッグをさっと持ち上げると、逃げるように公園を出た。甲高い子供の笑い声が、わたしの背中を刺した。
(つづく)