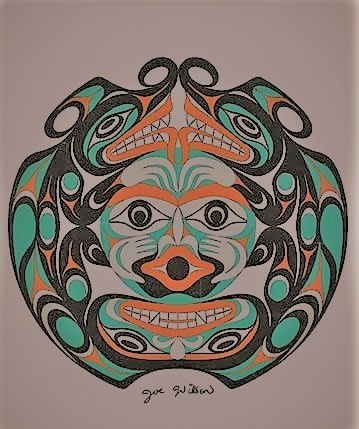アシメックがいなくなってしばらくすると、オラブは木の陰から出てきた。それは髭も髪も荒れ放題に伸ばした、醜い小男だった。青白い顔をして、痩せている。手にはネズミの頭蓋骨を持っていた。腹をすかせたときにそれをしゃぶるためだ。
オラブは入り口から山を出ると、イタカの野に目をめぐらした。そして遠目の効く目で、もう誰もいないことを十分に確かめた。オラブは知らなかった。自分が人よりずっと目がよく、遠くのものや暗いところにあるものを、実によく見ることができることを。だから人が暗いところに隠した栗の壺なども、すぐに見つけることができるのだ。
「へっ」
オラブは入り口を覆う木の下に、アシメックの大きな足跡を見つけると、つばを吐くように言った。馬鹿馬鹿しい。謝るなんていやだ。おれはここで、ひとりで暮らしている方がいいんだ。
オラブはねぐらにしている木の根元に戻ると、シロルから盗んだ栗の壺の中に手を入れた。そして皮をむいた栗の実をふたつとりだして、それを噛んだ。火で煮ていない栗は硬かったが、それでも食うとうまかった。オラブは煮炊きなどほとんどしなかった。火を起こす錐は一応持っていたが、煙が出れば居所をすぐに見つけられてしまう。だから、激しく米が食いたくなったとき以外は、めったに火など起こさなかった。
冬の山は寒い。雪に降られれば魔にさそわれる。だからふもとの方に下りてきていたのだが、まさかアシメックがこんな時に山に来るとは思わなかった。オラブは内心、見つからなくてよかったと思っていた。アシメックに見つかれば、きっと無理矢理村に戻されるだろう。体力では、オラブはアシメックにはとてもかなわない。