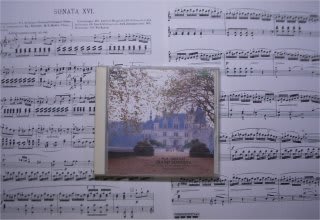今年楽しんだ音楽、書籍、映画などで、特に印象的だったものをあげてみます。
(1)山響、そして室内楽。山響の演奏会には、条件が許す限りせっせと通いました。今年はテレビでも放映され、県外でも少しは知名度が上がったかな?オーケストラとしての活動のほか、団員の方々を中心に、室内楽の活動が活発です。パストラーレ室内合奏団によるベートーヴェンの「七重奏曲」など、ほんとに楽しかったし、メンバーの方からお葉書などを頂戴して、ありがたかった。テルサ・ホールと文翔館は好きですが、県民会館はどうも・・・。来年は、山形弦楽四重奏団の演奏会にも行きたいと願っております。
(2)音楽CDを相変わらず購入しましたが、CD店からクラシックがどんどん後退しているのが悲しい。ネットショップ栄えて地方の店舗はすたれてしまうのでしょうか。今までロングテールをになっていた小規模店舗が、フラット化の大波に飲み込まれていくようです。印象的なのはエルガー作品を知ったこと。
(3)劇場で映画を見ました。『武士の一分』『バルトの楽園』が印象的でした。同日に『ミッション・インポシブルIII』も見たはずだが、どんな映画だったか内容を思い出せない。もう忘れてしまいました。
(4)たくさん本を読みました。ディケンズ作品とともにインパクトがあったのは、やはりフリードマン『フラット化する世界』(上下巻)でしょうか。今年最大の収穫だったような。あとは、平岩弓枝さんの本を読んでいる途中で、どうしても急カーブを切りたくなり、いきなり読み始めたデュマ『モンテ・クリスト伯』。なんと10回を越える連載になっておりますが、コメント・トラックバックが来ないという点からも、ほとんど自己満足の世界となっております。でも、いいのです。ブログの世界でも、誰もやらないことをやることに意味があるのですから(^o^)/
ちなみに、今年の備忘録から、自作スクリプトで読了書籍一覧を調べると、
>awk -f book.awk memo2006.txt
2006/01/01 吉田司『宮沢賢治殺人事件』読了
~
2006/12/27 酒見賢一『墨攻』を読了
以上、76 件
でした。
(5)展覧会では、仙台市文学館の「藤沢周平の世界展」を見に行きました。作家の日常を実際に目にするようで、見ごたえがありました。また、妻と二人で鶴岡にも足を運び、秋の楽しい一日となりました。
(6)のんびりした旅行らしい旅行はぜんぜんできませんでした。でも、子どもが大学に合格し、入学を契機に東京小旅行を楽しみましたし、甥の結婚式でまた東京へ旅行するも、電車が大きく遅延するなど、ハプニングもありました。
(7)古いデスクトップ・パソコンを2台処分し、なおかつ液晶ディスプレイを更新しました。部屋も広くなりましたが、17インチの広々とした画面は、たいへん見やすく便利です。Windows の新版の声も聞きますが、むしろ Linux 用の新規マシンに心がときめきます。でも、実際は十年乗った車の更新のほうが先でした。
(8)ブログ更新を続けて二年経過し、三年目に入りました。テキスト備忘録も、ときどき忘れていましたので、今年の分のWeblog記事を参照してデータを追補。こうしてみると、いただいたコメントやトラックバックの総数に驚きます。ありがたいことです。事情で更新できなくなる方もおられますが、それは仕方のないこと。現実には、転勤・転職等の事情で周囲の方々と疎遠になってしまうケースも少なくありません。でも、デジタル通信ネットワーク上では、地理的な制約を越えて、きっとまたどこかでお会いできることでしょう。
写真は今日の当地の空です。干柿が田舎の風情を出していると思います。
みなさま、どうぞ良い新年をお迎えください。
(1)山響、そして室内楽。山響の演奏会には、条件が許す限りせっせと通いました。今年はテレビでも放映され、県外でも少しは知名度が上がったかな?オーケストラとしての活動のほか、団員の方々を中心に、室内楽の活動が活発です。パストラーレ室内合奏団によるベートーヴェンの「七重奏曲」など、ほんとに楽しかったし、メンバーの方からお葉書などを頂戴して、ありがたかった。テルサ・ホールと文翔館は好きですが、県民会館はどうも・・・。来年は、山形弦楽四重奏団の演奏会にも行きたいと願っております。
(2)音楽CDを相変わらず購入しましたが、CD店からクラシックがどんどん後退しているのが悲しい。ネットショップ栄えて地方の店舗はすたれてしまうのでしょうか。今までロングテールをになっていた小規模店舗が、フラット化の大波に飲み込まれていくようです。印象的なのはエルガー作品を知ったこと。
(3)劇場で映画を見ました。『武士の一分』『バルトの楽園』が印象的でした。同日に『ミッション・インポシブルIII』も見たはずだが、どんな映画だったか内容を思い出せない。もう忘れてしまいました。
(4)たくさん本を読みました。ディケンズ作品とともにインパクトがあったのは、やはりフリードマン『フラット化する世界』(上下巻)でしょうか。今年最大の収穫だったような。あとは、平岩弓枝さんの本を読んでいる途中で、どうしても急カーブを切りたくなり、いきなり読み始めたデュマ『モンテ・クリスト伯』。なんと10回を越える連載になっておりますが、コメント・トラックバックが来ないという点からも、ほとんど自己満足の世界となっております。でも、いいのです。ブログの世界でも、誰もやらないことをやることに意味があるのですから(^o^)/
ちなみに、今年の備忘録から、自作スクリプトで読了書籍一覧を調べると、
>awk -f book.awk memo2006.txt
2006/01/01 吉田司『宮沢賢治殺人事件』読了
~
2006/12/27 酒見賢一『墨攻』を読了
以上、76 件
でした。
(5)展覧会では、仙台市文学館の「藤沢周平の世界展」を見に行きました。作家の日常を実際に目にするようで、見ごたえがありました。また、妻と二人で鶴岡にも足を運び、秋の楽しい一日となりました。
(6)のんびりした旅行らしい旅行はぜんぜんできませんでした。でも、子どもが大学に合格し、入学を契機に東京小旅行を楽しみましたし、甥の結婚式でまた東京へ旅行するも、電車が大きく遅延するなど、ハプニングもありました。
(7)古いデスクトップ・パソコンを2台処分し、なおかつ液晶ディスプレイを更新しました。部屋も広くなりましたが、17インチの広々とした画面は、たいへん見やすく便利です。Windows の新版の声も聞きますが、むしろ Linux 用の新規マシンに心がときめきます。でも、実際は十年乗った車の更新のほうが先でした。
(8)ブログ更新を続けて二年経過し、三年目に入りました。テキスト備忘録も、ときどき忘れていましたので、今年の分のWeblog記事を参照してデータを追補。こうしてみると、いただいたコメントやトラックバックの総数に驚きます。ありがたいことです。事情で更新できなくなる方もおられますが、それは仕方のないこと。現実には、転勤・転職等の事情で周囲の方々と疎遠になってしまうケースも少なくありません。でも、デジタル通信ネットワーク上では、地理的な制約を越えて、きっとまたどこかでお会いできることでしょう。
写真は今日の当地の空です。干柿が田舎の風情を出していると思います。
みなさま、どうぞ良い新年をお迎えください。