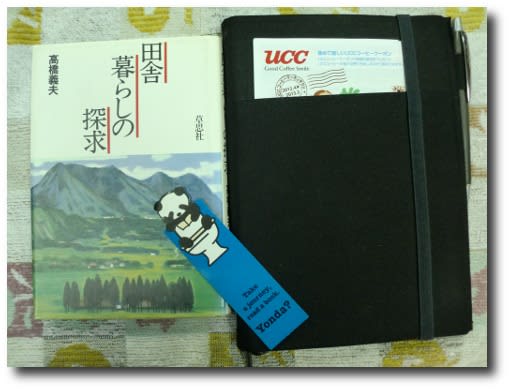都会人が田舎に憧れ、田舎暮らしをしたいと願う実例は多いようで、「田舎暮らし」をメインに掲げた雑誌もあるそうです。また、「定年帰農」というようなキーワードを打ち出した特集も、ときに散見されます。そういえば、当ブログにも「週末農業」などというカテゴリーがあって、体裁の良い収穫の話などをよく記事にしていますが、苦労や汚れ仕事の話はあまりしていませんね(^o^;)>poripori
本書は、作家の高橋義夫さんの、1980年代前半までの田舎暮らしルポを雑誌に発表したものに手を入れてまとめられたもののようです。雑誌がこういう連載を持つようになったということに、バブル期以前の、これからバブルに向かう時代の空気を感じます。舞台は長野県木島平村で、無人となった保育園を借りて住むようにした話から、田舎暮らしの裏と表を、おもしろおかしく、でも実にリアルに、描いています。
田舎暮らしを楽しめるのは、実は生活基盤~とくに職業的・経済的な~がしっかりあって、一定の余裕がある場合だろうと思います。作者は、いかに呑気で無頓着に見えようとも、小説家としてのスキルとテーマを持ち、連載してくれる雑誌と編集者との人間的なつながりを持っています。サラリーマンが突然田舎に憧れ、田舎暮らしに飛び込もうとしたと仮定して、うーむ、できるんだろうか。実際問題として、せいぜい楽観的に言ったとしても、なかなか楽ではなかろうよ、と言わざるを得ないと思います。
本書は、作家の高橋義夫さんの、1980年代前半までの田舎暮らしルポを雑誌に発表したものに手を入れてまとめられたもののようです。雑誌がこういう連載を持つようになったということに、バブル期以前の、これからバブルに向かう時代の空気を感じます。舞台は長野県木島平村で、無人となった保育園を借りて住むようにした話から、田舎暮らしの裏と表を、おもしろおかしく、でも実にリアルに、描いています。
田舎暮らしを楽しめるのは、実は生活基盤~とくに職業的・経済的な~がしっかりあって、一定の余裕がある場合だろうと思います。作者は、いかに呑気で無頓着に見えようとも、小説家としてのスキルとテーマを持ち、連載してくれる雑誌と編集者との人間的なつながりを持っています。サラリーマンが突然田舎に憧れ、田舎暮らしに飛び込もうとしたと仮定して、うーむ、できるんだろうか。実際問題として、せいぜい楽観的に言ったとしても、なかなか楽ではなかろうよ、と言わざるを得ないと思います。