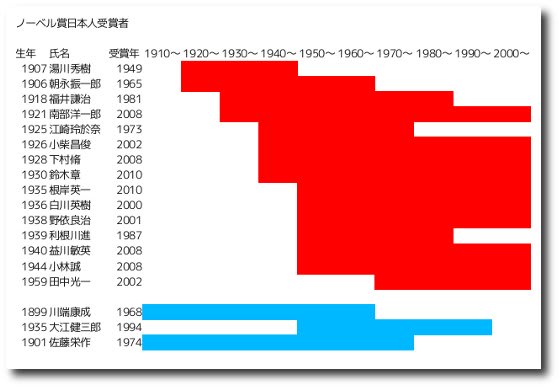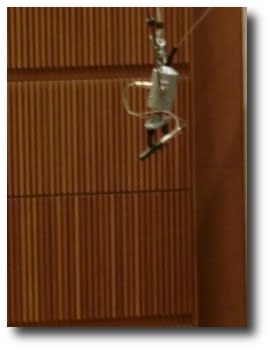当ブログにときどきコメントをいただく 林 侘助。さんが、A5型パソコンに Linux をインストールして、使えるかどうかを試している(*)ようです。林さんは、もともとWindowsユーザーで、業務上でもMS-Accessを中心に、合理的に便利に使ってこられました。2010年10月の「音楽日誌」によれば、脳ミソに喝!!を入れるためと称して、UbuntuLinux にチャレンジ中。実際は、試してみた結果「やっぱりや~めた」となる可能性もないわけでもありませんが、意外性のあるレポートになっています。
そういえば、当方の身近にも、Linux に興味を示す方が増えているような気がします。景気が悪く収入もダウンする中で、なくてはならない存在になっているパソコン関係の経費圧縮という動機が大きな要因になっているのだろうと思いますが、もう一つ、Linux の側にも、使いやすさがだいぶ向上しているから、という面もあるからでしょう。
慣れ親しんだ Windows XP から、Vista や Windows7 に替えるべき時期ではありますが、操作性もだいぶ変わっています。どうせまたいろいろ覚えなければならないのなら、Ubuntuのような新しいものに挑戦するのも同じことだ、という割り切り方もあるかもしれません。
かつて、フロッピーディスクの抜き差しに際して、Linux ではマウントやアンマウントというコマンド操作が必要になるなど、敷居の高い面がありました。でも、今は USBメモリの時代です。「安全な取り外し」を選んで抜き取るという操作は、Windows も Linux も共通になっています。実は、どちらもアンマウントを実行しているのですね。そんなふうに、メールやWEB閲覧、ブログの更新やデジカメ写真の編集管理などを中心とする利用では、もはや OS の違いをそれほど意識しなくても良くなってきています。
長年、蓄積したテキストファイルがある場合は、文字コードを一括変換するなどの対策を取る必要があるでしょうが、たいへん興味深いところです。
(*): KechiKechiClassics~2010年10月の音楽日誌及びBBSより
そういえば、当方の身近にも、Linux に興味を示す方が増えているような気がします。景気が悪く収入もダウンする中で、なくてはならない存在になっているパソコン関係の経費圧縮という動機が大きな要因になっているのだろうと思いますが、もう一つ、Linux の側にも、使いやすさがだいぶ向上しているから、という面もあるからでしょう。
慣れ親しんだ Windows XP から、Vista や Windows7 に替えるべき時期ではありますが、操作性もだいぶ変わっています。どうせまたいろいろ覚えなければならないのなら、Ubuntuのような新しいものに挑戦するのも同じことだ、という割り切り方もあるかもしれません。
かつて、フロッピーディスクの抜き差しに際して、Linux ではマウントやアンマウントというコマンド操作が必要になるなど、敷居の高い面がありました。でも、今は USBメモリの時代です。「安全な取り外し」を選んで抜き取るという操作は、Windows も Linux も共通になっています。実は、どちらもアンマウントを実行しているのですね。そんなふうに、メールやWEB閲覧、ブログの更新やデジカメ写真の編集管理などを中心とする利用では、もはや OS の違いをそれほど意識しなくても良くなってきています。
長年、蓄積したテキストファイルがある場合は、文字コードを一括変換するなどの対策を取る必要があるでしょうが、たいへん興味深いところです。
(*): KechiKechiClassics~2010年10月の音楽日誌及びBBSより