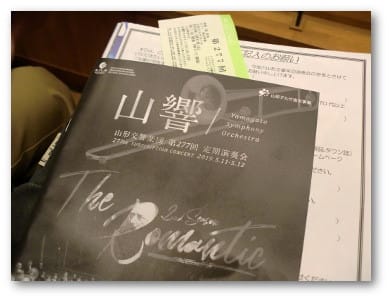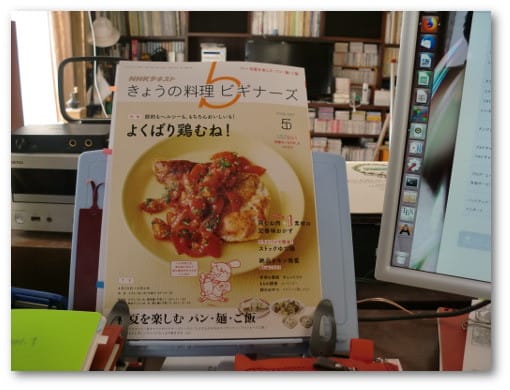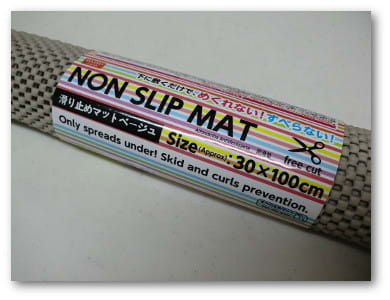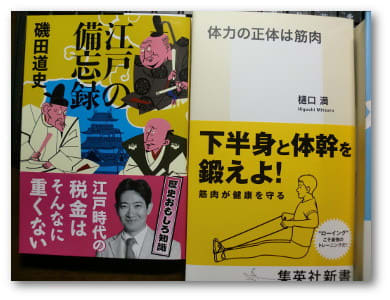このところ、料理が楽しいです。新米シェフの例にもれず、覚えたてだからという理由もありますが、もう一つ、この楽しさには既視感があります。
中学生の頃、実験室に入り浸って毎日のように化学実験をしていたとき、いろいろな化学薬品の性質を試したり知ることが面白かった、あれと似ています。例えば同じ酸といっても一つ一つ特徴的な性質があり、使い方も適切な濃度や温度に保つ必要があるなど、個別の知識を知り、それを組み合わせていく楽しさ、面白さです。
今、料理をしているときに感じるのは、その時の気分に近いのかも。例えばオリーブオイルにニンニクを入れ、加熱するときは高温にしてはならない。むしろ低温でじっくり加熱するほうが良いのは、たぶん親油性の成分を抽出するためで、高温だとニンニクの表面が固くなり、成分が抽出されにくいからなのでしょう。また、タケノコを湯がくのは、単にえぐみ成分を流出させるだけではなくて、大量に含まれるチロシンからホモゲンチジン酸等のえぐみ成分を生じさせる酵素の働きを熱変性によって失活させるためなのでしょう。
うーむ。昔、生化学等の講義で習った知識が、立体的によみがえります。たぶん、こうするとうまく行くだろうと予想し、やってみると調理技術的にドンピシャだったりします。で、出来上がった料理が美味しいのですから、楽しくないはずがありません。家族が「化学実験のような料理」と評するのは、意外に本質をついているのかもしれません(^o^)/

中学生の頃、実験室に入り浸って毎日のように化学実験をしていたとき、いろいろな化学薬品の性質を試したり知ることが面白かった、あれと似ています。例えば同じ酸といっても一つ一つ特徴的な性質があり、使い方も適切な濃度や温度に保つ必要があるなど、個別の知識を知り、それを組み合わせていく楽しさ、面白さです。
今、料理をしているときに感じるのは、その時の気分に近いのかも。例えばオリーブオイルにニンニクを入れ、加熱するときは高温にしてはならない。むしろ低温でじっくり加熱するほうが良いのは、たぶん親油性の成分を抽出するためで、高温だとニンニクの表面が固くなり、成分が抽出されにくいからなのでしょう。また、タケノコを湯がくのは、単にえぐみ成分を流出させるだけではなくて、大量に含まれるチロシンからホモゲンチジン酸等のえぐみ成分を生じさせる酵素の働きを熱変性によって失活させるためなのでしょう。
うーむ。昔、生化学等の講義で習った知識が、立体的によみがえります。たぶん、こうするとうまく行くだろうと予想し、やってみると調理技術的にドンピシャだったりします。で、出来上がった料理が美味しいのですから、楽しくないはずがありません。家族が「化学実験のような料理」と評するのは、意外に本質をついているのかもしれません(^o^)/