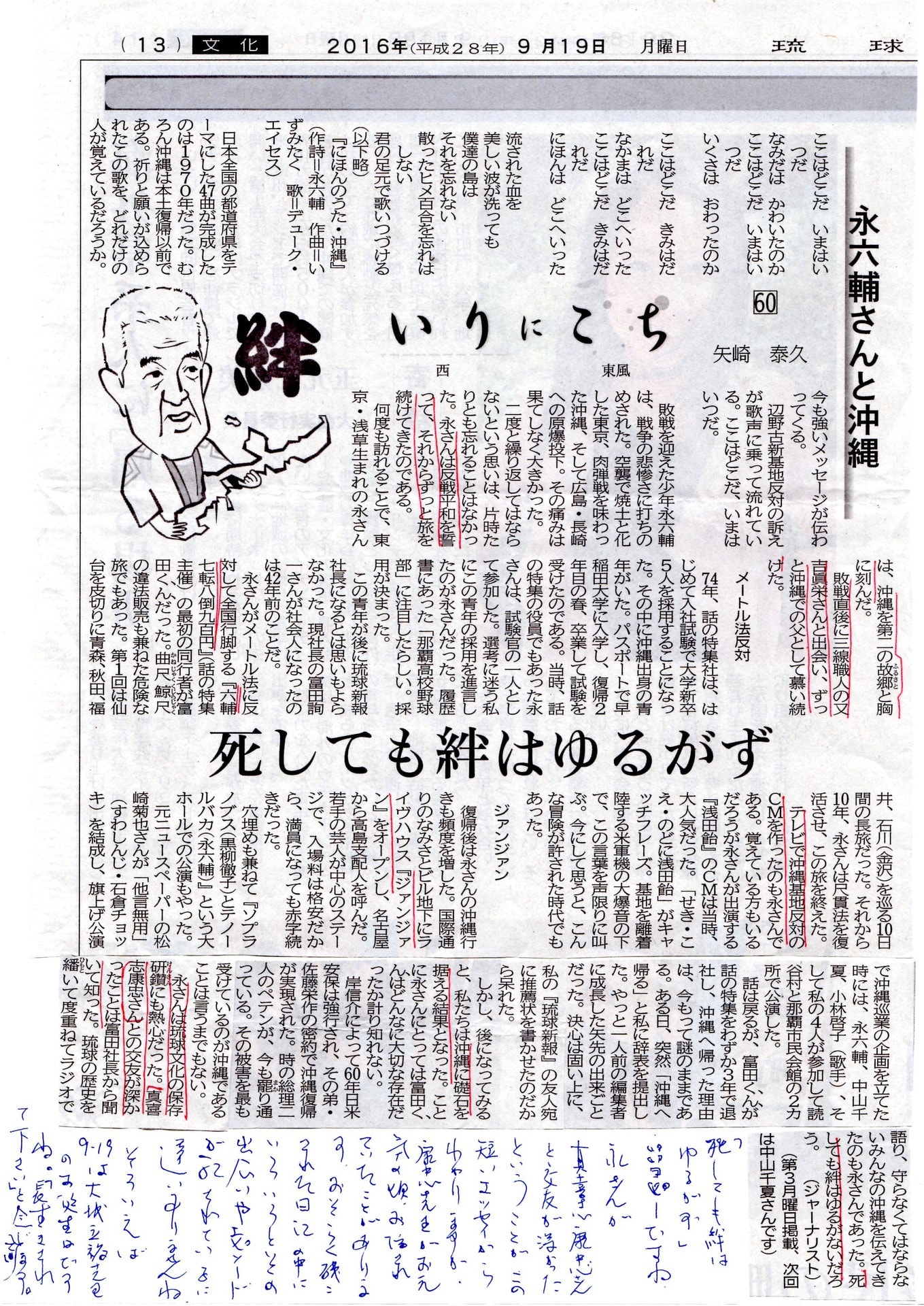
先月の新聞記事だが、いい話なのでこのブログでも紹介したいと思った。永六輔さんはよく沖縄にやってきた方だったが、親しくお話する機会はなかった。でも確か真喜志康忠さんのお話の中に登場してきた方だった。上原直彦さんたちが東京で沖縄音楽コンサートの催しをした時、「何かお手伝いすることがありませんか」と来られたことがあったという。「何もないですよ」と上原さんは答えたという。しかし当の永さんは、会場の入り口で案内係などのような手伝いをされたのらしい。何でもいい、役にたちたいと、永さんは労を惜しまない方だったのだ。
私の記憶はちょっと正確ではないのかもしれない。「靴番のような役割」と話していたのかもしれない。つまり決して綺麗で華やかではないところで、永さんは沖縄のためにと立ち居振る舞いができた方だったのである。単純に「いい話」だと思った。そして手渡された新聞のエッセイを読んだ。何と現琉球新報社長の富田諄一さんだけではなく、敬愛すべき真喜志康忠さんの名前が!永さんと康忠さんの付き合いは本当だったのだ。かなり多くのインタビュー録音テープを持っているが、その中にも、お二人のエピソードが録音されているはずである。そして10冊にも及ぶ日記にも。懐かしさがやってきた。
沖縄の「ますらお」の役者であり、戯作者、そして座長だった。「沖縄芝居実験劇場」では、演出家の幸喜良秀さん、作家の大城立裕さんと情熱的に現代沖縄芝居の舞台に挑んでいた。その貴重な時間を目撃することができたのは幸いだった。この御三人は戦後沖縄演劇を語る上で中軸になっている。20世紀から21世紀へその過度期の沖縄で彼らのパッションが生み出したもの、その貴重な沖縄の無形文化財としての「舞台芸術の力」が、現在にどう活かされているだろうか?劇団創造が「ウチナーグチ現代劇」を上演するようになった。リバイバル、歴史の修復だろうか?



















