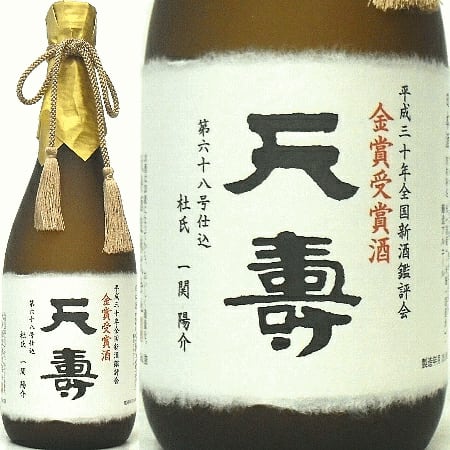2020年ヒット商品ランキング 日経トレンディが選んだベスト30 13~16位
16位 「スマホ証券」
初心者・若年層の投資意欲を増進。ネット大手に劣らぬ年30万口座ペース。
スマホ取引によって、株取引のハードルは低くなった。スマホを使える層には打ってつけ。
殆どの利用者にとって、大きな取引に発展することはなさそうだが・・・
15位 「popIn Aladdin 2」
天井からつる新発想で累計6万台超。より障害物に強い2代目が絶好調。
ステイホームも手伝ってか、自宅の快適性を求める1つのツールとなった。
シーリングライトを利用した発想は抜群である。
14位 「食べチョク/ポケットマルシェ」
厳選農家が売りの産直ECが躍進。リピーター続出で流通総額40倍も。
これまたステイホームが後押し。
外食用食材の売れ残りの必死の対応策でもある。「価格」が全ての売れ行きの最大要因に。
13位 「リングフィット アドベンチャー」
フィットネスとゲームの融合に成功。通年品薄で争奪戦も160万本突破。
任天堂が以前展開した「Fit」の進化系。
ステイホームも手伝いヒットの要因に。
13~16位まで、いずれも日経MJではランクインせず。
*日経X TREND HP より